「夜中に天井裏からバタバタと音が聞こえる」「天井から悪臭がする」と悩んでいませんか?実はその正体は、ハクビシンかもしれません。
ハクビシンによる被害は、天井裏の騒音やフンの悪臭だけではなく、建物の劣化や健康リスクに発展することもあるため、注意が必要です。
この記事では、ハクビシンが引き起こす4つの被害を詳しく解説します。自分でできる応急処置や対策する際の注意点まで分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

1. ハクビシンがもたらす4つの被害
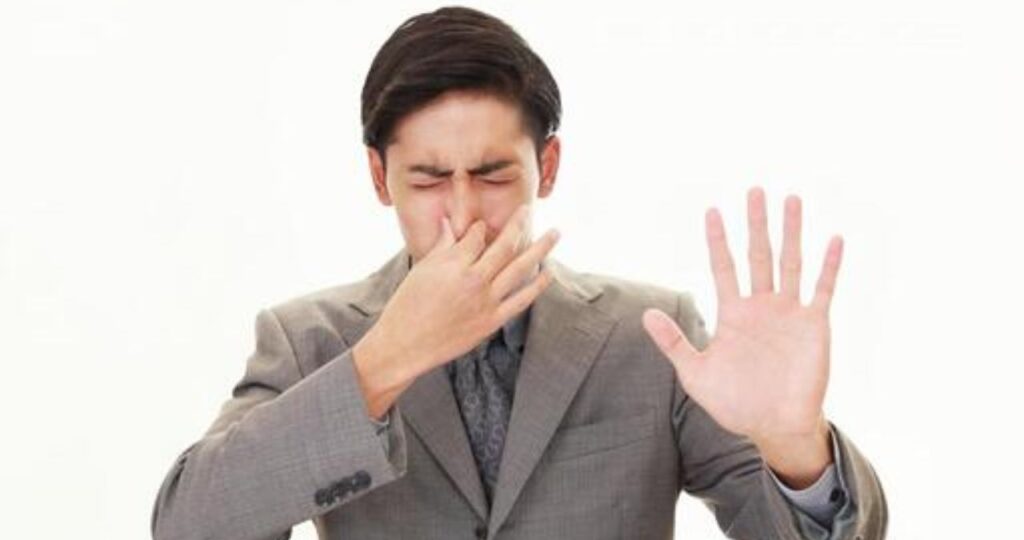
ハクビシンが住みつくと、生活環境に様々な悪影響が生じます。被害は騒音や悪臭、健康リスクまで広範囲に及び、放置すると状況がさらに悪化しかねません。
ここでは、ハクビシンがもたらす代表的な4つの被害を紹介します。
1-1. 足音や鳴き声による騒音被害
ハクビシンによる被害で最も気付きやすいのが、足音や鳴き声です。ハクビシンは夜行性で深夜に活動が活発になるため、就寝中の時間帯に天井裏でドタドタと走る音が響きやすく、生活リズムが乱れる原因になります。
さらに、子育て中は親子の鳴き声が頻繁に聞こえ、静かな時間がほとんどなくなることもあります。複数匹で住みついている場合は足音の量も増え、天井全体がきしむほどの騒音に発展するケースも少なくありません。
こうした騒音が続くと、不安やストレスが溜まり、日常生活にも悪影響が出る可能性があります。
1-2. 建物の腐食や悪臭を招くフン・尿被害
ハクビシンは同じ場所にフンを集める「ためフン」の習性があり、天井裏に入り込んだ場合、短期間で大量の排泄物が堆積します。フンには強烈なアンモニア臭が含まれ、家全体にニオイが広がるだけでなく、換気をしても悪臭が消えないことも多いです。
さらに、尿が天井板へ染み込むことで茶色いシミができ、木材が湿気を吸って腐りやすくなります。湿気が溜まるとカビが発生し、家屋の構造部分まで劣化が進む可能性があります。
また、湿気とフンが混ざることでダニやノミが繁殖しやすくなり、被害が健康面へ広がる危険性もあるため、注意が必要です。
この悪臭被害は、放置すればするほど修繕費が高額になるケースも多いため、早めの対策が大切です。
ハクビシンのフン被害については、以下の記事でも詳しく解説しています。
1-3. 農作物が荒らされる食害
ハクビシンは果物や野菜を好むため、家庭菜園や農地に侵入して作物を食べてしまいます。スイカやトマト、梨などの甘いものを狙う傾向が強く、食べ頃の実を食い荒らされることが多いです。
食べ散らかした果実や皮が地面に残され、被害に気付く時には収穫できる量が大幅に減ってしまっているケースも珍しくありません。
また、ハクビシンに一度餌場として認識されると繰り返しやってくるため、対策を講じない限り被害が続きやすい点が厄介です。
農家の場合は収入に影響が出るほど深刻な問題となり、長期的な損失に繋がる可能性があるため、被害に気付いた時点ですぐに対策することが大切です。
参考:農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル アライグマ、ハクビシン、タヌキ」
1-4. ノミ・ダニ、病原体による健康被害
ハクビシンのフンにはサルモネラ菌やトキソプラズマなどの病原体が含まれ、これらに感染すると発熱や下痢、腹痛などの症状が現れたり、重症化する危険があります。
また、ハクビシンやフンに引き寄せられたノミやダニが天井裏で増殖し、室内に入り込むと、皮膚のかゆみや発疹、アレルギー反応などが起きることもあります。
さらに、乾燥したフンが粉状になって空気中に舞うと、吸い込むことで気管支系のトラブルを引き起こす可能性もあるため、早めの対策が大切です。
ハクビシンのフンが原因の感染症については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:厚生労働省検疫所「サルモネラ感染症」/「トキソプラズマ症」
2. 自分でもできる応急処置の方法

ハクビシンの気配を感じたら、まずは応急的な対策で被害の拡大を抑えることが大切です。自宅でできる方法を実践するだけでも、一時的な追い出しや侵入防止の効果が期待できます。
ここでは、手軽にできる応急処置の方法を2つ紹介します。
2-1. 忌避剤などを活用した追い出し
ハクビシンは強いニオイを嫌うため、忌避剤を使った追い出しが効果的です。
市販の忌避剤には、スプレー・固形・煙タイプがあり、いずれも刺激臭を利用して屋根裏や軒下から一時的に追い出す仕組みです。長く同じタイプの忌避剤を使うと慣れてしまうため、複数タイプをローテーションしながら使用すると効果が続きます。
使用時は取扱説明書を確認し、必要に応じてマスクや手袋を着用しましょう。追い出した後は、隙間を必ず封鎖することが再侵入を防ぐために大切です。
忌避剤として有効な激臭シートについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2-2. 餌になるものを置かない
ハクビシンを遠ざけるためには、餌になるものを置かないことも大切です。雑食性のハクビシンは、生ゴミや果実、外に置きっぱなしのペットフードなどを目当てに近寄ってきます。
そのため、ゴミ箱は必ずフタを閉め、袋の口もしっかり縛るように意識すると安心です。ペットフードは屋外に置かず、食べ残しは早めに片づけましょう。
こうした日々の対策を積み重ねることで、ハクビシンが近寄りにくい環境が整い、被害の予防に繋がります。
3. ハクビシン被害の対策をする際の注意点

ハクビシン対策を進める際は、思わぬトラブルを避けるために守るべきポイントがあります。法律面のルールや衛生面の危険を理解していないと、逆に被害が大きくなる可能性があります。
安全に対処するためにも、事前に注意点を把握しておくことが大切です。
3-1. 無許可での捕獲や殺傷をしてはいけない
ハクビシンは鳥獣保護管理法の対象動物であり、無許可での捕獲や殺傷は法律違反です。
罠を設置する際は自治体への申請が必須で、手続きを踏まずに捕獲すると違法行為となります。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。
さらに、法律違反だけでなく近隣トラブルにも発展しやすいため、ハクビシン対策をする際は、必ず適切な方法で進めましょう。
鳥獣保護管理法・害獣駆除の許可申請については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:e-GOV「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
3-2. ハクビシンやフンに直接触れてはいけない
ハクビシンのフンには、サルモネラ菌やトキソプラズマなどの病原体が含まれることがあり、素手で触れる行為は非常に危険です。これらを吸い込んだり触れたりするだけでも感染リスクが高まるため、注意が必要です。
そのため、掃除を行う際は、必ず手袋やマスクを着用し、排泄物が乾燥して舞い上がらないように注意しましょう。
4. 本格的なハクビシン対策はプロへの依頼がおすすめ

自分でできる応急処置でも一定の効果はありますが、再発を確実に防ぐには、専門業者への依頼が最も効果的です。
本格的なハクビシン対策では、侵入口の封鎖と安全な作業を同時に進める必要があります。しかし、自力で実施する場合は侵入経路を正確に見つけることが難しく、一部を塞いだだけでは別の隙間から再び入り込まれるケースが多いです。
その点、プロは専用機材などを使用して家屋全体を調査し、金網や防獣パネル、専用パテを使って再侵入を防ぐための封鎖を徹底します。この工程は専門的な知識と経験が求められるため、確実に行うにはプロの施工が必要不可欠です。
さらに、ハクビシンの追い出しや清掃作業にはケガや感染症のリスクが伴います。フンや尿には寄生虫や病原菌が含まれており、素手で触れる行為は非常に危険です。また、屋根裏の作業では転落の危険もあるため、作業する際には安全対策を徹底する必要があります。
そのため、自ら危険な作業への対策や準備をする手間が省ける点も、プロに依頼する大きなメリットです。
5. ハクビシン被害にお悩みなら協会の無料相談をご活用ください!

「自分で対策しても状況が改善しない」「どんな業者に頼めばよいか分からない」という方は、ぜひ「日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」の無料相談をご活用ください。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会は、ハクビシンをはじめとした鳥類・害獣による被害に対し、安全で安心な生活環境を守るための防除・管理を専門とする団体です。
経験豊富な担当者が状況を聞き、効果的な対策のアドバイスや専門業者探しをお手伝いします。全国の信頼できる登録業者を紹介してもらえるため、悪質な業者トラブルを避けられます。
「こんな相談をしても良いのかな?」と感じるようなことでも、もちろん大丈夫です。ぜひお気軽にご相談ください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
ハクビシンによる被害は、騒音、悪臭、建物の劣化、健康リスクまで多岐にわたります。
応急処置として、追い出しやハクビシンが寄り付かない環境作りを行うことはできますが、根本的な解決には限界があります。法律上のルールや衛生面のリスクを踏まえると、本格的な対策は専門業者に依頼する方法が最も安全で確実です。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会では、無料相談を行っているため、ハクビシンの被害でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。


コメント