「夜中に天井裏でドタドタという音がする」「庭の作物が荒らされている」と悩んでいませんか?
その正体は、ハクビシンかもしれません。ハクビシンは、民家の屋根裏や畑に住みつき、フン害や悪臭、騒音を引き起こす厄介な害獣です。
こうした被害に悩む方の間で注目されているのが、「激臭シート」です。
本記事では、ハクビシン対策に有効な激臭シートについて、効果的な設置方法から併用したい対策まで分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

1. ハクビシン対策に激臭シートが効く理由
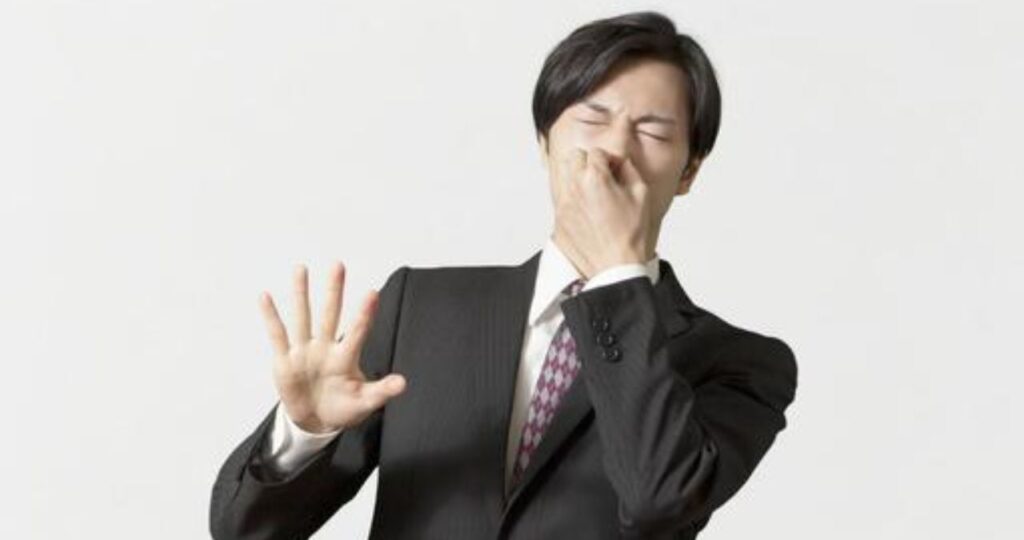
結論から言うと、激臭シートはハクビシンの「嗅覚と視覚」を刺激して近寄らせないための効果的なアイテムです。
ハクビシンが嫌う成分が含まれた激臭シートを設置すると、「危険な場所」と判断して近づかなくなります。
さらに、ハクビシンが苦手な色であれば、視覚的にも威嚇効果を発揮します。
1-1. 嗅覚を刺激!ハクビシンが嫌うニオイ
ハクビシンは人間よりもはるかに敏感な嗅覚を持っています。そのため、わずかな異臭でも不快感を覚え、居心地の悪い場所として避けるようになります。
特に嫌うニオイとして知られているのが、木酢液やハッカ油、アンモニアのような刺激臭です。
これらの成分はハクビシンにとって強い刺激となり、「危険な場所」と認識させる効果があります。
激臭シートには、これらのニオイ成分が染み込ませてあり、時間が経っても効果が続くようになっています。
また、屋外用・屋内用で配合成分や濃度が異なるため、設置場所に合った商品を選ぶことが大切です。
ハクビシンが苦手なニオイについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
1-2. 視覚で威嚇!ハクビシンが怖がる色
実は、ハクビシンは視覚にも一定の反応を示します。ハクビシンのような夜行性の哺乳類は、強い光や反射、急なコントラストの変化に敏感で、警戒してその場を離れることがあります。
そのため、激臭シートの中にも、ハクビシンが苦手な赤色などの反射素材を組み合わせたタイプが増えているのです。
このように、ニオイと見た目の両面から威嚇する仕組みによって、より強力な忌避効果を発揮するのが「激臭シート」の最大の強みです。
2. ハクビシンの被害を防ぐ!激臭シートの効果的な使い方

激臭シートは、ただ置くだけでは十分な効果を発揮できません。ハクビシンの通り道や出入口に近い場所など、適切に設置することが大切です。
ここでは、実際に被害が多い「屋外」と「屋内」に分けて、設置方法のコツを紹介します。
2-1. 【屋外編】畑や庭など場所別の激臭シート設置方法
屋外では、ハクビシンが通るルートを特定することが最も重要です。足跡やフンの位置を確認し、畑・庭・屋根の登り口などの通り道を重点的に防ぐように設置しましょう。
畑の場合は、作物の周囲や地面に沿ってシートを設置します。支柱や杭に吊るして風に揺らすことで、ニオイの拡散と視覚的な威嚇の両方を狙えます。
特に、ハクビシンが好む甘い果物畑では、1〜2m間隔でシートを配置すると効果的です。
庭では、物置やゴミ置き場、家庭菜園など、ハクビシンがエサを探しに来る場所の近くに設置します。また、屋根や塀をよじ登るケースもあるため、雨樋の下やブロック塀の上などのルートにも注意が必要です。
設置後は、雨や風でシートが飛ばされたり、ニオイが薄くなったりすることがあるため、定期的に点検し、状態を確認しましょう。
庭でのハクビシン対策については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル アライグマ、ハクビシン、タヌキ」
2-2. 【屋内編】屋根裏や床下への激臭シート設置方法
屋内の場合、侵入したハクビシンを追い出すために使うことが多くなります。
設置場所は、ハクビシンの出入り口付近や、フンが集中している箇所が効果的です。複数の場所に分散して置くことで、空間全体にニオイが広がり、再侵入を防ぎやすくなります。
ただし、通気の悪い空間ではニオイがこもることがあります。そのため、作業を行う際はマスクや手袋を着用し、可能であれば換気を行いながら設置してください。
また、床下に設置する場合は湿気によってニオイが弱まりやすいため、定期的に効果の確認を行いましょう。
2-3. 効果はいつまで?激臭シートの交換時期の目安
激臭シートの効果は、おおよそ1年程度が目安とされています。
ただし、設置環境によって持続期間は変わります。直射日光が強い場所や風雨にさらされやすい環境では、成分の揮発や劣化が早まり、効果が短くなることがあるため、注意が必要です。
特に、台風や豪雨などの極端な気象条件下では、忌避効果が十分に現れない場合もあります。
また、シートが汚れたり、ニオイが薄くなったりした場合は、1年を待たずに早めの交換を行うと安心です。
3. 激臭シートだけでは不十分?併せて行いたいハクビシン対策

激臭シートは強力な忌避効果を持ちますが、それだけで被害を完全に防ぐことは難しいのが現実です。なぜなら、ハクビシンは学習能力が高く、ニオイに慣れてしまうケースがあるためです。
そのため、激臭シートを活用しながら、環境の改善や侵入経路の封鎖など、複数の対策を組み合わせることが重要になります。
ここでは、激臭シートと併せて行うべき2つの基本対策を紹介します。
3-1. 寄せ付けない環境作り!ハクビシンの餌になるものを撤去する
ハクビシンが人の住まいに近づく最大の理由は、「食べ物」です。畑の果実、家庭菜園の野菜、さらには生ゴミやペットフードまでも、彼らにとっては格好の餌になります。
そのため、まずは周囲の環境を整えることが重要です。
具体的には、熟した果物や収穫し忘れた作物は早めに取り除きましょう。生ゴミはしっかりフタの閉まる容器に入れて保管し、夜間は屋外に出しっぱなしにしないことが大切です。
また、ペットフードを庭やベランダに置いたままにするのも避けましょう。
これらを徹底することで、ハクビシンが「ここには餌がない」と判断し、自然と近寄らなくなります。
3-2. 最も重要!ハクビシンの侵入経路を物理的に塞ぐ
ハクビシン対策で最も効果が高いのは、侵入経路を完全に封鎖することです。ハクビシンは直径8cmほどの穴があれば、簡単に体をねじ込んで侵入することができます。
侵入経路になりやすい場所としては、以下が挙げられます。
- 屋根と外壁の接合部
- 軒下や通気口
- 床下の通風口
- 屋根裏への点検口
これらの箇所を金網や防獣ネットで塞ぐことで、ハクビシンの出入りを防げます。
ただし、建物の構造によっては封鎖が難しいケースも多いため、無理をせず専門業者への相談を検討しましょう。
4. 本格的なハクビシン対策はプロに依頼すべき理由

ここまで紹介したように、激臭シートや環境改善で一定の効果は期待できます。しかし、本格的に被害を止めたい場合は、専門の駆除業者へ依頼するのが最も確実です。
ここでは、ハクビシン対策をプロに依頼すべき理由を詳しく見ていきましょう。
4-1. 封鎖作業を完璧に行うのは高難易度だから
ハクビシンの侵入経路を見つけ出し、すべてを完全に塞ぐ作業は非常に難しいです。
その点、プロは専用機材等を使用して被害箇所を徹底的に調査します。その上で、金網・防獣パネル・専用パテなどを使い、再侵入されないように徹底的に封鎖します。
つまり、一部だけ塞いでも、別の場所から侵入されるケースが多いため、プロの施工による完全封鎖が重要なのです。
4-2. ケガ・病気のリスクがあるから
ハクビシンは見た目が愛らしくても、噛みついたり感染症のリスクがあります。また、フンや尿には寄生虫や病原菌が含まれており、素手で触れると健康被害に繋がる恐れもあります。
さらに、屋根裏など高所での作業は転落の危険があるため、専門知識と装備が必要です。
その点、プロは防護服・手袋・マスクを着用し、危険を回避しながら作業を安全に行ってくれるのが大きなメリットです。
ハクビシンが原因で起こる感染症については、以下の記事で詳しく解説しています。
5. ハクビシン被害でお悩みなら協会の無料相談をご活用ください!

「激臭シートを使っても被害が減らない」「どこから入っているのか分からない」そんな場合は、ぜひ「日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」の無料相談をご活用ください。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会は、ハクビシンをはじめとした鳥類・害獣による家屋被害に対し、安全で安心な生活環境を守るための防除・管理を専門とする団体です。
経験豊富な担当者が状況を聞き、効果的な対策のアドバイスや専門業者探しをお手伝いします。全国の信頼できる登録業者を紹介してもらえるため、悪質な業者トラブルを避けられます。
「こんなことを聞いても良いのかな?」と思うような内容でも、もちろん大丈夫です。ぜひお気軽にご相談ください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
激臭シートは、ハクビシンの嗅覚と視覚を同時に刺激し、近寄らせないための優れたアイテムです。
屋外では通り道や畑周辺に、屋内では侵入口やフン害箇所に設置することで高い効果を発揮します。ただし、ニオイへの慣れや気象条件によって効果が変化するため、定期的な交換と環境整備が不可欠です。
自力での対応が難しい場合は、専門業者や協会の無料相談を利用し、安全かつ確実な駆除を行いましょう。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会では、無料相談を行っているため、ハクビシンの被害でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。


コメント