ハクビシンの被害に悩んでいませんか?夜中に屋根裏から足音がしたり、天井にシミや悪臭が発生したりする場合、ハクビシンが住みついている可能性があります。
その際、「毒餌を使えば簡単に追い出せるのでは?」と考える人もいますが、これは絶対に行ってはいけません。
毒餌による駆除は法律で厳しく制限されており、無断で実施すると懲役や罰金を科される可能性があります。
この記事では、毒餌が禁止されている理由や、一般の方でもできる安全な駆除方法を解説します。ハクビシンを放置した場合に起こり得る被害まで分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

1. ハクビシン駆除に毒餌を無断で使用してはいけない
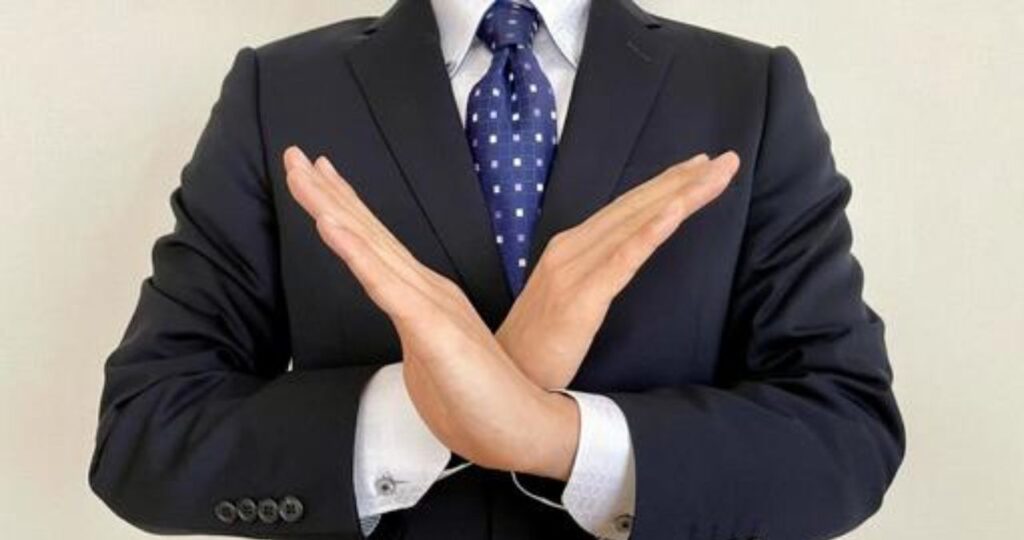
まず結論から言うと、毒餌を使った駆除は行ってはいけません。なぜなら、ハクビシンは「鳥獣保護管理法」によって保護されている野生動物だからです。
この法律では、自治体の許可を得ずに捕獲・殺傷する行為を禁止しています。
1-1. 鳥獣保護管理法で制限されている
ハクビシンは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」によって保護されています。
この法律では、自治体の許可を得ずに捕獲・殺傷する行為を禁止しており、毒餌を使用した駆除もその対象に含まれます。
もし無許可で毒餌を設置してハクビシンを死なせてしまうと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される場合があります。
そのため、個人が毒餌を使用することは、法的にも衛生的にも絶対に避けてください。
鳥獣保護管理法・害獣駆除の許可申請については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:e-GOV「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
1-2. 罠を使った捕獲の方が自治体に許可されやすい
もし本格的な駆除を行う場合は、自治体に「有害鳥獣の捕獲許可」を申請し、罠を使用する方法が一般的です。箱罠はホームセンターなどでも入手可能ですが、使用には必ず事前の許可が必要です。
自治体の担当課に相談すれば、被害の状況に応じて許可申請の流れを案内してもらえます。申請が通ると、一定期間の間、罠を設置することが認められます。
ただし、申請書類の作成や報告義務などの手続きがあり、個人では難しいことも多いです。そのため、捕獲許可を持つ専門業者に依頼する方が、迅速で確実に被害を解決できるケースが大半です。
専門業者であれば、許可取得・捕獲・清掃・再発防止まで一貫して対応してくれるため、不安がある場合は一度相談してみましょう。
2. 自治体の許可なしで試すことのできる駆除方法

毒餌を使うことはできませんが、自治体の許可を得ずにできる合法的な対策もあります。基本は「追い出す」「寄せつけない」「侵入させない」の3ステップです。
ここでは、即効性のある追い出し方法から長期的な再侵入防止まで、許可なしで実行できる具体的な手順を紹介します。
2-1. 忌避剤を用いて追い出す
ハクビシンは嗅覚が非常に発達しており、刺激の強いニオイを嫌います。その性質を利用して、忌避剤を使って追い出す方法が効果的です。
市販の忌避剤には、以下のようなタイプがあります。
| タイプ | 仕組み | 主な使用場所 |
|---|---|---|
| スプレー | 刺激臭を直接噴霧して不快感を与え、 ハクビシンを追い出す | 屋根裏の出入口付近、軒下、倉庫の隅など |
| 固形 | 揮発性のニオイを長時間放出して、 通路に持続的なバリアを作る | 通り道や軒下、庭木の根元など |
| 煙 | 煙で巣や隙間全体にニオイを行き渡らせ、 一斉に追い出す | 屋根裏全体や天井裏など |
忌避剤を使用する際は、同じタイプを使い続けるとハクビシンが慣れてしまうため、2〜3種類をローテーションして使用すると効果が長持ちします。
また、忌避剤はあくまで「追い出し」のための手段であり、追い出した後に隙間を確実に封鎖することが再侵入を防ぐために大切です。
さらに、人やペット、植物への安全性は製品によって異なるため、使用前には必ず取扱説明書を確認し、必要に応じて手袋やマスクを着用しましょう。
ハクビシンが苦手なニオイについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
2-2. ハクビシンの寄りつかない環境を整える
ハクビシンを寄せつけないためには、餌となるものを徹底的に取り除くことも重要です。ハクビシンは雑食性で、人間の生活ゴミや果物、ペットフードなどを狙ってやってきます。
そのため、ゴミ箱のフタはしっかり閉め、袋の口も二重に縛っておきましょう。ペットフードを屋外に置いたままにせず、食べ残しは必ず片づけるようにすると安心です。
また、庭木に実る果物は熟す前に早めに収穫し、落ちた果実は放置しないようにしましょう。
こうした小さな工夫を積み重ねることで、ハクビシンが「居心地の悪い場所」と判断し、被害の予防に繋がります。
2-3. ハクビシンの入る隙間を封鎖する
ハクビシンは体が柔らかく、わずか8cmほどの隙間からでも侵入できます。そのため、屋根の隙間、軒下、通風口、床下などを点検し、金網やパンチングメタルなどで塞ぎましょう。
封鎖する際は、必ず「内部から完全にハクビシンを追い出したあと」に行うことが重要です。また、換気口や通風口には防獣ネットを取り付けると、通気を確保しながら侵入を防ぐことができます。
ハクビシンによる被害が広がっている場合や侵入口が特定できない場合は、専門業者の現地調査を受けることをおすすめします。
3. ハクビシンを放置した場合に起きる被害

ハクビシンを長期間放置すると、住環境や健康に深刻な影響を及ぼします。見た目は小さな被害でも、時間が経つにつれて悪臭・騒音・衛生面の問題が拡大し、修繕費が高額になるケースも少なくありません。
ここでは、ハクビシンを放置した場合に起きる代表的な3つの被害を紹介します。
3-1. 悪臭被害
ハクビシンは巣の近くにフンや尿をためる「ため糞」の習性があります。長期間住みつくと天井裏や壁の中にフン尿が大量に溜まり、強烈な悪臭が発生します。
この悪臭は木材や断熱材に染み込み、掃除だけでは除去が難しいです。また、尿によって木材が腐食し、天井や梁が劣化して家屋へのダメージに繋がることもあります。
このように、悪臭は単なるニオイの問題にとどまらず、家屋全体の劣化を招く深刻な被害に発展することもあるため、注意が必要です。
3-2. 騒音被害
ハクビシンは夜行性で、主に夜間に活動します。そのため、夜になると天井裏で走り回る足音や、巣の中で子どもを育てる鳴き声が聞こえることがあります。
特に、繁殖が盛んになる春先は複数匹が出入りし、ドタドタと走る音が響くケースも少なくありません。
これらの騒音が長期間続くと、睡眠不足やストレスを引き起こし、精神的な負担も大きくなりかねないため、早めの対策が大切です。
3-3. 健康被害
ハクビシンのフンや尿には寄生虫や細菌が含まれており、放置すると健康被害のリスクが高まります。
代表的なものには、サルモネラ症やトキソプラズマ症などがあります。これらに感染すると、発熱・下痢・倦怠感などの症状が現れ、重症化する場合もあるため、注意が必要です。
また、フンにダニやノミが発生して室内に侵入すると、かゆみや皮膚炎、アレルギー反応を引き起こすこともあります。免疫力の低い子どもや高齢者は、特に注意が必要です。
ハクビシンのフンが原因の感染症については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:厚生労働省検疫所「サルモネラ感染症」/「トキソプラズマ症」
4. 本格的な対策はプロへの依頼がおすすめ

ハクビシンによる被害を根本的に解決するには、専門知識と機材を持つプロに依頼するのが最も確実です。
業者に依頼すれば、鳥獣保護管理法に基づいた安全な方法で駆除を行える上、専用の機材等を使って侵入口や巣の場所を正確に特定してもらえます。
その後、清掃や消毒、再発防止の施工までを一括で対応してくれるため、個人では難しい作業も安心して任せられます。
さらに、再発保証付きのプランを提供している業者も多く、もし再びハクビシンが侵入した場合でも、対応してもらえるケースもあるため安心です。
5. ハクビシン被害でお悩みなら協会の無料相談をご活用ください!

「毒餌が使えないなら、どうすればいいの?」という方は、ぜひ「日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」の無料相談をご活用ください。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会は、ハクビシンをはじめとした鳥類・害獣による家屋被害に対し、安全で安心な生活環境を守るための防除・管理を専門とする団体です。
経験豊富な担当者が状況を聞き、効果的な対策のアドバイスや専門業者探しをお手伝いします。全国の信頼できる登録業者を紹介してもらえるため、悪質な業者トラブルを避けられます。
「こんなことを聞いても良いのかな?」と思うような内容でも、もちろん大丈夫です。ぜひお気軽にご相談ください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
ハクビシンに毒餌を使って駆除する行為は、鳥獣保護管理法で禁止されており、無許可で行えば罰則の対象になります。
そのため、忌避剤による追い出し、エサ場の撤去、侵入口の封鎖といった合法的な方法を組み合わせて対策することが重要です。
放置すれば悪臭・騒音・健康被害が発生し、最悪の場合は建物が損傷することもあります。
ハクビシンによる被害が広がっている場合や再侵入が続く場合は、有害鳥獣捕獲の許可を持つ専門業者に依頼しましょう。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会では、無料相談を行っているため、ハクビシンの被害でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。


コメント