近年、山に餌がなくなり、ハクビシンだけではなく、イタチ、たぬき、クマなどの多くの動物が人里へと降りてきています。人間が動物の食べ物となる木を山からなくしてしまったために、やむを得ず人間の住んでいるところへ来るように。ハクビシンの実態を知らないで、ハクビシンを見かけると「かわいい」と思う方も多くいるのではないでしょうか?
ハクビシンは農作物を食べ荒らしたり、住宅に侵入して屋根裏に住み着いてしまったり、ゴミを荒らしたりと様々な被害があります。もし、ハクビシンを見つけたらどうしたらいいでしょうか?
身近に潜んでいるかもしれないハクビシンについて、ハクビシンの特徴やするべきことをご紹介します。
目次
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

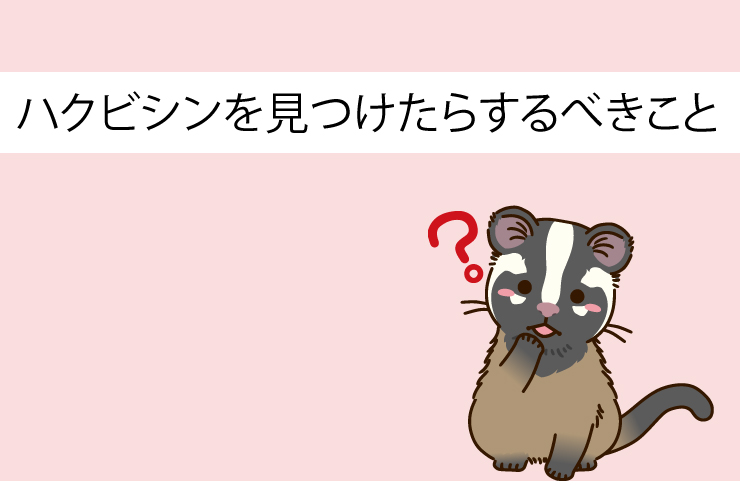 ハクビシンの生態とは?
ハクビシンの生態とは?ハクビシンの特徴
・大きさは50〜60cm くらいと小柄です。
犬で例えると【ウェルシュ・コーギー・ペンブローク】【ビーグル】
・しっぽが長いのが特徴的です。
しっぽの長さはハクビシンの体と同じくらいともいわれています。
・指は5本
・ハクビシンは冬眠しません。
・ハクビシンは一定の体温を維持することができる哺乳類です。
冬の寒い環境の中でも、体温を保つため、生きるために食料をとりに行く活動を一年中行っています。
ハクビシンの繁殖
・春夏秋冬の一年中繁殖が可能
・一度に 1~4 頭出産します
・大人になるまでの期間が早く、生後10か月で成人するといわれています。
ハクビシンの食について

・ハクビシンは雑食性です。
ゴミやドックフードなど食べてしまうこともあるハクビシンですが、特に甘いものには目がないようです。収穫時期の甘くておいしい果物や食べ頃の野菜などはハクビシンに狙われる確率が非常に高いです。
ハクビシンは雑食のため、本当になんでも食べます。先ほどもあげましたが、ゴミやペットフードなどを食べる他、昆虫や鳥類なども捕食します。
ハクビシンの食べるもの
植物質から動物質のものまで幅広く食べます。
・果実
・野菜
・小型哺乳類
・鳥類
・爬虫類
・両生類
・魚類
・甲殻類
・昆虫類等
ハクビシンの行動について

よくいる場所
・夜行性のハクビシン。昼間は樹の上、納屋や家屋、寺社仏閣の屋根裏などの中で休息していることが多いです。
・水辺を好む傾向があります。
そのため、河川や用水路、側溝などを移動経路として利用していることもチラホラ…
木登りが得意
木にひっかき傷があった際は【ハクビシン】がいるかもしれないと周りを注意深く観察してみてくださいね。
・柱に登ったり、電線を伝い歩きしたりします。
ハクビシンは身体能力が非常に高い動物です。足で物を掴むという芸もできるほどです。電線の上を歩けるのは、足で電線を掴み、尻尾でバランスをとっているからです。ハクビシンのバランス感覚がいいことがよくわかります。
季節に応じた行動

春
冬の寒さが明け、活発的にハクビシンが行動。住みかとしていた屋内(屋根裏、倉庫など)から出ていく時期もこの頃です。探索範囲が拡がってくる春は、周辺だけを探索していたハクビシンが餌を求めて広範囲に探索をスタートさせます
夏
夏は、ハクビシンにとっては最高の季節。ですが、私たち人間にとってはハクビシンの被害が最も多い季節でもあります。
なぜなら、育てていた夏野菜、果物の被害が多いからです。ハクビシンの好物となるスイカや梨などの美味しい果物。甘いトウモロコシなどが豊富にある夏はハクビシンにとっては過ごしやすい季節です。
また、夏は外での生活が快適なため、屋内にいることは少なくなります。それではどこにハクビシンがいるかというと、木登りをして涼しい木陰で生活することが増えていきます。
秋
ハクビシンは冬眠はしませんが、体温を一定に保つ必要がある恒温動物。人間と同じで冬眠せずに生きていることはできますが、寒さが強く、活発的に動けるというわけではありません。そのため、ハクビシンは冬の寒さを凌ぐために温かい場所を求めて屋内に侵入してきます。屋根裏や床下、物置など民家などでハクビシンを多く見つける機会はこの頃です。
冬の時期に屋根裏などに侵入する傾向があるハクビシン。対策をするなら冬になる前のこの時期です。本格的に寒くなる前に、ハクビシンの侵入経路をしっかりと塞いでおきましょう。
冬
雨風、雪などでハクビシンの体が冷えない絶好の環境が民家です。あたたかい空気は上に上がっていきます。そのため、天井は比較的にあたたかく、寒さを凌ぐにはもってこいの場所なんです。さらに、同様に寒さを凌ぐネズミなどがいればハクビシンにとって絶好の場所となります。住みかになっていなくても、ネズミを探し求めてハクビシンが侵入してきてしまうことがあります。
ネズミが家の中にいるかもしれないと感じたら駆除対策を行うのが最適でしょう。
ハクビシンを見つけたら通報しましょう
ハクビシンの通報は、地元の市役所や環境保護団体に連絡しましょう。
その際に
・場所
・時間
・ハクビシンの数など
詳細をお伝えするとなお、いいでしょう。
ハクビシンを見つけたらハクビシンが近くに住み着いているかも
こんな時には要注意!
・屋根裏で音がする
・天井にシミができている
・畑にある野菜や、庭にある果実が食べられている
・庭木の果実(柿やビワなど)が食べられている
・雨どいやベランダなど とある一角にまとまって何かのフンがある
・夜、庭や屋根の上に見慣れない動物がいた
・池の金魚がいなくなった
・飼っている犬、猫などが血を流している
ハクビシンが侵入していたり、近くに住み着いている可能性があります。
ハクビシンの被害が出る前に|忌避剤を使用し、追い出しましょう

*ハクビシンの嫌いな臭い
・木酢液
・ニンニクの臭い
・唐辛子の臭い
・天敵の臭い
・石油系の臭い
*ハクビシンの忌避剤 使用方法
・忌避剤はハクビシンの通り道に設置しましょう
・ハクビシンの顔の高さ【15cm】のところに吊るすと効果的です
※ペットのいる方は近くで使用しないように注意しましょう
手作りできる!忌避剤をご紹介
木酢液、ニンニク、唐辛子を混ぜるだけ
材料の比率の目安は【木酢液:ニンニク:唐辛子=10:1:1】
<材料>
・木酢液1L
・ニンニク100g
・乾燥唐辛子100g
・空のペットボトル(2L)1個
<作り方>
①唐辛子を半分に切る
②ニンニクを潰す
③2Lのペットボトルに木酢液・ニンニク・唐辛子を入れる
④1~3ヵ月ほど漬け込む
犬の毛を袋に入れて吊るす
集めた毛を約10gずつネットに包む地上1メートルほどの高さにつり下げる
犬を飼っていないという方もご安心ください。
ペットショップやペットサロンなどで分けていただくこともご検討ください。
灯油をしみ込ませた布を置く
灯油もハクビシンが嫌うにおいですが、揮発性があります。
屋外の風通しのよい環境では灯油をしみ込ませた布を置くよけの効果はあまり期待できません。
自分でできる!?ハクビシン駆除【STOP!!】
ハクビシンを捕まえて仕留める行為は法律で禁止されている行為です。
ハクビシン駆除についてネットで検索すると、様々な方法が出てきます。
それを見て「これならできそう!」と容易に考えてしまいます。ただ捕獲に関しては「鳥獣保護法」に基づき、本来は捕獲・処分・保護なども原則禁止です。また、許可なく勝手に捕まえる行為は、法律で「50万以下の罰金、又は一年以下の懲役」が罰せられることも・・・。
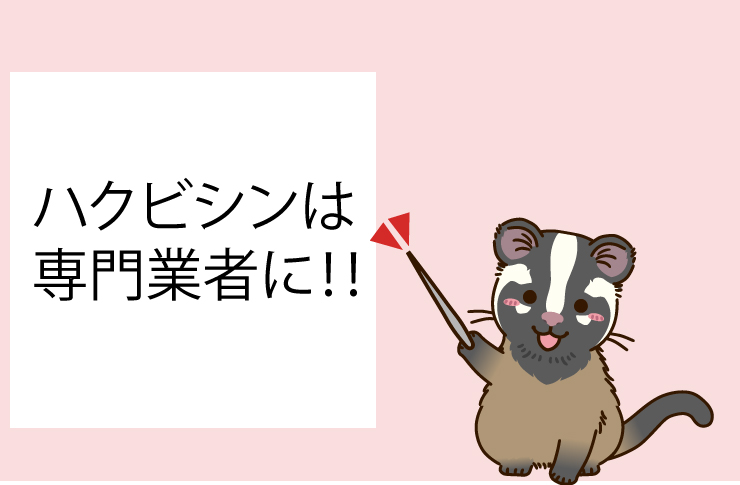
ハクビシンは専門業者に
ハクビシンの追い出しがうまくいかない・・・
ハクビシンを追い払えないときは、専門業者にお願いするといいでしょう。
☆プチ アドバイス☆
害獣駆除の業者を選ぶ際は、害獣駆除から建物の修繕まで、しっかりと対応してくれる業者を選びましょう。
害獣を追い出すことは、業者なのでやってもらって当たり前です!
害獣駆除はもちろんのこと、害獣により被害を追った箇所(建物)の修繕や、除菌・消毒まで行ってくれる業者だと安心です♪
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
まずは、ハクビシンの生態について知りましょう。
ハクビシンの特徴としては、しっぽが長いこと。ハクビシンの身体と同じくらいしっぽが長いため、【イタチかな?】【ハクビシンかな?】と迷ったときはしっぽを見ると一目瞭然でしょう。ハクビシンは冬眠をしないため、1年中見かける機会があるでしょう。ただ、恒温動物のハクビシンは、冬の間は、寒さを凌ぐために、必要最低限の狩りしかせず、温かいところで過ごしています。
また、繁殖率が高いこともハクビシンの特徴です。一度に3〜5匹ほど産みます。
ハクビシンは雑食性のため、なんでも食べます。虫や果物、野菜のほかにも家庭から出すゴミをあさって食べることもあります。もし、ハクビシンを見つけたら、忌避剤を使用し、追い払いましょう。
忌避剤を使用しても追い払うことが難しい場合は、専門業者にお願いしましょう。


コメント