皆さんはネズミの被害に遭った事はありますか?
様々なものを齧るネズミは自身にも病原菌を保有している大変危険な害獣です。
そんなネズミを駆除する時の市販薬はどういうものが良いか悩んでしまいますよね。
そこで今回はネズミの市販殺鼠剤に注目し、どういうものが効果的なのかを解説していきます。ぜひ最後まで読んでみて下さい。
目次
ネズミの特徴は?家ネズミの生態について
まず、私達の生活圏に悪影響を与えるネズミはどのような種類がいるのでしょうか?
現在の日本には10属20種類以上のネズミが存在し、その生息域は本州全域から南西諸島までと幅広いです。
そんな中で、私達の生活圏に悪影響を与えるのはたった三種類と言われています。
この三種類を総称したものが家ネズミです。家ネズミには以下の三種類があたります。
ドブネズミ
ドブネズミは体長が約22cm~26cmの大型に分類される家ネズミであり、頭の大きさに対して耳が小さいのが特徴です。
性格は非常に獰猛で攻撃的であり、人間を恐れない為駆除の際にも此方に襲いかかってくる可能性がある為注意が必要です。
普段は下水道などに生息しており、水気の多い場所を好んで住み着く傾向があります。
その為体が濡れているので粘着トラップにかかりづらいのです。
クマネズミ
クマネズミは体長が約18cm~24cmの中型に分類される家ネズミです。
性格は怖がりで警戒心が強く、知能も高い為仕掛けた罠を見破ってしまうケースもあります。
非常に繁殖力が強いネズミであり、1頭につき6匹の子供を生む上これが年間で5回〜6回繰り返される為住み着かれると駆除が大変な家ネズミといえます。
クマネズミは運動能力に優れており、高い所を好むため建物の天井やビルの上層階にも侵入してしまう為マンションに住んでいても被害に遭う可能性があります。
ハツカネズミ
ハツカネズミは体長が約6cm~10cmの小型に分類される家ネズミです。
性格はおだやかで好奇心が強く灰褐色の毛色が特徴です。
クマネズミ同様繁殖力が強く、1頭につき6匹の子供を産む上これが年間で6回から10回繰り返されます。その為、一度住み着いてしまうと駆除が難しいネズミと言われています。
本来は畑や雑木林に生息していますが冬になると寒さを避ける為人間の住居に侵入してくるのです。寒くなる10月から3月までの間に発生し、1月から2月が発生のピークと言われています。
ネズミが住み着く事によって起こりうる被害
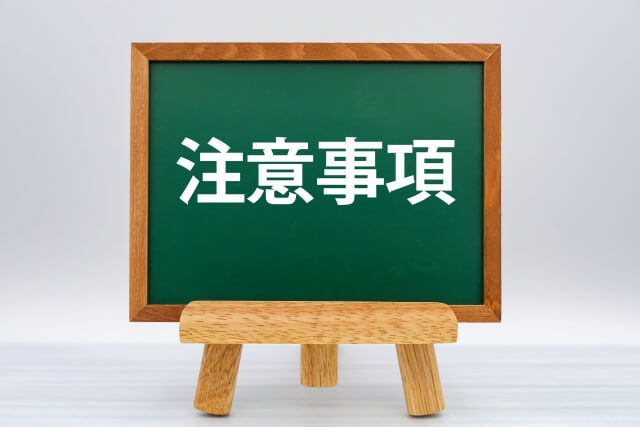
それではネズミが私達の生活圏に住み着く事でどのような被害が起こるのでしょうか?
感染症など様々ありますが、ここでは大きく4つに分けて被害の実態について解説していきます。
騒音被害
ネズミが住み着く事で引き起こされる被害の1つが騒音被害です。
ネズミは夜行性であり、活動するのは勿論私達が寝静まった深夜になります。
その為、ネズミが天井を走り回る音や柱などを齧る音に悩まされ睡眠不足に陥る人は多いのです。
睡眠不足はストレスの原因になり、日中の作業効率の低下を招く恐れもあります。
またこの被害を放置してしまうと症状が悪化し、ノイローゼを発症したケースもあるので天井裏などから足音が聞こえる場合はネズミの侵入を疑い、早急に対処を行いましょう。
健康被害
ネズミが住み着く事によって引き起こされる被害の中には健康被害も含まれます。
ネズミはフンや自分自身に様々な病原菌を保有しており、中には命の危険を伴う病原菌も確認されています。
ここでは主に つの病原菌について解説していきます。
サルモネラ菌
サルモネラ菌は食中毒を引き起こす原因であり、ネズミが保有している病原菌の一種です。
主な症状として急性の発熱や腹痛、下痢などが挙げられ、12時間から36時間の潜伏期間を経て発症します。
上記の症状は2日から7日かけて続くと言われており、殆どの場合は治療をせずとも回復します。
ですが免疫の少ない幼児や高齢者が発症した場合、脱水症を併発する可能性があり命の危険もある感染症です。
レプトスピラ菌
レプトスピラ菌はネズミの糞尿を介して感染する病原菌の一種です。
主な症状として38度から40度の高熱、頭痛、結膜の充血などが挙げられ、中でも腓腹筋(ひふくきん)の筋肉痛が特徴的です。
また重症型すると一週間程度経過後に黄疸や出血が見られ、腎障害に発展する可能性もあります。
鼠咬症
鼠咬症はネズミに噛まれる事で発症する病気の一種です。
3日から10日の潜伏期間を経た後、血液中に細菌が入ってしまう菌血症を引き起こし皮疹や発熱が発症します。
また、意識障害や肺炎などの病気を併発する可能性もある為十分な注意が必要です。
ネズミに噛まれた場合、鼠咬症だけではなく噛まれた箇所からの出血多量により死亡した事件も存在する為駆除の際はしっかり対策を行うようにして下さい。
ダニやノミによる被害
またネズミが住み着く事でダニやノミを招き入れてしまう可能性もあります。
本来はネズミなど野生動物に寄生していますが繁殖期などを経て住む場所が狭くなると人間に寄生してしまいます。
特にダニの中にはマダニなど危険な種類のダニも存在します。マダニを媒介して感染する感染症は以下の通りになります。
ツツガムシ病
ツツガムㇱ病は正確に言うとツツガムシというダニの種類に咬まれる事によって発症する感染症です。
5日から14日の潜伏期間を経た後、高熱などの症状が現れますがここでの特徴は皮膚にツツガムシの刺し口(黒色痂疲)があることです。
また数日経過する事で発疹や倦怠感、頭痛などの症状が現れ治療が遅れた場合多臓器不全を引き起こし、死の危険生がある感染症です。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
SFTSはSFTSウイルスを保有したマダニに咬まれる事によって発症する感染症の一種です。
主な症状として発熱や消化器症状などが見られ、嘔吐や下痢などの症状が現れます。
またSFTSに感染した場合、血液や体液などの接触感染も報告されています。
また重症化した場合命を落とす可能性がある危険な感染症でもあります。
ダニ媒介肺炎
ダニ媒介肺炎は病原菌を保有するダニに咬まれる事によって引き起こる可能性のある感染症の一種です。
主な特徴としては39度以上の高熱と特徴的なダニの刺し口が挙げられます。
国内での発症も毎年多く確認されており、重症化してしまうと肺炎や脳炎に発展する可能性もあります。
汚損被害
ネズミが住み着くことで起きる被害は健康被害や騒音被害だけではありません。
ネズミが走り回ったり物を齧ることによって起こる汚損被害も有名です。
ネズミはげっ歯類に分類される為、食材から柱まで様々なものを齧ることで歯が伸びすぎるのを防いでいます。その為ネズミに住み着かれてしまうと大事な家財の価値が損なわれたり、食材が無駄になってしまう可能性があります。
ネズミの侵入が疑われる場合は業者に相談するなどして、早急に対策を勧めましょう。
火災事故など
またネズミが齧ることによって大きな事故に発展したケースもあります。
ネズミが電気配線などを齧ってしまい漏電による火災が毎年数十件報告されており、ニュースになった事もあります。
他にもネズミの尿によって電気機器が破損してしまう例も少なくないので、素早い対応が必要になります。
忌避剤と駆除剤の違いは?
ところで皆さんは忌避剤と駆除剤の違いをご存知でしょうか?
忌避剤は一般的にネズミを初めとする害獣が嫌がる匂いや成分を利用し、寄せ付けなくする効果を持っており、駆除後の対策として有効です。
駆除剤はネズミなどの害獣を殺鼠する成分を持っており、ネズミが現れた場合に応急処置として有効です。
しかし個人によるネズミの完全駆除は難しいと言われており、もし完全に駆除をする場合は専門業者に依頼しましょう。
ネズミの侵入がわかる?ラットサインとは
屋根裏から足音がするけどネズミかどうかわからない、うちにはネズミが住み着いているんじゃないかと不安になった経験がある方も多いのではないでしょうか。
実はネズミは侵入している場合とある目印で見分ける事ができます。それがラットサインです。
一般的にラットサインは以下のものが挙げられます。
ネズミのフン
ネズミが侵入した場合、家の中に小さなフンが落ちている場合があります。
この時ドブネズミの場合は整った楕円形、クマネズミの場合は不揃いな楕円形、ハツカネズミの場合は両端が尖っているなどの特徴があります。
黒い擦り痕
壁の隅や天井付近に黒い擦り痕がある場合、そこがネズミの通り道になっている可能性があります。
ネズミは隅に沿って移動する習性がある為、何度も同じ場所を通るとネズミの体に付着していた脂分などで汚れてしまうのです。
齧り痕
家財や柱などにある齧り痕もラットサインの一種です。
先ほども解説した通りネズミはげっ歯類であるため、様々なものを齧ります。
食材や家具などに見慣れない齧り痕がある場合、ラットサインと考えて良いでしょう。
足跡
ネズミの足跡もラットサインの一種として挙げられます。
ネズミは尻尾を持っている為、移動の際に尻尾の痕が付着します。
小さな足跡の間に線が見られる場合、ネズミの足跡と考えていいでしょう。
こういうものがオススメ!タイプ別駆除剤
さて、いよいよネズミの駆除剤について解説していきます。現在は薬局などで様々な駆除剤が販売されていますが、どんなタイプが効果的なのかわからないという方も少なくないかと思います。
ここでは駆除剤のタイプ別にどういう場合にオススメなのかを解説していきます。
固形タイプ
固形タイプは、設置するだけで効果を発揮するものが多く直接ネズミを見たくないという方にオススメです。
効果の期間が長いものも多く遅効性のものもある為、警戒心が強いネズミが相手でも効果は大きいです。
また固定式のものもあるのでネズミが持ち去ってしまう可能性が低いのも嬉しいポイントです。
投げ込みタイプ
ネズミを駆除する場合、天井などの隙間などに投げ込むだけで効果を発揮する投げ込みタイプもオススメです。
通常齧るタイプの駆除剤は何度か齧らないと効果を発揮しないものも多いですが投げ込みタイプの中にはネズミが一度食べただけで効果を発揮するものもあります。
その為、警戒心が強いネズミにも警戒されることなく使用できる場合が多いのです。
天井裏に住み着いているネズミに困っている方は一度使用してみてもいいでしょう。
袋タイプ
ネズミの駆除剤の中には袋のまま使う事ができる袋タイプも存在します。
仕掛けてから3日から5日ほどで効果を発揮するものもあり、設置も簡単なものが多いため、ネズミが気になる場合に気軽に使う事ができます。
個人では難しい場合、専門業者に依頼しよう
ここまでの解説でも何度かお話したように個人でのネズミの完全駆除は難しいと言われています。一度駆除できたとしても再侵入されてしまったりとなかなか厄介なのです。
そんな時はネズミの専門業者に依頼することを視野に入れてみましょう。
専門業者の選び方が分からない場合、以下を基準にする事でしっかりとした会社を選ぶ事ができます。
口コミなどで接客態度の評価が高い場所を選ぶ
ホームページを確認して、成功実績が豊富な会社を選ぶ
現地調査を行ってくれる会社を選び、細かい作業工程や現状を質問する
見積もりを複数社から貰い、自分に合った保証期間や予算に近い会社を選ぶ
ネズミを駆除した後の対策とは

ネズミを駆除した後も気を抜いてはいけません。
ネズミは再侵入をしてくる可能性もある為、完全に駆除できたタイミングで再侵入予防の為の対策を行いましょう。
侵入経路の封鎖
対策の1つ目は侵入経路の封鎖です。ネズミは以下の場所から侵入してくる場合があります。
配管や電線など壁に貫通している場所
押入れ
壁の隙間や小さな穴
流しの下
排水溝
配管工などが原因の場合、ホームセンターなどに売られている目の細かい金網を設置固定する事で侵入を防ぐ事ができます。
壁の穴などが原因の場合は此方もホームセンターや通販などで購入できる隙間パテやモルタルなどで埋めてしまう事でネズミが侵入できなくなります。
流しの下や排水溝、換気扇などが原因の場合は専用のフィルターなどを利用する事でネズミの侵入を防ぐ事ができます。
忌避剤を撒く
侵入経路を塞いだ後は忌避剤を利用してネズミを近寄れなくしましょう。
駆除剤同様、今は忌避剤も様々なものが売られています。殺虫剤のようにワンプッシュするだけで効果を発揮するスプレータイプから、設置するだけで効果を発揮する固形タイプなど様々なタイプのものがあります。
また効果の期間もそれぞれ違ってくるので購入の際にはよく確認する事をオススメします。自分の環境に合わせたものを使い対策を行いましょう。
まとめ

さてネズミの駆除剤による対策と解説、いかがでしたでしょうか。
害獣駆除ガイドではネズミを始め、様々な害獣の対策や原因を解説しています。
是非一度他の記事も読んでみてくださいね。


コメント