「夕方になると、シャッターのあたりからカサカサ物音が…もしかしてコウモリ?」
シャッターはコウモリが巣を作りやすい場所の一つです。
自宅に住み着いたコウモリを放置すると、騒音や健康被害に悩まされる恐れがあります。「コウモリがいるかも」と感じたら、早急な対策を考えましょう。
この記事では、コウモリがシャッターに潜んでいるサインや自分でできる対処法などについて徹底的に解説します。
一日も早く安心できる日常を取り戻すために、ぜひ最後までご一読ください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

コウモリがシャッターに潜んでいる3つのサインとは?

コウモリがシャッターに住んでいる場合、周辺に以下のようなサインを残します。
- シャッター周辺にフンが落ちている
- 夕方や明け方に物音がする
- 壁やシャッターに黒いしみがついている/異臭がする
まずは該当するサインがないか、チェックしてみましょう。
シャッター周辺にフンが落ちている
コウモリが住み着いている場合、巣の周辺にフンが落ちていることがあります。
コウモリのフンは5~10㎜程度で黒っぽく、細長い形をしています。ネズミと見間違われがちですが、油分が多く光沢のあるネズミのフンと比べるとパサパサしており、主食である昆虫の一部が混入していることもあるのが特徴です。
夕方や明け方に物音がする
夕方や明け方に、シャッター付近から「カサカサ」「バタバタ」という羽音や「キィキィ」という甲高い鳴き声が聞こえるのも、サインの一つです。
コウモリは夜行性のため、日没後の夕方から夜にかけて活動が活発になります。シャッターの内部から聞き覚えのない物音が聞こえる場合は、コウモリが住み着いていることを疑いましょう。
シャッターや壁にシミがついている/異臭がする
シャッターやその周辺の壁に黒いシミがついていたり、異臭がする場合も要注意です。
コウモリには、同じ場所から何度も出入りを繰り返す習性があります。そのため出入り口付近の壁やシャッターには、尿や体の皮脂汚れが付着し、黒っぽい筋のようなシミができたり異臭がしたりします。
シャッターのコウモリ対策で守るべき注意点

シャッターのコウモリ対策を自分で進める場合、次の3点を厳守しましょう。
- コウモリを捕まえたり傷つけたりしない
- マスクや手袋などを装着して行う
- 高所の作業は安全に十分注意する
さらなるトラブルを引き起こさないためにも、まずは以下で詳細を確認しましょう。
コウモリを捕まえたり傷つけたりしない
自治体の許可なくコウモリを捕まえたり傷つけたりしてはいけません。駆除作業の目的は、あくまでコウモリを「追い出すこと」です。
実は日本に生息するほとんどのコウモリは「鳥獣保護管理法」という法律で守られています。誤って傷つけたり殺してしまった場合は違反とみなされ、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることもあるので注意しましょう。
参考:e-GOV法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
マスクや手袋などを装着して行う
駆除作業は、必ずマスクや手袋、ゴーグルなどを装着し、汚れてもよい服装で行いましょう。
コウモリのフンは乾燥すると粉末状になりやすく、吸い込むとアレルギーや感染症を引き起こす恐れがあります。健康被害を防ぐためにも、徹底した予防対策が必要です。
高所の作業は安全を最優先する
シャッターのコウモリ対策は高所での作業が多いため、安全には十分注意しましょう。
シャッターに住み着いたコウモリの駆除は、脚立やはしごを使う場所での作業が多く、転落など思わぬ事故につながる危険性が伴います。作業中は家族に脚立を支えてもらうなど安全確保を心がけましょう。
少しでも「怖い」と感じたら、無理をせず専門業者への依頼をおすすめします。
シャッターのコウモリ対策3ステップ
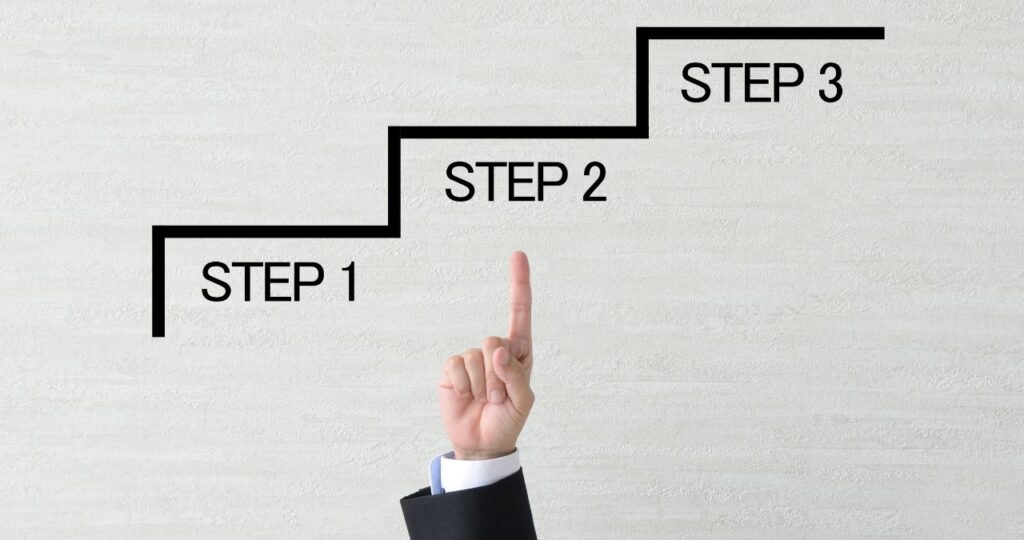
シャッターのコウモリ対策は、以下の手順で進めます。
- 忌避剤などでコウモリを追い出す
- 侵入口をふさぐ
- シャッター内や周辺を清掃・消毒する
正しい手順で駆除し、被害の拡大やコウモリの再侵入を防ぎましょう。
忌避剤などでコウモリを追い出す
夕方にコウモリが巣から飛び立ったら、忌避剤などで巣に寄せ付けないようにします。
忌避剤とはコウモリが苦手なハッカの成分などを利用したもので、ホームセンターなどでも簡単に手に入ります。
ジェルタイプや固形タイプなどさまざまな形態がありますが、おすすめはロングノズル付きのスプレータイプです。長いノズルで成分をシャッターの奥まで届け充満させられるので、巣に残っているコウモリも残さず追い出すことができます。
なおコウモリの駆除には、避けるべき時間帯と時期があります。日中や冬眠時期(11月~3月頃)、繁殖期(7月~8月頃)は、コウモリを追い出しにくいだけでなく、被害の再発・拡大を招く恐れもあるので避けましょう。
駆除に適した時間帯や時期の詳細に関しては、以下の記事でもチェックできます。
侵入口をふさぐ
コウモリを完全に追い出したら、侵入口をふさぎましょう。
コウモリには、元いた場所に戻ってくる習性があります。一度追い出しに成功しても、放置すれば再び住み着いてしまいかねません。
コウモリの体は1.5㎝ほどで、わずかな隙間でもすり抜けてしまいます。特に経年劣化がみられるシャッターは、コーキングの剥がれやひび割れが生じている可能性が高いため注意が必要です。
目の細かい金網やコーキング剤などを使い、シャッターボックスの両脇や壁との接合部などの隙間を徹底的に封鎖しましょう。
ただしシャッターには開閉に必要な隙間が作られている場合もあります。故障の原因にならないよう、取扱説明書などで事前に確認しておきましょう。
シャッター内部や周辺を清掃・消毒する
コウモリの追い出しに成功したら、シャッター内部や周辺を清掃・消毒します。
フンを放置すると健康被害のリスクが残るだけでなく、臭いが他のコウモリを呼び寄せる恐れもあります。必ずマスクや手袋を装着して、ほこりが舞い上がらないように掃きだしましょう。
またフンがあった場所やシミになっている箇所には、アルコールスプレーや塩素系漂白剤を薄めた液を吹きかけ、布で拭き取って消毒すると安心です。
再発防止に知っておきたい「コウモリに好かれるシャッターの共通点」とは?

コウモリが巣を作りやすい環境には、以下の共通点があります。
- 静かで安全(閉めっぱなしのシャッターなど)
- 狭くて外部から見えにくい(軒下があるシャッターなど)
- エサとなる虫が多い(照明周辺のシャッターなど)
自宅のシャッターに上記の特徴がある場合は、特に再発防止策に力を入れましょう。
静かで安全(閉めっぱなしのシャッターなど)
コウモリは警戒心が強いため、巣作りには人気のない静かで安全な場所を好みます。
特に普段からシャッターを閉めっぱなしにしていると、コウモリに「安全な場所」と認識される恐れがあります。駆除が完了した後も定期的にシャッターを開閉し、コウモリが寄り付かないようにしましょう。
ただしシャッターを開けっ放しにしていると、コウモリが屋内へ侵入するケースもあるため注意が必要です。室内でコウモリを見つけた際の対処法は、以下の記事を参考にしてください。
狭くて外部から見えにくい(軒下があるシャッターなど)
狭くて外部から見つかりにくいことも、コウモリが巣を作りやすい場所の条件に挙げられます。
カラスやイタチなどコウモリの天敵は体が大きいため、狭い隙間には侵入できません。中でも軒下があるシャッターは天敵からの目隠しになる上、雨風もしのげるため、絶好の隠れ家になってしまいます。
自宅シャッターが条件に該当する場合は、効果が長い置き型の忌避剤やコウモリ除けのLEDライトを設置するなど、再侵入防止対策を特に徹底しましょう。
エサとなる虫が多い(近くに照明があるシャッターなど)
コウモリは、エサになる昆虫が豊富な場所に巣を作る傾向があります。
周辺に玄関灯などの照明がついているシャッターは、蚊や蛾などの虫が集まりやすく、コウモリにとっては魅力的な環境です。
照明の電球を防虫効果のあるものに変えたり、人が通るときだけ光る「人感センサー付きライト」を設置したりして、虫が寄り付かないように工夫しましょう。
コウモリ被害を防ぐための防虫対策については、以下の記事もチェックしてください。
コウモリ被害でお悩みなら協会の無料相談をご活用ください

「シャッターのコウモリ対策がしたいが、自分一人では不安」「対策が十分か自信がない」という方は、ぜひ「日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」の無料相談をご活用ください。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会は、コウモリをはじめとした鳥類・害獣による家屋被害に対し、安全で安心な生活環境を守るための防除・管理を専門とする団体です。
経験豊富な担当者が状況を聞き、効果的な対策のアドバイスや専門業者探しをお手伝いします。「こんな質問をしてもいいのかな?」と不安に思うような内容でも、安心してご相談いただけます。ぜひお気軽にご利用ください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
今回はコウモリがシャッターに住み着いたサインと、自分でできる対策方法について詳しく解説しました。
効果的にコウモリ対策を進めるには、正しい手順と技術が必要です。やみくもに行うと法律違反や被害拡大のリスクもあるため、少しでも不安がある場合は専門家に相談しましょう。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会では、無料相談を行っているため、コウモリの被害でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。


コメント