アライグマを駆除するのは、かわいそうに思えるかもしれません。
しかし、被害を放置するのは危険です。
アライグマのフンには、アライグマ回虫という寄生虫が潜んでいることがあります。
この寄生虫が人間の体内に入ると、幼虫移行症を引き起こして中枢神経に深刻なダメージを残します。最悪の場合、死に至ることもある非常に危険な寄生虫です。
また、アライグマの中には狂犬病を発症しているものもいます。
アライグマは身体能力に優れ、知能も高いです。力も強くすぐに数を増やします。
きちんと対策を打たないと、被害状況は悪化していきます。
その負担を負うのは自分です。
この記事では、アライグマに効果的な対策方法をわかりやすく紹介しています。
アライグマ対策に失敗すると、痛い目を見ることになるかもしれません。
早めにしっかりとアライグマ対策を講じて、平穏な生活に戻りましょう!
アライグマ対策の種類
アライグマを退治する方法には、大きく分けて3種類あります。
- ⑴心理的な効果を使ってアライグマを追い出す方法
- ⑵アライグマの侵入を物理的に防ぐ方法
- ⑶アライグマを物理的に捕獲して駆除する方法
⑴心理的な効果を狙う方法は誰でも簡単にできる上、一定の効果も見込めます。ただし、アライグマが慣れてしまったり、アライグマにも個体差があり、嫌悪感を抱かないものもいるため、被害を確実に減らすことは難しいです。
⑵アライグマの侵入を阻むことも効果は高いですが、設置に費用や時間がかかります。また、アライグマの侵入ルートを見つけるのは素人では難しく、確実に被害を減らせるわけではありません。
⑶捕獲して駆除するには専門的な知識がないと難しいですし、捕獲の際に各都道府県や市町村、保健所などに申請する必要があります。
それぞれの方法について以下に詳しくまとめたので、対策の参考にしてみてください。
心理的な効果によって退治する方法

アライグマが不快に感じる音や匂いを使えば、アライグマの被害を減らせるかもしれません。
アライグマは、以下のものを嫌がります。
- ⑴唐辛子やワサビなどの激辛臭
- ⑵物が焼け焦げたような匂い
- ⑶オオカミの尿の匂い
- ⑷超音波
- ⑸オオカミの鳴き声
- ⑹電気や痛み
⑴唐辛子やワサビなどの激辛臭
アライグマがなぜ激辛臭を嫌うのか理由は定かではありませんが、唐辛子は動物に食べられないために、辛味成分を持つように進化したと言われています。
激辛臭は市販のアライグマ用忌避剤にも含まれており、アライグマの駆除グッズとして人気があります。忌避剤はホームセンターなどで購入できますが、家庭にあるもので自作することも可能なので、簡単に試すことができます。
⑵物が焼け焦げたような匂い
元々野山で生活していたアライグマは、山火事を連想させる匂いを嫌がります。ホームセンターなどで売っている木酢液(もくさくえき)は、そうした匂いがするので駆除グッズとしてよく使われます。木酢液とは、木炭を燃やしたときに発生する蒸気を冷やして液体にしたものです。自分で木炭を焼いて作ることも可能なので、手軽に試せる方法です。
⑶オオカミの尿の匂い
オオカミはアライグマの天敵のため、オオカミの尿を嗅ぐと身の危険を感じて逃げていきます。その習性を利用したウルフピーも、アライグマ対策の効果に期待が持てるでしょう。
⑷超音波
アライグマが超音波を嫌がる理由ははっきりとはしませんが、害獣対策として超音波はよく使われます。広範囲にわたって音を出すことができますが、人によっては超音波が聞こえるため、騒音被害を起こしてしまうかもしれません。人気のない場所に向いている方法です。
⑸オオカミの鳴き声
アライグマの天敵であるオオカミの鳴き声を流すことで、アライグマを逃がすというものです。この方法もアライグマの防衛本能をくすぐるので、一定の効果が見込めます。
⑹電気や痛み
アライグマに限らず野生動物は、未知のもの対して本能的に危険かどうか確認する習性があります。そこで、電気ショックや痛みを与えて、危険を感じた動物を遠ざける対策方法があるのです。
- ・電気柵
- ・有刺鉄線
- ・有刺鉄板
電気柵
アライグマが電気柵に触れて感電することで、「痛みを感じるから近寄らない」と学習し、電気柵の内側に入る気を削いでくれます。
有刺鉄線・有刺鉄板
有刺鉄線や有刺鉄板は、鋭いトゲを触ることで危険物と認識し、近寄らなくなります。
心理的な効果は弱い?!
アライグマの駆除グッズとして人気の高い忌避剤や木酢液ですが、効果が必ずしも持続するというわけではありません。
アライグマは適応能力が高く、最初は不快に感じても時間が経てば慣れてしまいます。
また、知能の高い生き物でもあるので、危険なオオカミの匂いがしても安全が確認できれば気にしなくなるかもしれません。
もちろんアライグマにも個体差はあるので、そもそも匂いや音に敏感でないアライグマであれば効果は薄いです。
そのため、アライグマ対策としての効果は限定的です。
アライグマの侵入を防ぐ方法

家屋などアライグマの侵入経路が限定されているケースでは、侵入口を封鎖する策が有効です。
アライグマの主な侵入口はこの2つです。
- ・屋根裏付近
- ・床下
アライグマは身体能力に優れていて、壁登りやジャンプが得意です。手先も器用で力も強いので、屋根材などを剥がして中に入り込むこともできます。
また、ちょっとしたスキマでもアライグマは通り抜けることができるため、怪しいところはできるだけ塞いだ方がよいです。
アライグマは力が強く、障害物を置くだけでは簡単に除けられてしまいます。金属製の頑丈なプレートなどで侵入口をしっかり塞ぐと効果的です。
侵入口を見つけるのが難しいときは
ジャンプしたり壁登りしたりと縦横無尽に動けるアライグマは、ちょっとしたところから侵入することができます。
そのため、屋根など高い所のスキマなども塞がないとアライグマの被害を完全になくすことは難しいです。
慣れていない高所での作業でけがをする可能性や、作業中にアライグマに遭遇して攻撃される可能性もあり、素人では対応しきれない場面が多々あります。
そのようなリスクを回避したい方は、害獣駆除業者に相談したり駆除の依頼をしたりするとよいです。
物理的に捕獲して駆除する方法
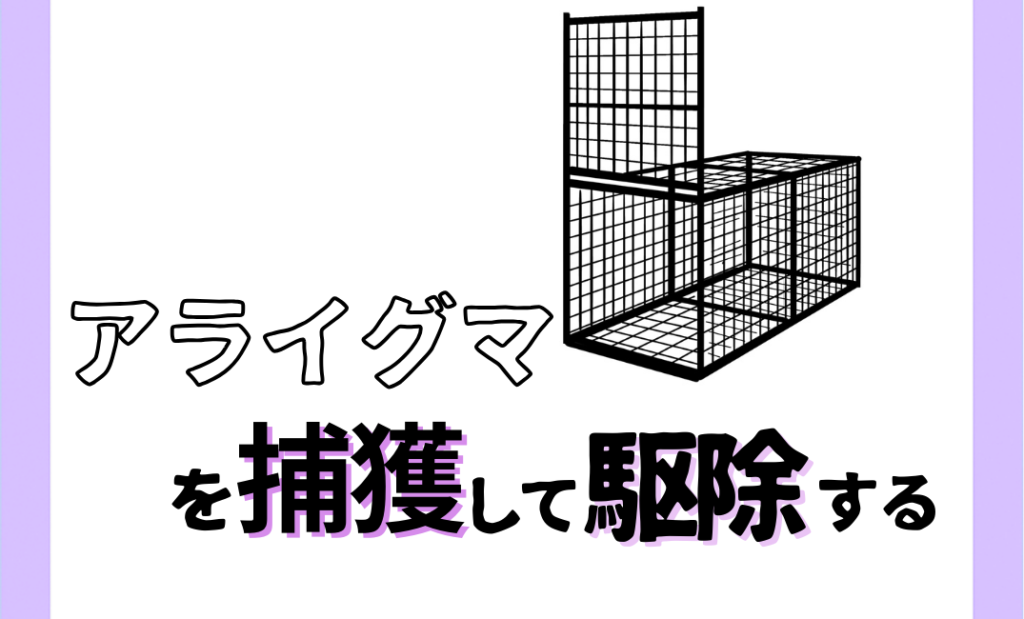
最も確実な対策は、アライグマを捕獲して駆除する方法です。
被害の犯人を捕まえて、駆除後にアライグマの予防策を講じておけば、さらにアライグマの被害に遭うリスクを格段に減らすことができます。
しかし、アライグマの駆除は条件を満たさないと法律違反になってしまいます。
その条件は以下のとおりです。
- ・狩猟免許を持っている
- ・事前に駆除の申請を出す
北アメリカ原産のアライグマは、2005年に特定外来生物に指定されました。
特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・野外に放つことが原則禁じられています。
そのため、狩猟免許という特別な資格がないと法律違反になってしまうのです。
また、特定外来生物は、防除という観点から市役所に駆除の通知を行う必要があります。
捕獲機についても、他の駆除グッズに比べると高額になるので、一般の方がアライグマの被害を受けているからと言ってすぐにアライグマを駆除することは難しいのが現状です。
プロに駆除を依頼する流れ
害獣駆除業者は、鳥獣保護法と外来生物法を遵守した害獣駆除を行うことができます。
経験も豊富なので被害状況に合わせた対応もできますし、個人でやるよりも確実に被害は減らせるでしょう。
詳しくは業者ごとに異なるのですが、ここでは簡単にプロに依頼した場合をイメージできるように一例を紹介します。
害獣駆除業者へ申し込んでから駆除までの流れは以下のとおりです。
- ⑴相談
- ⑵現地調査日の決定
- ⑶現地調査
- ⑷被害状況と駆除計画の報告
- ⑸見積書の提出
- ⑹駆除作業日の決定
- ⑺駆除の実施
スケジュールや時期、被害状況にもよりますが、駆除の作業時間は半日で終わる場合もあります。
費用の相場はおよそ1.5~30万円です。
中には無料で相談を受け付けているところもあるので、アドバイスをもらうために連絡するのもよいかもしれません。
おまけ:アライグマ予防策
アライグマは繁殖力が強く数が増加しています。
近年の被害件数も増加傾向のため、きちんと予防策を打たないと、被害が再発する恐れがあります。
予防策は以下のとおりです。
- ・屋外にペットのエサや食べ物を置かない
- ・ごみやペットの食べ残しを外に放置しない
- ・屋根裏や物置などのスキマを塞ぐ
アライグマは雑食です。加工食品から生ごみまで食べるため、屋外にアライグマのエサとなるものを置いてはいけません。
また、アライグマが人の周囲に住みつかないように家屋のスキマを塞ぎ、巣を作らせないことも大切です。
アライグマを誘因する条件をしっかりと排除すれば、再発するリスクを減らせるのでしっかり行いましょう!
まとめ
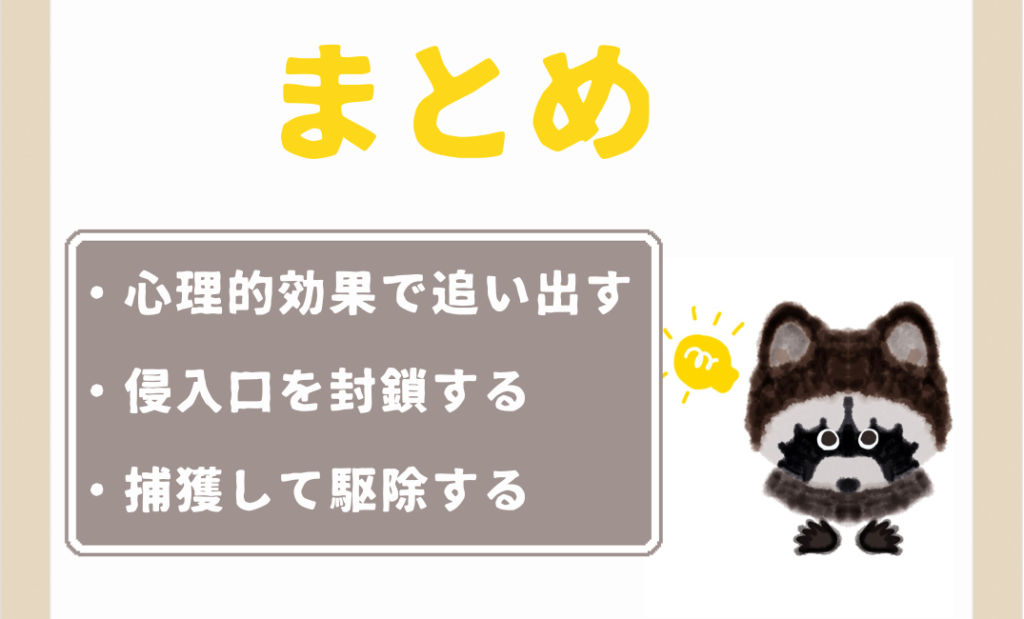
被害状況に合ったアライグマの被害対策は見つかりましたか?
アライグマは、心理的効果で簡単に追い出すこともできますし、侵入経路を絶てばより効果が見込めるでしょう。
狩猟免許を持っているならより確実に駆除することもできます。
しかし、個人で作業するには時間がかかります。不慣れな作業では失敗する恐れもあり、アライグマと遭遇するとケガするリスクもあります。
そこで、アライグマの駆除に慣れているプロフェッショナルに依頼してみるのはどうでしょうか?
害獣駆除業者は、アライグマの被害現場に日々駆けつけ、駆除を成功させています。迅速なプロに一任すれば、手間をかけずにアライグマの被害を止められるでしょう。
不明点があっても、経験豊富な業者なら的確に答えることができますし、予防策についてもフォローしてくれるところもあります。
一日でも早くアライグマの被害をなくし、平穏な生活に戻りましょう!


コメント