みなさんは、このような悩みを持っていませんか?
- アライグマが庭に毎晩やってきて、ゴミを撒き散らす
- 畑にアライグマが入り込んで、大切に育ててきた野菜が食べつくされてしまった
- 公園に頻繁にアライグマが近づいてきて、子どもたちに危険が及ばないか心配
- 毎晩天井から物音とアライグマの鳴き声がして眠れない
- 家の近くに巣を作ったアライグマの排泄物の臭いに耐えられない
かわいいイメージがある一方で、環境省によって特定外来生物に指定されているアライグマ。
アライグマをすぐにでも退治して平穏な生活に戻りたいですが、アライグマは知能が高く手先も器用なため一筋縄ではいきません。
そこで、この記事ではアライグマの生態を踏まえて、アライグマの撃退方法を紹介しています。追い出し用のグッズごとに作業手順も解説しているので、できそうなアライグマ対策をすぐに見つけられると思います。
自分でできそうな対策を見つけて、一刻も早くアライグマを追い出しましょう!
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

アライグマの駆除方法

アライグマを退治する方法は大きく分けて2つあります。
1つは追い出しと呼ばれる手法で、アライグマ用の駆除グッズを使って追い出すものです。誰でも手軽に実践できるメリットがありますが、効果が出なかったり被害が再発したりする可能性があります。
もう1つが駆除です。捕獲機を使用してアライグマを捕獲し、処分する方法です。アライグマがかわいそうな気もしますが、確実にアライグマを捕えてしまえば再度被害に遭うリスクを減らすことができます。
ただ、アライグマは鳥獣保護法と特定外来法の対象になっているため、駆除するには狩猟免許が必要です。
そのためアライグマの被害を減らす方法として最も簡単なのは、ホームセンターでアライグマ対策グッズを買って追い出すことです。
アライグマを追い出す方法
アライグマ対策グッズには以下のようなものが売られています。
- ・アライグマ忌避剤(きひざい)
- ・くん煙剤
- ・木酢液(もくさくえき)
- ・超音波発生装置
- ・侵入口の封鎖
- ・電気柵
- ・有刺鉄板
それぞれの詳しい使い方と注意点を以下にまとめました。
アライグマ忌避剤
アライグマは嗅覚が鋭く、臭いに敏感です。なのでハーブやトウガラシなどのアライグマが嫌う刺激臭を撒けば、アライグマを追い出すことが簡単にできます。
アライグマ忌避剤には、スプレータイプや液体タイプ、ゲルタイプなどがあります。また、アライグマを追い出したい場所に散布して使用するものや、置き型タイプのものもあります。被害状況や場所、使用者の希望を考慮して商品を選びましょう。
忌避剤が用意できたら、作業に取り掛かりましょう。
作業手順1:道具の準備
アライグマ忌避剤を使用する前に、以下のものを用意してください。
- ・防護用手袋
- ・防護用メガネ
- ・防護用マスク
- ・忌避剤(一般的にアライグマに対して効果的なものは、アンモニアや辛い香りのものがあります)
- ・スプレーボトルまたは噴霧器
- ・廃棄物処理用のビニール袋
忌避剤には化学物質が多く含まれているものや、刺激臭が強いものがあります。
臭いと色が付着したり、使用した後に気分を害したりする可能性もあるので防護用品の準備は怠らないようにしましょう。
作業手順2:安全の確保
必要な道具を用意できたら、散布前に周囲の安全確保をしましょう。
散布予定の場所にアライグマがいる場合、アライグマが警戒して襲ってくる可能性があります。アライグマがいるときは静かにその場を離れ、駆除業者に相談するか数時間待ってから様子を見ましょう。
また、散布予定の周辺を他の人やペットが通る可能性はないか確認し、他の人の迷惑にならないよう工夫することも大切です。
作業手順3:忌避剤を使用する
安全の確保ができたら、防護具を身に付けて忌避剤の準備をしましょう。忌避剤によって使用方法が異なるので、お手持ちの忌避剤の使用方法をよく読んでから使用してください。
効果的な散布場所は、アライグマの出入り口やよくいる場所がおすすめです。
被害が広範囲にわたる場合には、窓やドア、通気口などのアライグマの侵入経路に重点的に散布しましょう。
忌避剤は、通気性の良い場所で使用するようにしましょう。屋内で使用すると、忌避剤の刺激臭により気分を害する可能性があります。
アライグマの巣穴に撒く場合には、アライグマが巣穴から逃げ出してくることがあるため、注意が必要です。
作業手順4:使用した忌避剤の処理
忌避剤を撒き終わったら、空の容器や防護用具を廃棄物処理用の袋に入れ、適切に処理しましょう。処理の方法については、忌避剤の容器に記載されているので、よく読んで処理を行うようにしてください。
忌避剤の効果が出にくいとき
使用する時期や状況によっては、忌避剤が上手く効かないことがあります。
- ・エサとなるものが近くにある
- ・子育て中である
アライグマは雑食なため、生ごみやペット用のエサを食べにくることがあります。散布場所がアライグマにとって貴重な餌場となっている場合にはアライグマを追い出すことは難しいです。生ごみはフタ付きのゴミ箱に入れたり、エサとなるようなものを屋外に置かないようにすることが大切です。
また、春先から初夏まではアライグマの子育てシーズンです。子育て中は安全のため、その場から離れようとしません。
成功率を上げるには

アライグマによる被害はできるだけ早く食い止めないと、どんどん悪化してしまいます。
忌避剤を使用した場合の成功率を上げるには、以下の点を意識しましょう。
- ・通り道や巣穴、餌場などアライグマの生活圏内に散布する
- ・アライグマが匂い慣れしないように複数の忌避剤を交互に使用する
- ・再発防止のために定期的に散布する
- ・相乗効果を狙って他の方法と組み合わせる
もしこれらの点を意識して撒いてもアライグマの被害が収まらなかった場合には、害獣駆除業者に相談してみましょう。
くん煙剤

くん煙剤とは、煙によって害虫の嫌がる有効成分を空間内に散布するものです。本来は害虫に使用するものなのですが、アライグマは煙を嫌がるため、アライグマにも効果があると言われています。
くん煙剤は簡単に使用できることも、アライグマ除けとして挙げられる理由です。
多くのくん煙剤は、セットしてから1分で煙が出てきて短時間で効果が実感できます。また、ドラッグストアなどでよく売っているため手軽に買うことができます。
また、アライグマだけではなく害虫駆除にも役立つため、アライグマが持ち込んだダニやノミなどの害虫を退治することができます。
ただし、アライグマが部屋の中にいるときはくん煙剤を使用することは避けましょう。
アライグマは好戦的な性格ではありませんが、狂犬病に罹患していたり、出産シーズンなどは警戒心が高まっていたりすることがあります。
アライグマが常に部屋の中にいて、自分で追い出すことが難しい場合には、害獣駆除業者に相談しましょう。
反対に、夜間などアライグマが外出しているときに火災報知器などにカバーを付けるといった事前作業を行っておけば、アライグマがいるときでもスムーズにくん煙剤を使うことができます。
作業手順1:くん煙剤の購入

くん煙剤の中には医薬品扱いとなっているものがあります。
医薬品はドラッグストアでしか購入できません。ホームセンターで購入できるものもありますが、使いたいくん煙剤が医薬品かどうか確認してからお店に向かいましょう。もちろんネット通販でも購入することができるので、ご自身の買いたい方法でくん煙剤を入手してください。
作業手順2:アライグマの子どもがいないか確認
アライグマの子どもがいる場合、くん煙剤を使用することはできません。
アライグマの子どもは自力で逃げ出すことができず、親に置いて行かれるか、親が煙のない場所に避難させようとして隙間などに落ちてしまいます。隙間に落ちた子どもはまだ自力で壁を登ることができないため、死んでしまいます。親に置いて行かれた場合でも、衰弱死することがあります。
子どもが死んでしまった場合、死体の処理をしないと腐敗臭がしたり、虫が湧いたりして二次被害が発生してしまいます。また、アライグマの子どもでも、寄生虫やウイルスなどを持っている可能性があり、一般の人が触るにはリスクがあります。
なお、子どもが生きているときでも寄生虫や感染症のリスクはあるため、出来る限り触らないようにしましょう。
アライグマの子育てシーズンは基本的に4~6月です。
もしこの時期に駆除するなら、他の方法をおすすめします。
作業手順3:使用する部屋を閉め切る
くん煙剤の煙が部屋の外に漏れてしまうと、煙を充分に部屋中に広げることができません。そうなると効果も半減してしまうので、必ず部屋を密閉させましょう。
作業手順4:アライグマの脱出口を作る
部屋を密閉し切ったら、アライグマの脱出口を確保しましょう。くん煙剤に含まれている成分は、アライグマではなく虫に効果があるものです。アライグマに対しては、煙そのものでアライグマを外に追い出すので、脱出口は必ず作りましょう。ただし、脱出口が大きいと煙を部屋全体に行き渡らせることができないため、あまり大きすぎても意味がありません。脱出口としては、直径30㎝程度の穴があれば充分です。
作業手順5:火災報知器や家電をカバーする
一部例外はありますが、くん煙剤は煙を出すので火災報知器が勘違いして作動することがあります。火災報知器が作動すると、大きな警報音がなって近隣住民の方が驚いてしまいます。火災が起きたと勘違いして消防署に連絡を入れられてしまうと大事に発展してしまうので、火災報知器が鳴らないようにスイッチを切っておくか、カバーを付けるとよいでしょう。
なお、熱式の火災報知器やノンスモーク霧タイプのくん煙剤は、火災報知器が誤作動することはありません。
ただし、家電製品にはカバーを付けましょう。煙によって家電製品が壊れる可能性があるからです。特にテレビやパソコン、オーディオ機器など、機械の内部に煙が入りそうなものにはカバーを付けましょう。
不安な方は、故障を防ぐという意味で火災報知器にもカバーを付けるとよいです。
部屋の中にアライグマがいるときは、アライグマに襲われる可能性があるため作業を中断しましょう。アライグマは好戦的な性格ではありませんが、狂犬病に罹患していたり、出産シーズンなどは殺気だっていることがあります。
常にアライグマがいるときは、害獣駆除業者などに連絡して相談するとよいです。
作業手順6:子どもやペットを外に出す
基本的に、くん煙剤の成分は哺乳動物には安全な成分を使っているので、用法・用量を守っているなら乳児や幼児がいても使うことができます。
ただ、くん煙剤の煙を直接吸い込むと、成人男性でも呼吸困難や頭痛など健康を害するケースが報告されています。使用中は部屋の中に誰もいないようにして、使用後もマスクやタオルなどで口元を覆った状態で入室し、充分に換気を行いましょう。
作業手順7:くん煙剤を使用する
詳しい使い方は商品によって異なるので、取扱説明書をよく読んでから使用するようにしましょう。
くん煙剤をセットしたら速やかい部屋から退出し、使用中は誰も部屋の中に入らないようにします。
作業手順8:換気する
説明書のとおりの時間が経過したら、直接煙を吸わないようマスクやタオルなどで口元を覆ってから部屋に入りましょう。
その際に部屋の中にアライグマが残っていないか確認します。アライグマがいた場合、煙によって警戒心が高まっている可能性があります。そのため、アライグマに攻撃されないように静かに部屋から退出し、害獣駆除業者などに相談しましょう。また、逃げ遅れた子どもがいた場合も、害獣駆除業者に連絡をして相談するとよいです。
くん煙剤の効果がなかったときは
くん煙剤を使用してもアライグマが住みついたままのときは、以下の原因が考えられます。
- ・部屋を充分に密閉できていなかった
- ・アライグマの出口がなかった
- ・アライグマが煙に慣れてしまった
部屋が密閉できていないと、そこから煙が外へ逃げてしまい、アライグマを追い出すことが難しくなります。
出口がない場合も、結局部屋の外に追い出すことはできませんから、被害を減らすことは難しいです。
くん煙剤の成分は哺乳動物を殺傷するほどの力はありません。アライグマは哺乳動物なので、煙を直接吸い込んで気分を害したり多少の健康被害が出たりすることもありますが、アライグマは適応能力が高いため、何度も吸い込むと煙に慣れてしまう可能性があります。
そのときはくん煙剤の使用をやめて、他の方法を検討しましょう。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

成功率を上げるには

くん煙剤を使ってアライグマを追い出すときには、以下のことに気を付けましょう。
- ・部屋を完全に締め切る
- ・アライグマ用の出口を確保する
くん煙剤は、煙を使ってアライグマを追い出すために使用します。そのため、肝心の煙が部屋の外に漏れないようにすることが大切です。
また、アライグマの脱出口を作ることも忘れないようにしましょう。
ただし、常にアライグマが部屋にいるときは自分で対処するのは危険です。害獣駆除業者に連絡をして
相談するとよいでしょう。
木酢液(もくさくえき)
木酢液とは、木炭を作る際に発生する蒸気を冷やして、液体にしたものです。木酢液の臭いは独特で、山火事のような匂いがするそうです。
アライグマはその匂いを嫌がるので、アライグマ対策として人気があります。
また、木酢液には殺菌作用があり、農作物などに付着した病原菌を死滅させる効果もあります。
木酢液はホームセンターなどで買える他、自宅で作ることもできるので、気軽に実践することができます。
作業手順1:木酢液の準備
木酢液をペットボトルに詰めます。ペットボトルは、飲み口が顔を出すくらいの深さまで地中に埋め込んで使用します。
作業手順2:安全確認
木酢液の設置場所や付近にアライグマがいないか確認しましょう。アライグマは好戦的な性格をしているわけではありません。しかし、中には狂犬病を発症しているアライグマもいるため、迂闊に近づかないようにしましょう。
もしアライグマがいる場合には、害獣駆除業者に連絡をするか、数時間後にまた様子を見てみましょう。
作業手順2:木酢液入りのペットボトルを埋める
木酢液の入ったペットボトルを地面に埋めます。大体3~5mの間隔で設置していきます。
アライグマは嗅覚が鋭い四足歩行の動物です。鼻先を地面に近づけて匂いを嗅ぐ習性があるため、出来る限り地面に近い場所に設置するようにしましょう。
木酢液の効果が出にくいとき
木酢液の効果が今一つなときは、以下のポイントができている確認しましょう。
- 継ぎ足しをしているか
- 雨で木酢液が薄まっていないか
木酢液の量が減っていると効果は出にくいです。定期的に見回って、きちんと木酢液の匂いがするかどうか確認しましょう。
また、雨で木酢液が薄まっている可能性もあります。これも効果が半減する原因なので、雨が降りそうならペットボトルに蓋をするか、雨が止んだ後に継ぎ足しをするようにしましょう。
成功率を上げるには

木酢液を使って上手にアライグマを追い出すには、以下のポイントが大切です。
- ・地面の近くに配置する
- ・木酢液の濃度が薄まっていない
アライグマは地面の匂いを嗅ぎながら移動します。そのため、ぶら下げるよりも地面に設置した方が効果が高いです。
また、木酢液の濃度が薄まっていると、アライグマの忌避効果が下がってしまいます。
アライグマが嫌がる匂いがちゃんとするか定期的に見回ることが大切です。
超音波発生装置
超音波発生装置は、文字どおりアライグマの嫌がる超音波を発生してアライグマを追い出すための装置です。
アライグマのいない間に装置を設置すればよいので、これも比較的簡単な追い出し方です。
ただ、耳の聞こえがよい人は超音波を聞き取ることができるため、子どもやペットなどがいる場所で使うのは控えたほうがよいです。
超音波は基本的には人間の聞き取れない音とされていますが、聞こえる人もいますし、聞こえると不快感を与えてしまいます。
超音波の周波数は商品ごとに異なるので、事前にどのくらいの周波数なら周囲に迷惑をかけずに使用できるか、確認することが大切です。
作業手順1:超音波発生装置の購入

超音波発生装置を購入する際のポイントとして以下のものが挙げられます。
- ・人間が聞き取れてしまう周波数でないか
- ・長時間使用できるか
人間が聞こえる可聴域はおよそ20Hz~23kHzとされています。一方でアライグマの場合は、約100Hz~40kHzと人間よりも広い範囲の音を聞くことができます。
もし人にも聞こえてしまいそうな場合は使用を控えるか、田畑など閑散とした場所でのみ使用するようにしましょう。
また商品の中には、光も発してアライグマをより近づけさせないようするものもあります。アライグマは夜行性なため、光に弱く効果はあるという意見もありますが、同じく夜行性のハクビシンの中には、光に興味を持ってむしろ近づいてきたというケースが報告されています。アライグマとハクビシンは全く異なる動物ではありますが、夜行性だからといって一概に効果があるとは言えず、果たしてアライグマに対してどの程度効果があるか、断言することはできません。
作業手順2:超音波発生装置の設置
設置の際には、周囲にアライグマが潜んでいないか念入りに確認しましょう。
アライグマがいなければ、設置の作業に移ります。
壁などの障害物があると音が広範囲に届かなくなります。
説明書のとおりに装置をセットして作業は完了です。
超音波発生装置の効果が出にくいとき
超音波発生装置の効果が感じられない理由として、以下の点が指摘できます。
- 電源が途中で切れてしまっている
- アライグマが慣れてしまった
電力が足りず装置の音が止まってしまうと、アライグマが簡単に侵入できるようになってしまいます。
超音波の音が聞こえないと気づきにくいですが、定期的に電源が落ちていないか確認するようにしましょう。
また、アライグマが音を気にしなくなったというケースも考えられます。
アライグマは適応能力が高く、音があるという環境に適応してしまったのかもしれません。
また、アライグマが不快に感じるとはいえ、不快感を上回る魅力的な食物があれば、アライグマの侵入を防ぐことは難しいです。
そのような場合には、他の対策方法を講じる必要があります。
成功率を上げるには

超音波発生装置を使ってアライグマを侵入を防ぐには、以下のポイントが大切です。
- ・障害物のないところにセットする
- ・電源が落ちないよう常に充電できるようにする
超音波装置や匂い対策には一定の効果がありますが、アライグマが慣れてしまえば意味がありません。
もしアライグマが戻ってきた場合には同じ策を使っても効果がないことがあります。そのような事態になって困っている方は、害獣駆除業者に相談するとよいでしょう。
侵入口の封鎖

住宅などでアライグマの侵入ルートがあらかじめ分かっている場合には、直接侵入口を塞いでしまうことが有効です。
アライグマの侵入経路として最も多いのが、屋根裏付近です。
屋根のちょっとした隙間からでもアライグマは侵入することができます。手先が器用で力も強いアライグマは、ブリキなどの屋根材をこじ開けて侵入してくることもあります。
次に多いのが、床下の通気口からの侵入です。
3~5㎝程度の隙間があれば、アライグマは容易く侵入してきます。
外壁に泥などで人の手のような足跡があれば、アライグマによる被害の可能性が高いです。
作業手順1:侵入口の確認
必ずしも侵入口が1つとは限りません。侵入口が他にもないか念入りに点検します。
アライグマが小さな隙間に潜んでいる可能性があります。侵入口を探そうと見えにくいところまで捜索すると、物陰からアライグマに襲われることもあるため、安全を優先して点検するようにしてください。
アライグマは身体能力に優れており、壁登りだけではなくジャンプすることもできます。垂直方向に約110㎝、水平方向に約120㎝は飛ぶことができるので、周囲から離れた窓枠などを伝って侵入できないかなど、想像力を働かせながら探してみましょう。
作業手順2:侵入口の封鎖
アライグマは器用で力が強いため、金属製のプレートや頑丈な木材などでしっかりと塞ぎます。
作業中にアライグマと遭遇すると攻撃される可能性があるため、周辺にアライグマが来ていないか確認しながら作業しましょう。
侵入口を封鎖しても効果がないときは
そのようなときは、他に侵入口がある可能性があります。今一度確認してみましょう。
もし侵入経路を見つけるのが難しい場合には、害獣駆除業者に相談してプロに任せるのも手です。
成功率を上げるには

アライグマの侵入口を塞ぐポイントは、以下のとおりです。
- 頑丈な素材でしっかりと塞ぐ
- できる限り全ての侵入経路を塞ぐ
侵入経路を塞げば住宅被害の根本的な解決にもつながります。ただ、侵入口を見つけるのは難しい場合がありますし、アライグマが隠れていると攻撃されることもあります。そのため、自分では対処が難しいと感じたら、害獣駆除業者に連絡するのが無難です。
電気柵

アライグマは賢く器用なため、簡単に壁を登ったりトンネルを作ったりすることができます。そのため、一般的な害獣対策用のフェンスや防獣ネットではあまり効果がありません。
農地などアライグマに入ってきてほしくない場所を守るには、電気柵で周囲を囲ってアライグマを排除する方法もあります。電気柵であれば、アライグマ以外の野生動物にも効果があるので害獣対策には打ってつけです。
多くの電気柵は100~200mほどあります。もし足りない場合には、設置距離を延長できるタイプのものも売られているので、そちらを検討しましょう。
作業手順1:設置場所の確認
まずはアライグマの侵入を防ぎたい場所はどこか、具体的な範囲を定めましょう。あまり広くしてしまうと電気柵の長さが足りなくなり、周囲を適切に囲むことが出来なくなってしまいます。メジャーなどを使用して範囲を決めることで、失敗するリスクを減らすことができます。
範囲が決まったら、どのくらいの高さの電気柵が必要か計算しましょう。電気柵を設置する付近に木が生えていると、その木を伝ってアライグマが侵入してくる可能性があります。その他にもアライグマが侵入できそうな経路はないか考えることで、電気柵を効果的に使うことができます。
作業手順2:電気柵の購入
安全確認
電気柵はホームセンターや通販サイトなどで販売されているので、気軽に買うことができます。しかし、中には安全面において重大な欠陥のある商品も販売されているので注意しましょう。特に、以下の4点があるかどうかをよく確認しましょう。
- ・電気柵用電源装置(電気柵本機)
- ・ACアダプター
- ・漏電遮断器
- ・パルス電流
電気柵電源装置は、人に危険が及ぶことがないように出力電流に制限がありますが、一般的な家庭用電源にはそのような仕組みはありません。
また、漏電遮断器を使用せずに直接家庭用電源から電気を流してしまうことも危険です。感電したときに絶え間なく電気が流れ続けてしまい、筋肉が痙攣して重大な事故になる可能性があるからです。漏電遮断器は、使用電圧が100V以上の電源から電気供給を受ける際に設置する義務があります。漏電遮断器を使用しなかった場合には法律違反となってしまうので、必ず設置しましょう。
電気柵に流す電流は、パルス電流の方が安全です。パルス電流は、短期的かつ瞬間的に流れる電流なので、間違って電気柵のワイヤーに触れてしまっても一瞬で手を離すことができます。
商品の電源の取り方がどうなっているかを必ず確認してから、購入するかどうか検討するようにしましょう。
購入する際のポイント

電気柵は高価なので、必要な長さを補えるかどうか吟味しながら選びましょう。また、ソーラー式や乾電池式などさまざまなタイプがあるので、天気や設置場所の環境を踏まえた上で選ぶと、正しく電気柵を使うことができます。また、アライグマ対象のものかどうかきちんと確認することで、買い物ミスを減らすことができます。
アライグマ対策用電気柵の購入ポイント
- ・アライグマ対象になっていること
- ・必要な長さが充分にあること
- ・設置場所の環境に合っているタイプを選ぶこと
電気柵の中に人間が入るための出入り口も確保する必要があります。電気柵の出入り口には以下のものがあります。
- ・ゲートハンドル
- ・ワンタッチゲート
- ・ゲートリール
ゲートハンドルは、電気ワイヤーの一部に絶縁体のハンドルを取り付けて、出入りするときにハンドルを持ち上げて使用します。他のものに比べて安価で、種類も豊富です。握りやすいサイズで滑りにくい素材のものを選ぶとよいでしょう。ただ、ゲートハンドルを引っ掛けておくためのゲートアンカーがないと使用することができないため、別売りの場合にはゲートアンカーを買う必要があります。
ワンタッチゲートは他のものと比較するとかなり高額ですが、簡単に出入りすることができるので便利です。ただ、部品の数が多いため設置に時間がかかるかもしれません。
ゲートリールは、ワイヤーを巻き取って出入りする仕組みになっています。価格はゲートハンドルよりやや高い程度です。自動巻き取り式のものもあり、ワイヤーがたるんで他のワイヤーに接触するリスクがなくなるので安心して使うことができます。
電気柵だけで大丈夫なの?
他のネット記事では、アライグマは穴掘りが得意なので地中の対策も万全にしようという意見が書かれています。
しかし、実はアライグマは自分で穴を掘ることはありません。巣穴も自ら掘るのではなく、樹木の穴や他の害獣が作った巣に住みつきます。
しかし、アナグマなど他の害獣による被害がある場合には、地中の対策をすることをおすすめします。
地中部分は、フェンスを埋め込むことで対応可能な場合が多いようです。
作業手順3:電気柵の設置
電気柵が準備できたら設置しましょう。
順番は以下のとおりです。
1.周辺の雑草を刈り取って、地面を平らにならす
雑草が生えていると漏電の原因になってしまうことがあります。漏電してしまうと危険ですし、肝心のアライグマ除けにはならなくなってしまいます。
また、地面を平らにならすことで支柱が打ち込みやすくなるため、凹凸や隙間などは埋めるようにしましょう。地面とワイヤーの距離に差があると、アライグマの侵入を許す原因にもなります。特に一番下のワイヤーの位置には、充分注意しましょう。
2.ワイヤーや埋める位置の印をワイヤーに付けて、フックを取り付ける
毛皮に覆われているアライグマは、電気のとおりやすい鼻先にワイヤーが当たるようにすると効果的です。アライグマの鼻先に当たるようにするには、地面から10㎝離れた位置にワイヤーを通すようにしましょう。
アライグマは中型動物なので、地中に埋める支柱の長さは30㎝あれば足ります。
3.支柱を目安ラインまで打ち込む
平坦な地面に打ち込むときは、およそ4m間隔で打ち込みましょう。
先に四隅の支柱を立てることで、ワイヤーをまっすぐに張ることができます。
また地面がでこぼこの場合は、へこんでいるところからの侵入を防ぐために支柱を追加して地面からの距離が一定になるようにすることができます。
4.ワイヤーを張り、出入り口を作る
ワイヤーがたるまないように張りましょう。もしワイヤーが余ってしまったら、リールなどを使って調整します。
5.ワイヤーの上下に結線を付ける
結線は、電気の回路を作るために部品を電線でつないで配線するためのものです。50~100mの間隔で取り付けていきます。
6.危険表示板を掲示する
人が通る面や目立つところに掲示しましょう。
電気柵のテスト中に人が振れてしまう可能性もあるので、電気を通す前に掲示した方がよいです。
7.出力コードをワイヤーに取り付けて、アース棒をすべて地中に埋める
アース棒を地中深くに埋め込み、電源装置の-端子とアース棒を接続します。+端子をワイヤーに接続させれば、電気柵の設置が完了します。
アース棒とは、絶縁不良や漏電による感電や火災などの事故を防ぐためのものです。アース棒を地中に埋め込むことで、電気柵に万一触れてしまっても電気を地中に流すことで、電気柵本機に漏電を知らせて電気の流れを止めることができます。
なお、漏電遮断器を取り付けているときもアース棒は必要です。もし漏電遮断器があってもアース棒を付けていなかった場合、漏電電流が行き場を失って漏電が継続してしまいます。しかしアース棒があれば、アース棒を経由して漏電電流が流れていき、電気柵本機の作動を止めることができます。
作業手順8:周辺の最終確認
電気を流してテストをする前に、再度ワイヤーに雑草が接触していないか、アライグマの侵入口になりそうなところはないか確認しましょう。危険表示板も見やすい位置にあるか再度点検すると、安全です。
作業手順9:テスト
電源装置をオンにして、
- ・各ワイヤーが通電しているか
- ・推奨値まで電圧が出ているか
電圧チェッカーを使用して確認しましょう。
確認して問題がなければ、電気柵の設置作業は終了です。
電気柵を使っても効果がでないときは
電気柵を使っていてもアライグマの被害が減らないときには、以下の可能性が考えられます。
- ・24時間365日稼働していない
- ・維持管理をしていない
ソーラーパネル式の場合では、梅雨の時期や冬場など、悪天候が連日続くと電源が落ちてしまうことがあります。その隙を狙ってアライグマが侵入してしまうと、被害に遭ってしまいます。
電力の供給方法を変えるか、太陽光が長時間当たる位置にソーラーパネルを設置して、電気柵に常に電気が流れるようにしましょう。
メンテナンスを定期的に行っていないことも、電気柵の効果を落とす原因になります。最初に刈った雑草が伸びていないか確認しましょう。特につる植物が絡まって漏電しやすくなるため、確実に取り除きましょう。
草刈り機を使用するときに支柱やワイヤーを切らないようなクリップが売っているので、そちらを使うとメンテナンスがしやすくなります。
また、力の強い動物に襲われて支柱が傾いてしまうとワイヤーがたるんで隙間が大きくなってしまうこともあります。きちんとアライグマの鼻先に当たる位置にワイヤーがあるか、見回ることも大切です。
成功率を上げるには

電気柵の効果を充分に発揮させるには、以下の点が重要です。
- ・アライグマの鼻先の当たる位置にワイヤーを通す
- ・常にワイヤーに電気を流す
- ・ワイヤーがどこにも触れていない
アライグマは全身毛におおわれているため、身体にワイヤーが当たっても電気が通りにくいです。そのため、毛のない鼻先に当てる必要があります。アライグマの鼻先は、地面からおよそ10㎝なので、その位置にワイヤーを通すようにしましょう。
アライグマは夜行性ですが、昼間は絶対に活動しないというわけではありません。むしろ昼間に活動しているのはお腹が空いているときなので、作物が狙われやすく、危険です。そのため、24時間常に電気を流すようにしましょう。
雨が降っていても通電させることに問題はありません。ただ、雑草などがワイヤーに触れていると、雨の日の方が電気抵抗が少なくなり、漏電しやすくなります。また、雨でワイヤーが濡れていると電気の消費量が多くなるので注意が必要です。
ワイヤーに雑草などが触れていると、漏電の原因になります。漏電しているとアライグマがワイヤーに触れても電気ショックを与えることができないため、侵入を許してしまいます。なので、草刈りをして定期的にメンテナンスを行いましょう。
有刺鉄板

有刺鉄板は、鋭いトゲによって動物の侵入を阻むものです。特に、壁登りが得意な動物に効果があります。
アライグマは指が長く手先も器用なため、簡単に壁を登ることができます。そのため、アライグマ対策として有刺鉄板は有効でしょう。
ちなみに、有刺鉄線ということばは知っていても、有刺鉄板ということばはあまり耳慣れないと思います。ですが、果樹園や敷地周辺のフェンス、住宅の雨どいまで使用できる場所は多岐に渡ります。
有刺鉄板は、有刺鉄線よりもトゲの間隔が狭いため、アライグマの侵入をより防いでくれるようになっています。
また、忌避剤の臭いが苦手な方は有刺鉄板を活用してみるのもよいでしょう。
作業手順1:設置場所の確認
有刺鉄板を購入する前に、以下のポイントを踏まえて設置場所を確認しましょう。
- ・必要になる有刺鉄板の長さ
- ・周囲の人通りは激しいか
有刺鉄板は、木に巻き付けたりフェンスの上部分に巻き付けたりして使います。有刺鉄板の長さが足りなくなると、充分に効果を発揮することができません。どのくらいの長さの有刺鉄板が必要になるか、購入前に計測しておくことで買い物ミスを減らすことができます。
また、有刺鉄板のトゲに人が触れると、思わぬ事故に繋がります。周辺の往来が激しい場合には、使用を避けたほうが無難です。そうでなくても、警告板などを掲示して周囲に注意喚起をするようにしましょう。
作業手順2:有刺鉄板の購入

有名なホームセンターのオンラインショップで有刺鉄板を検索してみましたが、見つかりませんでした。そのため、有刺鉄板はネット通販などで買うのが手っ取り早いと思います。
有刺鉄板は〇枚入りのようにして売られているので、一枚当たりの面積と枚数を比較してから自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
商品によって、有刺鉄板の耐用年数や素材が異なるので設置場所の環境に合わせて商品を吟味するとよいです。
電解研磨処理の施されたステンレス製のものならば、雨に濡れても錆びにくくお手入れがしやすいです。
作業手順3:有刺鉄板の設置
有刺鉄板を設置する前に、以下の道具を揃えておきます。
- ・厚手の手袋
- ・ハサミ
- ・警告板
- ・ペンチ
- ・針金
針金については、商品に専用の取り付けバンドなどが付いてきている場合には不要です。
有刺鉄板の設置作業に取り掛かる前に、警告板を掲示しましょう。
また、トゲから手を守るために厚手の手袋も忘れずに装着してください。
商品によっては家庭用のハサミで切断できるものもありますが、詳しい設置方法については、説明書に従うようにしてください。
有刺鉄板の効果が出にくいとき
有刺鉄板を設置してもアライグマの侵入が続いているときには、以下のことが考えられます。
- ・他の侵入ルートがある
- ・有刺鉄板が錆びてトゲが丸くなっている
他の侵入ルートがあると、有刺鉄板を設置していてもアライグマの侵入を止めることはできません。アライグマは手先が器用で賢い動物なため、もしかしたら他のルートを開拓していることもあるでしょう。そのため、他に侵入経路はないか見回って点検する必要があります。
また、有刺鉄板が錆びてトゲの鋭さがなくなっていると、アライグマの侵入を許してしまうこともあるかもしれません。
有刺鉄板を設置した後は、定期的に水で洗って清潔に保つようにします。
もし錆びが出てしまったら、素材にもよりますがステンレス製の場合、
- ・酸を使う
- ・電解研磨を行う
- ・紙やすりなどで物理的に取り除く
ことで錆びを落とすことができます。
ただし、紙やすりを使うと表面が傷ついて錆びやすくなる他、電解研磨を行うには工場などに持ち込む手間があります。そのため、一番手軽にできるのは、錆び落とし剤を使って対処する方法です。最近では100円均一などでも販売されているので、簡単に購入できます。錆び落とし剤は素材によって成分が異なるので、購入前に有刺鉄板の素材を調べておくようにしましょう。
成功率を上げるには

有刺鉄板を効果的に使うには、以下のポイントが重要です。
- ・充分な長さの有刺鉄板を使って保護する
- ・水洗いをして清潔に保つ
有刺鉄板の長さが足りないと、トゲのないところからアライグマが侵入してきてしまいます。そのため、どこにどのくらいの長さの有刺鉄板が必要か事前に計画を立ててから買うようにしましょう
有刺鉄板を設置した後は、定期的に水で洗って汚れを落とすことで長持ちします。
錆がないかどうかなど、定期的に見回ることが大切です。
追い出しだけでは対策は不十分?!
今まで紹介した方法はアライグマを追い出すためのものです。アライグマは利口な生き物なので、一時的に効果はあっても、抜け道を見つけたり適応したりして、また戻ってくるかもしれません。
他の手法を使っても同じことの繰り返しになるかも…
手っ取り早くアライグマの被害をなくしたい方には、害獣駆除業者によるアライグマの駆除がおすすめです。
なぜ駆除は一般の人ではできないの?
アライグマは2005年に特定外来生物に認定されました。
外来生物法に基づいて、アライグマは狩猟免許なしでの駆除が禁止されました。
なので狩猟免許を持たない一般の方は、捕獲機を用いたアライグマの捕獲や駆除ができません。
アライグマを駆除するには
アライグマを駆除するなら、害獣駆除業者に任せるのがおすすめです!
経験豊富な業者に頼めば、迅速に対応してアライグマを完璧に駆除してくれますし、アフターサービスが整っているところもあります。
何より時間と手間をかけずに、アライグマの被害をなくすことができるのです。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
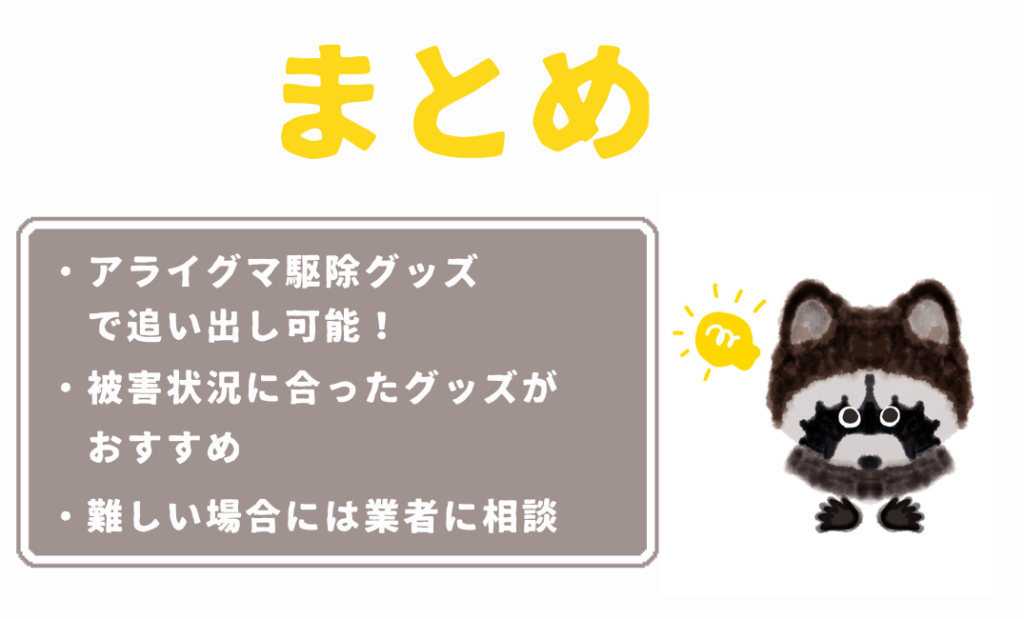
被害状況に合った対策方法は見つかりましたか?
今回紹介したアライグマの追い出し方法は簡単にできるものですが、人間慣れして知恵をつけたアライグマには太刀打ちできないかもしれません。
自分で退治することが難しい場合は、アライグマ専門の駆除業者に依頼してみるとよいでしょう。害獣駆除業者は経験豊富で手練れのアライグマを駆除した実績を持っているところもあります。また、迅速かつ丁寧な対応をしてくれるところもあるので、ぜひ検討してみてください!


コメント