コウモリは日本全国に生息しています。放置すると深刻な健康被害や自宅の損傷にもつながりかねないため、コウモリに気づいたら早めの対策が肝心です。
この記事では、コウモリの生息地や生態、自分でできるコウモリ対策などについて解説します。不安を解消し、自宅で安心して過ごすためにもぜひ最後までご覧ください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

コウモリの生態とは?

日本の家屋に住み着き、多くのトラブルの原因となるのは「アブラコウモリ」です。
ここでは、アブラコウモリの基本的な生態やコウモリが生息しているサインについて解説します。
【一覧表】知っておきたいコウモリの基本生態
まずはコウモリの基本的な生態を、以下の表で確認しましょう。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 種類 | アブラコウモリ | 住宅に住み着く代表的なコウモリ |
| 生息地 | 日本全国 | 近年は北海道でも被害が報告されている |
| 体長 | 5cm程度 | 大人の親指ほどの大きさ |
| 主なエサ | 昆虫類(蚊、ユスリカなど) | 1日に約100匹の虫を捕食する |
| 活動時間 | 夜行性 | 日没から明け方までエサを求めて飛び回る |
| 活動時期 | 主に5~10月 | 冬季は冬眠する |
| 繁殖期 | 主に7~8月 | 一度に1~3頭の子どもを産む |
世界には約1,000種類の大小さまざまなコウモリが存在しています。
日本で多く見られるアブラコウモリは、中でも小型なのが特徴です。また蚊やハエなどを大量に捕食するため、益獣としての一面も持ち合わせています。
コウモリが好んで捕食する昆虫については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
参考:国立研究開発法人 国立環境研究所「侵入生物データベース(アブラコウモリ)」
コウモリが自宅に住み着いた2つのサイン
コウモリが自宅に住み着くと、以下の2つのサインが見られることがあります。
- 不審な物音や鳴き声
- 黒くて細長いフン
日没ごろや明け方に天井裏や壁の中から「カサカサ」「カリカリ」といった物音や「キーキー」「チチチ」といった鳴き声が聞こえてきたら、コウモリが住み着いている恐れがあります。
またベランダや窓の下などに黒いフンが落ちていたり異臭がしたりする場合は、近くに生息しているサインと考えましょう。
なおフンは、5〜10mmほどの黒くて細長い形状です。一見するとネズミのフンに似ていますが、コウモリのフンは非常にもろく、指で軽くつまむとパサパサと崩れる点が特徴です。
コウモリが住宅で生息地にする場所5選

以下に挙げる5つは、コウモリが住宅で生息地にする可能性の高い箇所です。
- 屋根裏・天井裏
- 換気口・通気口
- 外壁の隙間・ひび割れ
- シャッターや雨戸の戸袋
- エアコンの室外機の裏側
コウモリの体長は5cm前後しかなく、1.5cmほどの隙間さえあれば簡単に侵入できてしまいます。
「うっかり見落としてた」とならないよう、ぜひ日頃のセルフチェックにお役立てください。
屋根裏・天井裏
住宅の中でも、特にコウモリの生息地として選ばれやすいのが屋根裏や天井裏です。
屋根裏や天井裏は外部からの侵入が難しく、天敵に襲われる心配がほとんどありません。さらに、断熱材などがあるため冬でも暖かく、コウモリの生育に適した環境です。そのため一度住み着かれると、100匹以上の集団(コロニー)を形成するケースも少なくありません。
大量のフンによる悪臭や建材の腐食、騒音被害など、生活に深刻な影響を及ぼす恐れもあるため、警戒が必要です。
換気口・通気口
換気口や通気口も、コウモリが住み着きやすい箇所の一つです。特に格子状のカバーが付いているだけのタイプの換気口は、コウモリの侵入を防ぐことはできません。
浴室やトイレの換気扇ダクトの周りに黒い汚れが付着していたり、真下にフンが落ちていたりする場合は、すでに侵入されている可能性が高いと考えましょう。
外壁の隙間・ひび割れ
モルタル壁のひび割れや、サイディングボードの継ぎ目の劣化など、外壁にできたわずかな隙間もコウモリの生息地になります。
壁の内側にある断熱材との間の空間は、コウモリにとって雨風をしのげる絶好の隠れ家です。
「壁の中から音がするので調べたら、壁材の内部にコウモリが潜んでいた」というケースは珍しくありません。特にエアコンの配管口の周りや、増築した部分との接続面などには注意が必要です。
シャッターや雨戸の戸袋
シャッターや雨戸の戸袋も、コウモリにとっては快適な生息地になり得ます。
特に閉まったままのシャッターや雨戸の内部は、日中に身を隠すのにはぴったりな環境です。「久しぶりに動かしたら大量のフンが落ちてきた」という事態にならないよう、定期的なチェックを心がけましょう。
エアコン室外機の裏側
コウモリはエアコンの室外機の裏側に潜んでいる場合もあります。
壁との間にできる数㎝の隙間は、コウモリが体を休めるのにちょうど良いスペースです。「捕食中の休憩場所になっているうちに、近くにある配管の隙間などから住宅内へ侵入されてしまった」というケースもあるため、フンの有無をチェックする習慣をつけましょう。
コウモリを放置することで起きる3つの深刻なリスク
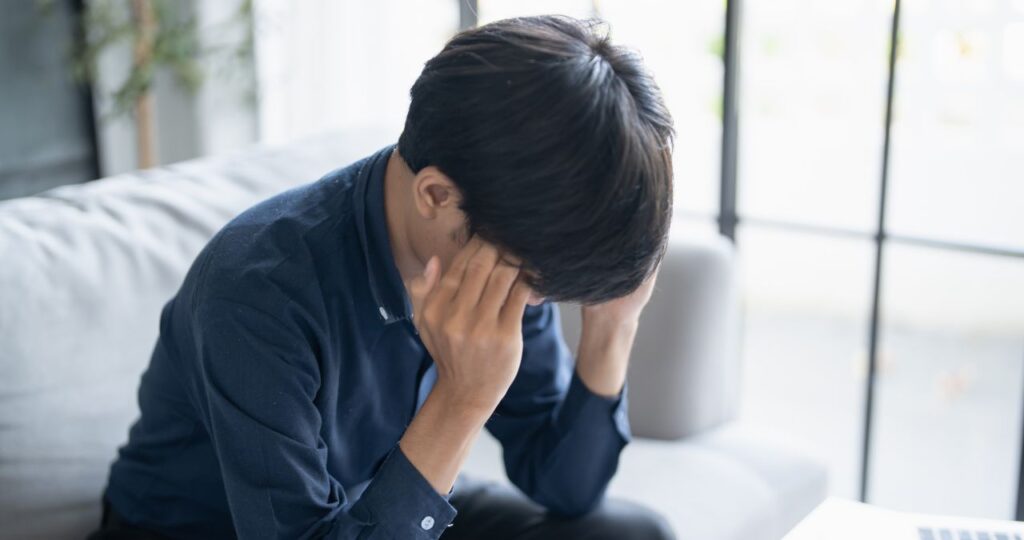
コウモリの生息に気づきながら「蚊などを食べてくれるなら」「ゴキブリを駆除してくれるかも」と、様子を見るのはおすすめできません。
以下はコウモリを放置することで起こりうる3つのリスクです。
- アレルギーや感染症などの健康被害
- 騒音や悪臭が引き起こすストレス
- 住宅自体の損傷
ここでは、絶対に知っておくべきリスクを具体的に解説します。
アレルギー・感染症などの健康被害
コウモリがもたらす深刻なリスクが、健康被害です。
コウモリのフンは乾燥すると粉末状になり、空気中に舞い上がります。万が一吸い込むと、ヒストプラズマ症などの深刻な感染症を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。
また、コウモリの体にはダニやノミなどの害虫が寄生している場合もあります。コウモリが自宅に住み着くことで害虫が室内に侵入すると、アレルギーや皮膚炎などの二次被害に発展するケースも少なくないため、早急な対策を検討しましょう。
コウモリが引き起こす健康被害については、以下の記事もチェックしてみてください。
騒音や悪臭が引き起こすストレス
騒音や悪臭が引き起こす精神的苦痛も、コウモリを放置するリスクの一つに挙げられます。
コウモリは夜行性のため、人々が寝静まる深夜から明け方にも活発に動き回ります。甲高い鳴き声や天井裏を走り回る物音、羽ばたきの音などが気になり、長期間の睡眠不足に悩まされている方も少なくありません。
さらに、コウモリのフンや尿からは強烈なアンモニア臭が発生します。場合によっては居住スペースにまで漏れ出す恐れもあるため、要注意です。
住宅自体の損傷
コウモリのフンや尿は、大切な自宅の資産価値を落としてしまう恐れもあります。
コウモリのフンや尿に含まれる成分は、木材や金属を腐食させる力を持っています。また、湿ったフンは断熱材を汚染し、機能を低下させるだけでなくカビの温床にもなります。
「気が付いたときには住宅内部の被害が深刻化していて、駆除費用に加えて大規模なリフォームや修繕が必要になってしまった」という事態につながる可能性も否定できません。
自分でできるコウモリ対処法3ステップ

自宅に住み着いたコウモリを自分で対処する際には、以下の3ステップで作業を進めましょう。
- 住処の特定
- 忌避剤などで追い出す
- 侵入路を塞ぐ
「コウモリがいるかも」と思ったら、住処を特定します。日没前後にコウモリが活動し始めたら、忌避剤などを使って完全に追い出しましょう。コウモリをすべて追い払ったら、生息箇所や周辺を清掃・消毒し、金網やコーキング剤などで侵入路を徹底的に塞ぎます。
コウモリの住処や侵入路が特定できなかったり、作業に不安があったりする場合は、駆除の専門家に相談するのもおすすめです。
コウモリ駆除専門家を選ぶコツについては、以下の記事も参考になさってください。
【要注意】駆除作業中にコウモリを捕まえたり傷つけたりはNG
自分でコウモリを駆除する場合には、コウモリを「追い出すこと」に徹しましょう。
コウモリは「鳥獣保護管理法」という法律によって守られている動物です。たとえ自宅に住み着いたコウモリであっても、許可なく捕まえたり傷つけたり、殺してしまったりすると、法律違反に該当する恐れがあります。
違法とみなされた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあるので注意しましょう。
参考:e-GOV法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
コウモリ被害でお悩みなら協会の無料相談をご活用ください

ここまで読んで「自分だけでのコウモリ駆除は難しいかもしれない」と少しでも感じたら、ぜひ「日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」の無料相談をご利用ください。
当協会は、コウモリをはじめとした鳥類・害獣による家屋被害に対し、安全で安心な生活環境を守るための防除・管理を専門とする団体です。
経験豊富な担当者が状況を聞き、効果的な対策のアドバイスや専門業者探しをお手伝いします。「こんなことを聞いても良いのかな?」と不安に思うような内容でも、もちろん大丈夫です。ぜひお気軽にご相談ください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
今回はコウモリの生息地と生態について、紹介しました。
日本には約30種類のコウモリが存在しています。特に住宅に生息することの多いアブラコウモリは、小型でちょっとした隙間からでも侵入し、人間に被害をもたらすため注意が必要です。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会では、無料相談を行っているため、コウモリの被害でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。


コメント