アリ・シロアリ・ネズミなど、害虫・害獣を駆除した場合には、一定の条件を整えることで確定申告時に費用(税金)の一部が戻ってくることがあります。
しかし、害虫・害獣駆除にかかる費用は、期間や状況によって変化するため、確定申告の際に勘定科目をどうするべきか迷ってしまう方も多いでしょう。
この記事では、害虫駆除費を経費や雑損控除の対象とする方法や申告時の注意点について解説します。
害虫(害獣)駆除にかかる費用をできるだけ削減したいとお考えの方は、ぜひ本記事を参考に対応を進めてみてください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

害虫駆除費は確定申告時に控除を受けられる

害虫駆除にかかった費用は、翌年の確定申告時に適切な申請をおこなうことで控除を受けられる可能性があります。
この章では、その詳細についてご紹介します。
事業に関することで害虫駆除をおこなった場合
たとえば、飲食店・事務所・工場など事業に関係する場所で害虫駆除をおこなった場合、駆除にかかった費用を「経費」として計上することができます。
この場合の勘定科目は、どのように駆除をおこなったかによって変化します。
- 業者に依頼した場合→「施設維持費」「衛生費」
- 市販の駆除剤を購入した場合→「消耗品費」
- 害虫による建物の修繕にかけた費用の場合→「修繕維持費」 など
事業に関連する費用は基本的に「経費」とすることができますが、駆除方法によって勘定科目が変化する点に注意しておきましょう。
住居としている建物で害虫駆除をおこなった場合
お住いの家など、住居としている建物で害虫駆除をおこなった場合は「雑損控除」の対象となります。
そのため、確定申告(還付申告)時に適切な申請をおこなえば、所得税の還付を受けられる可能性があるでしょう。
雑損控除を受けたい場合は、確定申告書類に必要事項を記入したうえで、駆除費用の領収書や源泉徴収票などを添付・申請します。
なお、還付だけ受ける場合は、対象年の翌年から5年間おこなうことが可能です。
雑損控除を受ける条件と計算方法について

雑損控除とは、端的に説明すると「自分の所有する資産が被害を受けた際に、翌年の所得税を減らすことができる制度」のことです。
ただし、雑損控除を受けるには一定の条件を必要とします。
この章では、雑損控除を受ける条件や計算方法について解説を進めていきましょう。
雑損控除を受ける条件とは?
雑損控除を受けるための条件として、被害を受けた「人」や「場所」さらに「誰が駆除したのか?」が重要なポイントになります。
それぞれ、以下で詳細を解説していきます。
誰が被害を受けたのか?
雑損控除は、誰にでも適用されるわけではありません。
基本的には、被害を受けた建物や家財などの資産を所有する方+所得税を納めている方に適用されます。
また、資産を所有している人の配偶者などの親族であること+その人物の年間総所得が38万円以下の場合にも適用されます。
どういった場所(資産)に被害を受けたのか?
雑損控除を受けるためには「被害を受けた場所(資産)が生活に欠かせないもの」である必要があります。
たとえば、日常生活を送っている住宅がシロアリなどの被害を受けた場合は、雑損控除の対象となる可能性が高いでしょう。
しかし、別荘や貸し出している物件など、日常生活に必要のない資産であれば、雑損控除の適用外となります。
また、30万円以上するような資産(貴金属や絵画など)の場合も、適用の対象外となってしまうケースが多いとされています。
雑損控除の対象かどうかは、事前にチェックしておくことが望ましいといえるでしょう。
誰が駆除をしたのか?
雑損控除の対象となるのは「業者に支払った駆除費用」であり、自身で市販の駆除グッズを使い対処した場合は雑損控除を受けることができません。
加えて、業者に依頼した場合も「駆除」が対象となるため、「予防」に対して雑損控除が適用されることもありません。
控除を受けるには、害虫駆除業者に駆除を依頼することが必須となるという点に注意しておきましょう。
雑損控除の計算方法とは?
雑損控除を受ける場合の控除額の計算方法は、以下の通りです。
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
この計算式のうち、多いほうの金額が控除額となります。
要注意点としては「雑損控除の金額そのまま税金が安くなるわけではない」ということが挙げられます。
所得税=(総所得-控除金額)×税率のため、翌年に支払う所得税を計算したい場合は、この計算方法に金額を当てはめてみましょう。
また、雑損控除以外にも控除される金額があれば、所得税をより安くすることができるはずです。
駆除費用を負担してもらえるケースもある
以下のように、物件によっては害虫駆除にかかった費用を負担してもらえるケースもあります。
- 新築物件:引き渡しから10年未満
- 中古物件:購入してから1年未満
- 賃貸物件:基本的に貸主が駆除費用を負担する(貸主には居住者が快適に暮らせる住環境を提供する義務があるため)
ただし、契約内容によっては上記が該当しない可能性もあります。
害虫駆除を業者に依頼する場合は、事前に必要な個所に確認を取ることをおすすめします。
害獣駆除における雑損駆除の申請方法

この章では、害獣駆除における雑損駆除の申請方法について解説します。
雑損控除を受けるには必要な書類を準備する必要があるため、申請の流れを把握し・しっかりと準備をおこなうことでスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
申請の流れ
申請の流れは、おもに以下の通りです。
- 税務署で確定申告書をもらう
- 確定申告書に雑損控除の内容を記入する
- 害虫駆除と修繕工事の領収書+給与所得がある方は源泉徴収票も貼り付ける
- 納税をおこなっている地域の税務署に提出する
- 1か月~2か月ほどで指定の銀行口座に控除額が振り込まれる
近年はe-Taxといったインターネットで確定申告を完了させる方法もあるため、こういった方法を用いれば税務署に出向く手間も省くことができるでしょう。
e-Taxなどのオンライン申請の場合は、税務署(確定申告の用紙)で申請するよりも早く還付金が振り込まれるケースもあるため、早めに還付金を受け取りたい方や忙しい方はe-Taxでの申請をおすすめします。
確定申告に必要な書類について
確定申告時に必要となる書類は、以下の通りです。
- 源泉徴収票(会社に勤めていて給与所得がある方のみ)
- 確定申告の申請用紙(お住まいの地域の税務署・自治体の役所などに常備されている)
- 駆除にかかった費用の領収書
- 修繕工事にかかった費用の領収書(修繕工事をおこなった場合)
とくに業者依頼時に発生した際の領収書が絶対に必要となるため、きちんと残しておきましょう。
雑損控除申告はさかのぼって申告することもできる
雑損控除の申請は「還付申告」にあたり、確定申告の時期とは関係なく申請することが可能です。
「還付申告」とは、多く納税してしまった場合などに納めすぎた分を返還してもらうためのものであり、雑損控除のように思いもよらぬ自然災害or害虫・害獣などによる被害or盗難などの被害に遭い、家などの資産に損害を受けた場合に申告できます。
たとえば、2024年5月に害虫駆除を業者に依頼した場合、翌年から5年の間であればいつ申請しても問題はありません。
とはいえ、後回しにしておくと忘れてしまうこともあるため、できるだけ早めに申請しておくことをおすすめします。
条件次第では「災害減免法」などで所得税を軽減できる可能性もある
損失を被った場合、雑損控除以外にも「災害減免法による所得税の軽減免除」を利用することも可能です。
この制度は、通称「災害減免法」といい、所得条件を満たしていれば適用できます。
【災害減免法の適用条件】
- 災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上(損害金額は保険金などにより補填される金額を除く)
- 所得金額の合計額が1,000万円以下
- 災害による損失額について雑損控除の適用を受けない
上記の条件をすべて満たしていれば、所得税の軽減or免除が受けられます。
ただし、災害減免法と雑損控除は併用できないため、より節税できるほうを選択してください。
また、災害による損害を受けた場合は、自治体によっては住民税などの減免制度が適用されるケースもあります。
これは、納税免除または納税期限の猶予など税負担の軽減につながる制度のことであり、免除対象の税金には住民税以外にも個人事業税・固定資産税・事業所税といった、さまざまな地方税が含まれます。
減免制度の詳細は自治体によって異なるため、事前に確認しておくと安心といえるでしょう。
業者依頼時にかかる費用はいくら?

業者に駆除を依頼する際の費用は、状況によってまちまちです。
その理由は、害虫の種類・被害状況・対処する敷地の広さなどが、人によって変わるためです。
なかには、調査の結果「害虫ではなく害獣が棲みついていた」というケースもあり、実際にかかる費用は現地調査・見積もりを提示してもらわなくては正確にはわかりません。
業者によって、駆除にかかる費用やサービス内容は異なり、なかには現地調査や見積もり時点で費用が発生する可能性もあるため、事前のリサーチは必須といえるでしょう。
業者選別時のポイントは「相見積もりをとる(=複数の業者に見積もりを依頼する)」ことです。
相見積もりを取ることで業者それぞれの良し悪しを判断でき、より納得・安心できるところに依頼できるでしょう。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

申請する際の注意点について
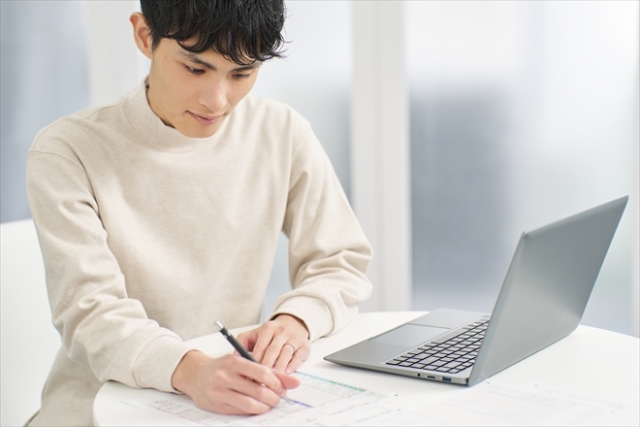
この章では、駆除にかかった費用を申請する際の注意点を解説します。
経費・雑損控除のどちらにも共通する内容のため、申請の際はしっかりと確認しておきましょう。
一部対象外となるケースもある
これは雑損控除の対象とする場合ですが、以下のように一部対象外となるものもあります。
- 「予防」にかかった費用
- 業者への依頼ではなく、自身で対処した際の費用
- 日常生活に必要のない資産の場合 など
害虫駆除を実施する場合は、対象となるかを事前にチェックしたうえで、必要となる対処を実施しましょう。
必要となる書類は大切に保管しておく
経費・雑損控除のどちらであっても、確定申告の際には必要となる書類を提出しなければ控除の対象にはなりません。
とくに、以下の書類は確定申告の申請時(念のため申請以後も)保管しておくことをおすすめします。
- 害虫駆除にかかった費用の領収書
- 物や家財などの修繕にかかった費用の領収書
- 業者に依頼した際の契約書 など
とくに「領収書」は確定申告時に必須となる書類のため、紛失しないよう大切に保管してください。
契約書はかならずしも必須ではないものの、場合によっては提出を求められるケースもあるため、念のため保管しておくことをおすすめします。
もし少しでも不備があれば控除の対象外となる可能性もあるため、必要書類の保管には十分な注意が必要といえるでしょう。
補助金を交付していないかを確認しておく
お住いの地域によっては、自治体が補助金などを交付しているケースがあります。
補助金の有無or金額は自治体によって異なり、基本的に害虫駆除に補助金を支給するケースは少ないものの、自治体によっては1万円など補助金を出している可能性もあるようです。
害虫駆除に関する費用を少しでも安く抑えたいという方は、経費や雑損控除だけでなく、補助金もうまく活用するとよいでしょう。
補助金の有無は自治体によって異なるため、詳細は事前にお住いの役所などに確認を取ってください。
あくまで「確定申告後に還付される」という点に要注意
経費にしろ雑損控除にしろ、あくまで「確定申告後(申請後)にかかった税金の一部が還付される」という点に注意が必要です。
確定申告は翌年(2024年であれば2025年)に実施されるため、業者に依頼する際は必要となる費用を全額支払わなくてはいけません。
決して「依頼時の費用が割引されるわけではない」という点を留意しておきましょう。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
害虫駆除にかかる費用は、事業者であれば経費に、個人であれば雑損控除の対象にできるケースがあります。
ただし、対象とするには一定の条件を必要とする(とくに雑損控除の場合)ため、事前の確認が必須といえるでしょう。
また、いずれも「確定申告時に申請をおこなう必要がある」「領収書など必要な書類を用意する必要がある」ため、申請をおこなうときまで必要な書類を大切に保管しておくことが重要です。
適切な申請をおこない、害虫駆除にかかる費用をできる限り削減しましょう。


コメント