不衛生なイメージのあるネズミが家に棲み着いて、ネズミによる寄生虫の被害に不安を感じていませんか。
確かにネズミの体表には、あらゆる寄生虫が付着しています。
家に侵入されてしまうと、ネズミを媒介あるいは中間宿主として健康被害に遭う可能性も否めません。
当記事では、ネズミが媒介する寄生虫による症状や寄生虫被害を予防する対策を解説します。
ネズミ被害と寄生虫被害のどちらにも遭わないよう、充分に対策を練りましょう。
1. ネズミが直接媒介する寄生虫の種類

人間がネズミから直接被害を受けるケースは少なくありません。
その被害のうちの1つが、寄生虫による皮膚炎や疾病です。
ネズミには、次の4つの寄生虫が付着している可能性があります。
- ノミ
- イエダニ
- ツツガムシ
- マダニ
それぞれの寄生虫の特徴や概要、起こり得る症状などについて詳しく紹介します。
1-1. ノミ
家で見かけるネズミ(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)には、ノミが寄生していることがあります。
跳躍力に優れた寄生虫で、1〜3mmとされる体長の200倍も跳ねるのが特徴です。
1〜3月の真冬を除いて年中発生し、特に7〜9月に多く発生します。
犬や猫などのペットの体に寄生して吸血するイメージがありますが、人間にも取り付いて吸血します。
ノミに刺されて起こる症状の一例を挙げてみましょう。
| 症状・病名 | |
|---|---|
| 皮膚疾患 | 激しいかゆみ、紅色丘疹、水ぶくれ、色素沈着、かさぶた |
| 媒介する感染症 | ペスト |
日本では1927年以降、ペストの発生事例はありません。
しかし、万が一にも罹患することのないよう、忌避剤などを使用してノミによる被害を最小限に留めるようにしましょう。
参考:日本感染症学会「腺ペスト・敗血症型ペスト」(https://www.kansensho.or.jp/ref/d41.html)
1-2. イエダニ
イエダニも家に侵入するネズミとともに、家の中へ入ってくることがあります。
イエダニはネズミの体だけでなく、ネズミの巣にも生息するのが特徴です。
5月頃から発生し始め、6〜9月頃にかけてピークを迎えます。
普段は宿主であるネズミを吸血して生きていますが、ネズミが巣を離れたり、ネズミが死亡したりすると、新たに吸血できる対象(寄生先)を探します。
イエダニによる被害は、かゆみや皮疹などです。
イエダニは人間の腹部や太ももを吸血する傾向にあるため、ネズミの侵入がありそうな状況下で腹部や太ももにかゆみや皮疹が見られた場合は、イエダニが原因かもしれません。
ダニ用の忌避剤は市販品でも多く販売されていますので、早めに対処しておきましょう。
1-3. ツツガムシ
ツツガムシは野山で見かけるネズミ、いわゆる野ネズミに付着する寄生虫です。
ダニの一種で、北海道・沖縄などの一部地域を除いた全国の野山や河川に生息しています。
発生のピークは春〜初夏、秋〜初冬で、ハイキングやキャンプといったレジャーの際に刺されるケースが多いです。
ツツガムシは、名を冠するツツガムシ病を引き起こすことがあります。
とはいえ、全てのツツガムシが病原体を持つわけではありません。
無害なツツガムシに刺された場合、発赤を生じてから数日後には跡がなくなります。
一方、病原体の「つつが虫病リケッチア」を持つ有毒なツツガムシに刺された場合、10〜14日ほど経過すると初期症状が現れます。
適切な治療が遅れ重症化してしまうと、命に関わるリスクが高まる病気です。
| 症状・病名 | |
|---|---|
| 初期症状 | 高熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、食欲不振 |
| 治療が遅れた場合 | 肺炎、脳炎 |
野山に出かけた後に上記のような初期症状が見られたら、お早めに医療機関へご相談してください。
参考:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト「つつが虫病」(https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/Scrub-Typhus/010/tsutsugamushi.html)
1-4. マダニ
マダニは野山で見かけるネズミに寄生しますが、身近な場所にも生息しています。
具体的には、庭・畑・公園・草地・河川敷などが生息地に該当します。
体長は3〜10mmと幅があるものの、肉眼で確認できるほどの大型のダニです。
3〜4月頃に増殖し始め、涼しくなった10〜11月に活動のピークを迎えます。
マダニはネズミを含むあらゆる動物に寄生して吸血しますが、その際に様々な感染症を媒介する恐れがあります。
中でも、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は特に問題視されている感染症です。
2013年、国内で初めてダニが媒介する重症熱性血小板減少症候群の症例が確認されました。
以降は西日本を中心に患者が報告されており、2025年には5月までに8件もの死亡事例が挙がっています。
マダニに刺されると、6〜14日で次のような症状が現れます。
- 発熱
- 吐き気・嘔吐
- 食欲不振
- 腹痛
- 下痢
症状に不安がありましたら、早急に医療機関を受診してください。
参考:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」(https://id-info.jihs.go.jp/diseases/sa/sfts/index.html)
福岡県庁「マダニによる人獣共通感染症に注意しましょう」https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kansen2013021501.html)
2. ネズミが間接的な媒介となる寄生虫
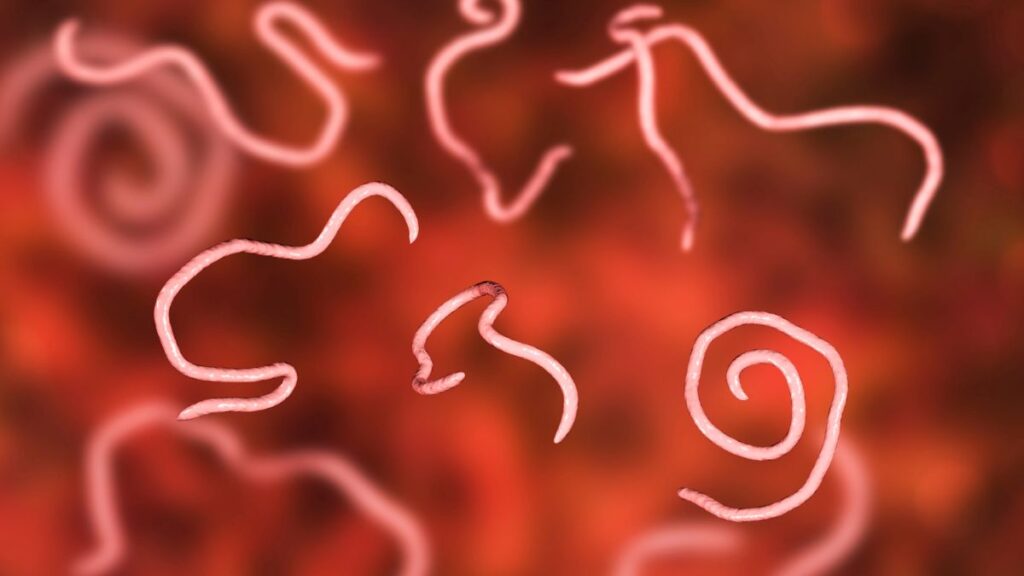
ネズミに寄生する寄生虫全てが、直接人間に害を与えるわけではありません。
寄生虫によっては、ネズミを中間宿主もしくは終宿主として人間に感染症をもたらします。
ネズミが間接的な媒介となる寄生虫は、以下の3つが代表的です。
- エキノコックス
- 広東住血線虫
- トキソプラズマ
各寄生虫による感染症の感染経路や症状などについて、詳しく解説します。
2-1. エキノコックス
エキノコックス症をもたらす寄生虫です。
動物が持つ寄生虫として広く知られており、野ネズミの体内にもエキノコックスが含まれている場合があります。
しかし、野ネズミから直接エキノコックス症に感染することはありません。
感染経路について、順を追って説明しましょう。
- 野ネズミがエキノコックスに寄生される
- エキノコックスに寄生された野ネズミを犬やキツネなどの動物が捕食する
- 動物がエキノコックスを含む排泄物を出す
- 排泄物内のエキノコックスによって汚染された山菜や水を人間が摂取して感染する
エキノコックスが人間の体内に侵入した場合、肝臓に寄生します。
感染しても数年〜十数年は無症状で、感染初期は肝機能も正常域です。
しかし、次第に肝腫大に伴う上腹部の膨満・不快感などの不定症状が現れ始めます。
さらに症状が進行すると、腹部症状の増強・発熱・黄疸などが現れ、末期には肺や脳に病巣が移転し命を脅かす恐れがあります。
自覚症状がある時点で病状が進行している可能性があるため、早めの受診が必要です。
なお、エキノコックスは成長段階によって寄生できる動物が以下のように決まっています。
中間宿主の体内にいる幼虫は成虫にならず、卵を作ることもないため、中間宿主同士での感染は起こりません。
- 幼虫が寄生する動物(中間宿主)…野ネズミ・豚・人など
- 成虫が寄生する動物(終宿主)…犬・キツネなど
参考:北海道立衛生研究所「エキノコックスについて」(https://www.iph.pref.hokkaido.jp/topics/echinococcus1/echinococcus1-1.html)
北海道「エキノコックス症について」(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/ekino1.html)
2-2. 広東住血線虫
広東住血線虫は体長22〜23mmの線虫で、クマネズミやドブネズミの肺動脈内に寄生します。
感染経路は以下の通りです。
- 成虫がネズミの肺動脈内に寄生する
- 肺動脈内で広東住血線虫が産卵し、孵化した幼虫は外界へ出る
- ナメクジ・カエル・淡水産のエビ・陸産のカニなどに経口的または経皮的に寄生する
- 寄生された動物そのものや動物の粘液、幼虫を経口摂取して感染
人間がナメクジやカエルなどを直接生で食べることは少ないですが、果物・野菜に付着していたナメクジの粘液を摂取したり、野菜についていた広東住血線虫を食べてしまったりすることは充分にあり得ます。
特に上記の4の段階で幼虫となっている広東住血線虫は非常に小さく、体長は0.45mmほどです。
無意識に摂取していることがあっても、不思議ではありません。
人体に移った広東住血線虫は、クモ膜下腔などに寄生します。
好酸球性髄膜脳炎を起こす場合があり、潜伏期間は約1~2週間です。
発症すると、激しい頭痛・発熱・知覚異常などの症状が現れます。
稀に失明や知的障害といった後遺症が残り、重症化すると命にかかわることもあります。
参考:愛知県衛生研究所「広東住血線虫」(https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/5f/kanton.html)
2-3. トキソプラズマ
トキソプラズマは、通常猫に寄生する寄生虫です。
猫から猫へ宿主を変えるために、ネズミを媒介とします。
ネズミがトキソプラズマに感染するのは、猫の糞便を食べたときです。
恐ろしいことに、トキソプラズマは次の猫へ寄生するためにネズミの脳へ影響を与え、猫に対する恐怖心を鈍らせてネズミが猫に捕食されやすくなるよう働きかけます。
感染したネズミを新たな猫が捕食すると、人間にも感染するリスクが高まるのです。
人間には、生肉や加熱不十分な肉を食べる・猫の糞便に直接触る・糞便に汚染された野菜を食べるなどの行為をきっかけに感染します。
感染しても無症状であることが多いですが、妊娠中の方が感染すると胎児に悪影響が及びかねません。
そして、恐怖心が鈍る・無気力になる・反射神経が鈍くなるなどの変化はトキソプラズマに感染した人間にも稀に見られます。
ご家庭に猫がいる場合は、猫がネズミを食べてしまわないよう注意しましょう。
参考:国立大学附置研究所・センター会議「宿主を支配する微生物 ヒトに蔓延する「顧みられない感染症」の実態に迫る」(http://shochou-kaigi.org/interview/interview_61/)
3. ネズミによる寄生虫被害を防ぐための対策

ネズミによる寄生虫被害は、いずれも深刻な事態になりかねません。
寄生虫被害を予防するためには、2つの対策が必要です。
- 屋外から寄生虫を持ち込まない
- 可能な限り早急にネズミを駆除する
それぞれの対策を具体的に説明します。
3-1. 屋外から寄生虫を持ち込まない
寄生虫被害に遭わないためには、寄生虫を室内に持ち込まないことが必須です。
人間だけでなくペットも寄生虫を持ち込む可能性がありますので、以下の措置を取りましょう。
- 野山に出かける際は露出を控え、長袖・長ズボンを着用する
- 野山から帰宅する際は玄関前で上着を脱ぎ、叩く・ガムテープを使うなどして寄生虫を落とす
- ペットと触れ合う・ペットを家に入れる際は寄生虫が付着していないか確認する
3-2. 可能な限り早急にネズミを駆除する
先述した寄生虫は、全てネズミを介して人間にも害をなす可能性があるものです。
したがって、ネズミを駆除することは、寄生虫被害を最小限に抑えるための非常に有効な手段と言えます。
また、ネズミは繁殖力が強いため、早めに駆除をすることでより寄生虫被害のリスクを低減できます。
ネズミ追い出し用スプレーや粘着シートなど簡易的な対策であれば、道具も比較的容易に入手でき、ご自身でも充分可能です。
また、ネズミの忌避剤として使用できるものに、ハーブ・木酢液・LEDライトがあります。
以下の記事でそれぞれ詳しくご紹介していますので、手軽にネズミ対策を始めたい方はご参考にしてください。
4. ネズミ被害でお悩みなら協会の無料相談窓口へ

ネズミ被害には、個人でも対策を取ることができます。
しかし、その対策は応急処置的なもので、ネズミが対策をくぐり抜けたり忌避剤に慣れたりして家への侵入を許してしまうケースも少なくありません。
加えて、ネズミの侵入口は初心者には確認しづらく、位置も多岐にわたります。
全ての侵入口を徹底的に封鎖しない限りは、ネズミが侵入し放題になってしまいます。
ネズミによる寄生虫被害を根絶するのであれば、まずはプロによるネズミの駆除が必要です。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会では、ネズミ被害に関する無料相談を行っています。
被害状況や駆除業者の選び方、費用を安く抑える方法など、どんなことでもご相談いただけます。
ネズミ駆除には、正確性と即時性が肝心です。
まずは一度、協会へのご相談をご検討ください。
まとめ
ネズミは、様々な寄生虫を媒介して人間に被害を及ぼすことがあります。
中には最悪の事態を招く感染症もあり、充分な注意が必要です。
ネズミの寄生虫被害を予防するには、寄生虫を持ち込まないこととネズミを早急に駆除することが求められます。
小さな寄生虫から大きな被害を生まないためにも、寄生虫への対策を確実に行いましょう。


コメント