昆虫は、その見た目や動きなどから苦手意識を持つ方も多いでしょう。
とくに人々の生活圏内に侵入し・人々や建物に悪影響をおよぼす「害虫」は、発見次第できるだけ早急に駆除をおこなう必要があります。
本記事では、害虫の種類と特徴、どんな被害をもたらすのか?などをご紹介します。
なかには、人間に恩恵を与えてくれる「益虫」なる存在もいるため、その違いを把握し、適切な対処ができるようになるとよいでしょう。
目次
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

「害虫」とは人々の生活に害をなす虫のこと

「害虫」とは、人間やペット・家畜・農作物・財産などにとって有害な作用をもたらす虫のことをいいます。
主に「無脊椎動物」(背骨・脊椎を持たない動物)、とくに昆虫類などの節足動物が代表的といえるでしょう。
人々の身近に存在する代表例としては「ゴキブリ」「ハチ」「ムカデ」「シロアリ」などがイメージしやすいでしょうか。
人が生活する建物に侵入・住処を作り、繁殖。害虫が増えるほど、人々の健康面や家屋への被害が甚大となっていく可能性が高いため、発見次第早急に駆除すべき存在です。
害虫の「種類」と「特徴」について

本章では、害虫の種類や特徴についてご紹介します。
害虫と一口にいってもその種類は多彩であるため、ここでは以下に大別して解説します。
- 食品害虫
- 衛生害虫
- 財産害虫
- 不快害虫
- 農業害虫
- 貯穀害虫
- 家畜害虫
それぞれで被害内容に大きな違いがあるため、その違いをしっかりと把握しておきましょう。
「食品害虫」
【該当する昆虫例】
- ゴキブリ
- ハエ
- カツオブシムシ
- ヒラタムシ
- チビタケナガシンクイ
- メイガ
- チャタテムシ
- トビムシ など
その名の通り、人が口にする「食料品」に被害をもたらす虫のことです。
穀物につく害虫だけでなく、加工品などさまざまな食料品につく虫も存在し、とくにゴキブリやハエなどは一般家庭でも目にする機会は多いでしょう。
一般家庭や田畑はもちろん、飲食店・食品工場・貯蔵倉庫などさまざまな場所で発生する可能性があります。
食品への異物混入の危険が高く・一度発生すると食品そのものを廃棄しなければならないケースがほとんどのため、見つけ次第早急に駆除するだけでなく、普段からの予防が大切といえるでしょう。
「衛生害虫」
【該当する昆虫例】
- 蚊
- ハエ
- ノミ
- ダニ
- 蜂
- ケムシ
- ムカデ
- ゴキブリ など
衛生害虫とは、人や家畜などに疾病など「衛生上の損害を与える虫」のことを指しています。
蚊・蜂・ダニ・ノミ・ムカデなどの毒や吸血などにより直接人間に害を与える虫もいれば、ハエやゴキブリのように菌・ウィルスなどの病原体を媒介とする虫などもいます。
放置しておくと健康面での被害が拡大してしまうため、普段からの侵入対策と発見時の駆除は徹底すべきといえるでしょう。
「財産害虫」
【該当する昆虫例】
- シロアリ
- フナクイムシ
- シバンムシ
- カツオブシムシ
- ヒメマルカツオブシムシ
- 紙魚(しみ) など
財産害虫とは、建築物や家財道具などの「財産」に該当するものに被害をもたらす虫のことです。
代表的なのは、家屋の木材を食べるシロアリでしょう。
放置するほどに建物に深刻な被害をもたらし、下手をすれば倒壊する危険性もあるため、早急な対処が求められます。
「不快害虫」
【該当する昆虫例】
- クモ
- ヤスデ
- ゲジ
- セミ
- カマドウマ
- ゴキブリ など
不快害虫は、その名の通り「人に不快感を与える害虫」のことを指しています。
たとえば「見た目が気持ち悪い」「悪臭を放つ」「鳴き声がうるさい」などが挙げられ、姿・形・行動などから心理的な不快感を感じさせます。
ただし、不快の基準は人それぞれであり「昆虫全般がダメ(見ただけで拒否反応が出る)」という方もいれば「別になんとも思わない」という人もいるため、不快害虫を定義するのは難しいといえます。
また、あくまで「不快感を与える」だけで、実質的な被害をもたらさない虫もいます。
とはいえ、繁殖するほどに不快感は増大するため、侵入対策や発見時の駆除は徹底すべき存在といえるでしょう。
「農業害虫」
【該当する昆虫例】
- バッタ
- イナゴ
- カメムシ
- アザミウマ
- ウンカ
- アブラムシ
- ハスモンヨトウ
- ハダニ など
農業害虫とは「農作物に対して食害をもたらす虫」や「菌・ウィルスなどを媒介として病気をもたらす虫」のことを指しています。
とくに、植物の病気には菌・ウィルスなどの感染性によるものが多く、その対策として殺虫剤などの農薬が使用されます。
農作物が対象となるため都市部などで被害をもたらすケースは少ないものの、農業を生業としている方からすると農業害虫の被害は見過ごすことができません。
「貯穀害虫」
【該当する昆虫例】
- コクゾウムシ
- ノシメマダラメイガ
- ノコギリヒラタムシ
- コクヌストモドキ
- チャイロコメノゴミムシダマシ
- シバンムシ など
貯穀害虫とは、貯蔵している穀物・穀物製品について食害を与える虫のことです。
たとえば、米などの穀物類、小麦粉などの製粉した粉製品などが挙げられます。
都市部で見かけるケースは少ないものの、地域によっては深刻な被害をもたらす可能性があるため、注意が必要です。
「家畜害虫」
【該当する昆虫例】
- ダニ
- アブ
- 蚊
- シラミ
- ハエ など
上記でご紹介した衛生害虫のなかでも、とくに「家畜」に被害をもたらす虫のことです。
吸血・病気の媒介といった直接的な被害だけでなく、害虫による家畜へのストレス被害といった問題も発生してしまいます。
こちらも対象となるのが「家畜」のため一般の方に影響をおよぼす可能性は低いものの、その手の職業に従事している方にとっては深刻な問題といえるでしょう。
家のなかに現れる害虫でとくに厄介な存在は?
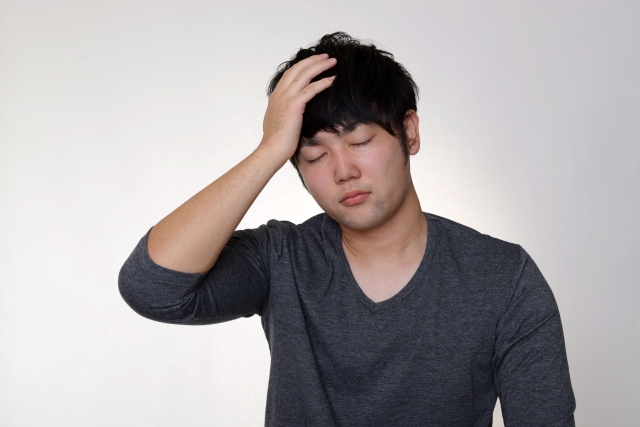
人々が住む家にも害虫は侵入・繁殖し、人々の生活を脅かします。
本章では、家のなかに現れるなかでも、とくに注意すべき害虫をいくつかご紹介します。
「衛生害虫」でとくに注意すべき害虫
衛生害虫のなかでとくに注意すべきは「ダニ」です。
「ダニはすべての家にいる」といっても過言ではなく、布団・カーペット・ソファなど家のあらゆる場所に生息しています。
家のなかに発生するダニは「チリダニ(ヒョウヒダニ)」「イエダニ」「ツメダニ」が主であり、なかには人に吸血するダニも存在します。
そもそもダニの体長は0.3mm~1mm程度のため肉眼で確認できず、放置しておくとアトピー性皮膚炎・喘息などのアレルギー性疾患の原因になる可能性があり注意が必要です。
また、普段から目にする機会が多い「ハエ」や「蚊」も、さまざまな病原菌や感染症を媒介する恐れがあります。
羽音が耳障りで不快感を与える原因にもなりかねないため、侵入させない対策をしておくべきでしょう。
もし、犬や猫などのペットと一緒にお住いの方は「ノミ」の存在にも注意しておきましょう。
ノミは、主に犬・猫などのペットに寄生し吸血しますが、寄生されると感染症を媒介される危険性もあります。
また、繁殖することで人間にも寄生し、吸血されると強い痒みを伴います。
市販されている薬剤・シャンプーなどを活用して対策するとよいでしょう。
「食品害虫」でとくに注意すべき害虫
食品害虫でとくに注意すべきは以下の4種類が挙げられます。
- 「コクゾウムシ」 :主に米びつなどに沸き、米を食べる(米食い虫とも呼ばれる)
- 「コナダニ」 :食品を保存している袋の隙間から侵入し、食品を劣化させる
- 「マメゾウムシ類」:畑や倉庫に保全されている豆と共に侵入し、豆類を食べて繁殖する
- 「シバンムシ類」 :ドア・窓・網戸の隙間などどこからでも侵入でき、乾麺・乾物・畳・本などを食べる(アリガタバチの宿主にもなる)
それぞれ侵入経路や食べる食材に違いがありますが、いずれも一度発生してしまうと食品そのものを廃棄しなければいけません。
そもそも「食品に虫が発生する」という時点で不快感を感じるため、食品害虫が発生しないよう対策を講じるべきといえるでしょう。
ホームセンターやネット通販などで対策グッズが多数販売されているため、それらを活用してみましょう。
「不快害虫」でとくに注意すべき害虫
不快害虫に関しては、不快を感じる基準が人それぞれで異なるため、定義するのは難しいといえます。
そのなかでも、とくに警戒しておくべき不快害虫としては以下が挙げられるでしょうか。
- 「カメムシ」:刺激を受ける・危険を察知するなどで、強烈な臭いを発する
- 「アリ」 :種類によっては毒針で刺したり・噛みつくことがある。また、群れを成して行動するため不快感を感じやすい
とくにカメムシは外からの侵入だけでなく、洗濯物などに付着して気づかぬ間に屋内に入り込んでいるケースもあります。
刺激を与えると悪臭を放つため、洗濯物を取り込む際は注意しておくべきといえるでしょう。
「財産害虫」でとくに注意すべき害虫
財産害虫のなかで、とくに警戒すべきは「シロアリ」です。
シロアリの特徴は「木材を食べること」であり、家に棲みつくと住まいの土台・柱などの木部を食べて、家の強度や寿命を著しく低下させます。
あまりに被害が深刻化してしまうと、倒壊の危険性もあるでしょう。
また、シロアリ自体が見つけづらいうえに繁殖力も高いため、気づいたときには建物への被害が深刻化して駆除・修繕費用が高額となってしまうケースもあります(シロアリは一つの巣に数万~数百万匹が生息するといわれている)。
シロアリが棲みつく兆候としては、以下が挙げられます。
- 「蟻道」(ぎどう)がある
- 羽アリを見たor羽が落ちている
- クロアリをよく見かける
- 床がきしむ・壁や柱から空洞音がする など
もしも上記のような兆候が見られたら、自身で対策を講じるか、駆除業者に相談して早急に対処すべきといえるでしょう。
ゴキブリは衛生・食品・不快害虫のすべての性質を持っている
ゴキブリは「衛生害虫」「食品害虫」「不快害虫」のすべての性質を兼ね備えており、もっとも警戒すべき害虫といえます。
侵入経路が多く、繁殖力もすさまじく、サルモネラ菌・赤痢菌・チフス菌・大腸菌などを媒介とするだけでなく、その見た目に嫌悪感を抱く方も大勢いるでしょう。
季節に関係なく(とくに夏場に多い)ふとしたときに目にするケースもあるため、常に対策を講じておくべき存在です。
「益虫」と呼ばれる昆虫も存在する

本章では、人々の生活に役立つ(益をもたらす)「益虫」についてご紹介します。
益虫の働きはさまざまであり、人間との関係性で判断も変わってきます。
なかには「益虫」であるものの「害虫」として嫌われてしまうケースもあるため、その違いを理解しておきましょう。
「益虫」とは?
益虫とは、人間の生活に役立つ(人になんらかの利益をもたらす)虫のことをいいます。
まさに害虫と対を成す意味をもっており、農業だけでなく、さまざまな業界から日常生活まで幅広く活躍しています。
代表的な益虫例を出すと、害虫を食べる「クモ」や「カマキリ」、植物の受粉やハチミツを生産する「ミツバチ」、絹糸を作る「カイコ」などが挙げられるでしょう。
益虫の代表例
上記でも少し例を挙げましたが、ここで益虫として知られる代表的な虫を掘り下げてみましょう。
とくに植物を栽培するうえで、害虫を捕食してくれる益虫の存在は重要です。
植物についている虫が益虫であれば、慌てて殺虫剤を散布する必要もなくなるため、覚えておいて損はありません。
【代表的な益虫】
- クモ :害虫を捕食する
- ゲジ :ゴキブリを捕食する
- テントウムシ:アブラムシを捕食する
- トンボ :さまざまな害虫を食べる肉食昆虫
- ゴミムシ :土や下草などに生息し、さまざまな害虫を捕食する(一部の種は食害をもたらすケースもある)
- ミツバチ :直物の花粉を媒介として受粉する。ハチミツを作る
- ミミズ :土のなかに生息し、有機物を食べる(良質な土壌を作るのに役立つ)
生活の場でよく目する「クモ」は不快害虫として扱われますが、ほとんどの種が人には無害であり、害虫を捕食する益虫として知られています。
ゲジ(通称ゲジゲジ)も人に害をなすことはほぼなく、むしろゴキブリの捕食者として有名です。
見た目から不快害虫として駆除の対象とされがちではありますが、ゲジゲジを駆除するとゴキブリなどの害虫が増える可能性もあるため、仮に家のなかで見つけた際は外へ逃がしてあげるくらいでいいかもしれません。
益虫と害虫は人によって立場が入れ替わることもある
クモやゲジのように「益虫であるものの、見た目などから害虫として扱われる」というケースがあります。
また、ムカデは害虫・害獣を食べるという「益虫」の側面と、見た目や噛みつかれた際に炎症を起こすという「害虫」の側面を持っています。
ミツバチやスズメバチも同様であり、農業においては「益虫」として有名ですが、人を刺す・家屋に巣を作るといった要素から一般人にとってはまぎれもない「害虫」です。
すなわち「益虫のすべてが、必ずしもすべての人に利益をもたらすわけではない」ということを理解しておくべきでしょう。
そもそも益虫か害虫かは人間の都合によって分類されたものであり、虫の存在そのものが「益」または「害」の性質を持っているわけではありません。
場面や見方を変えれば、人にとって益虫にも害虫にもなり得るのが「昆虫」といえます。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
虫は、その見た目から苦手とする方も多いでしょうし、なかには人々の生活に害をもたらす「害虫」も存在します。
その逆で、人々の生活に役立つ「益虫」も多く存在するため、もしも家のなかに虫がいたら、その虫の習性を理解することも大切といえるかもしれません。
虫は自身で駆除・予防ができますが、不慣れな方が完全に対処しきるのは至難の業です。
「害虫を駆除したい」「駆除すべきかどうか判断できない」という場合は、害虫駆除業者に相談してみるのもよいでしょう。


コメント