ゴキブリやハチなどの害虫の被害は増加傾向にあり、個人で駆除することが難しい場合は害虫駆除業者に依頼するケースも多くなっています。
もしも害虫駆除を生業とする場合、必須となる資格はあるのでしょうか。
この記事では、害虫駆除に必要な資格や、資格の種類・取得法についてご紹介します。
個人・企業を含め、害虫駆除を開業したいという方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

結論:害虫駆除に必須となる資格はない

結論からお伝えすると、害虫駆除には国家資格など公的な資格は(現時点では)なく、資格がなくても駆除できます。
また、資格がなくても害虫駆除業を開業することも可能です。
ただし、これは「害虫」に限った話であり、「害獣」を捕獲・駆除する場合には必須となる資格(+自治体の許可)が必要となります。
また、個人で駆除をおこなう場合はともかく、事業として害虫駆除をおこなうのであれば資格や実績など目に見える成果があるほうが依頼者側も安心して業者に相談できるでしょう。
そのため、必要性の有無に関わらず、資格は所有しておくに越したことはないといえます。
害虫駆除に役立つ資格とは?

害虫にもさまざまな種類が存在し、それぞれで被害内容や対処法、そして求められる資格が大きく異なります。
害虫駆除業者を営む場合はさまざまな害虫被害に対応できるようになるのが好ましいため、対象となる資格を取得しておいたほうがよいといえるでしょう。
本章では、害虫駆除に役立つ資格についてご紹介していきます。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
建築物の衛生的環境を確保するには、建築物の環境衛生上の維持管理をおこなう事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。
上記の観点から、建築物の環境衛生上の維持管理をおこなう事業者について、一定物的・人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることが可能という制度が設けられました。
登録を受けられる業種は、以下の通りです。
- 1号 建築物清掃業
- 2号 建築物空気環境測定業
- 3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 4号 建築物飲料水水質検査業
- 5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 6号 建築物排水管清掃業
- 7号 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 8号 建築物環境衛生総合管理業
これらの業種は、建築物の衛生的環境を確保するために重要な役割を果たしており、登録を受けることで事業者は適切な業務遂行が認められることとなります。
ただし、登録を受けない事業者が業務をおこなうことに対しての制限はありません。
登録は事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事がおこない、登録が完了すると、都道府県知事から建築物の衛生的環境を確保できる事業者と認められます。
なお、本登録の有効期間は6年であり、6年を超えて登録業者あることを示す(表示する)ためには、新たに登録を受けなければいけません。
厳密には「資格」ではなく「登録」ではありますが、登録することでより利用者に信頼感を与えることができるでしょう。
しろあり防除施工士
しろあり防除施工士とは、公益社団法人日本しろあり対策協会が定めているシロアリ防除施工に関する日本で唯一の資格です。
受験資格は「しろあり防除講習会を受講+所定の実務経験年数を満たしていること」であり、認定試験(筆記試験)ではシロアリの生態・木材・腐朽・防除薬剤・防除処理・建築といった、シロアリ防除施工を実施するうえでの知識が問われます。
受験場所は東京・大阪・埼玉・福岡・沖縄であり、試験は毎年の3月上旬ごろにおこなわれます。
また、受験料として15,000円。さらに別途受講料と登録料が必要です。
例年の合格率は70%ほどで、勉強する必要こそあるものの、取得が困難な資格ではないといえます。
シロアリ駆除は資格がなくてもおこなえますが、利用者への信頼感や業務の幅・スキルが広がるという点で、事業として携わる場合は取得しておくべき資格といえるでしょう。
ペストコントロール技術者
ペストコントロール技術者とは、ペストコントロール(有害生物の防除)をおこなうための技術を有する者に与えられる資格です。
資格には「1級~3級」+「名誉技術者」という4つの種類があります。
資格を取得するには、日本ペストコントロール協会が主催する養成講座を受ける必要があります。
養成講座の修了後、協会に申請することでペストコントロール技術者として承認されます。
受講料は、1級:137,600円・2級:85,300円・3級:61,300円(すべて税込)です。
本資格も害虫駆除の仕事をおこなううえで必須というわけではありませんが、資格を取得することで、専門性の向上はもちろんお客様からの信頼を獲得するといったメリットが得られるでしょう。
有害生物防除の基本的な資格となるため、害虫駆除を生業とする方は取得しておくことをおすすめします。
防除作業監督者(国家資格)
防除作業監督者は、建築物のねずみ・昆虫など防除作業の監督をおこなえる国家資格であり、防除業の登録に必要です。
「防除」とは、害虫・害獣・害鳥による被害を防ぐことを目的とした「予防」「駆除」などをおこなうことを指しています。
本資格の資格取得を通じて、薬剤の扱い方や駆除の方法など、害虫駆除を実施するうえでの専門的な知識を学ぶことが可能です。
資格保有者数・合格率は公表されていませんが、試験は講習をきちんと聞いていれば受かる内容(出題範囲は講義で解説される)といわれており、座学や実技など5日間の講義をしっかりと受講していれば問題なく合格できるでしょう。
ただし、2~5年の実務経験を必要とするため、誰でもすぐに取得できる資格ではありません。
企業で実務を積んだ後、独立開業する際などに取得を検討するとよいでしょう。
【講習の概要】
- 実施元:公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター
- 日程:5日間(32時間)
- 費用:60,000円(非課税、受講申込時には不要)
- 講習科目:建築物環境衛生制度、殺そ殺虫剤、作業と安全管理、ねずみ昆虫等防除各論、実技(デモンストレーション)、考査
- 試験時間:90分
建築物環境衛生管理技術者(国家資格)
建築物環境衛生管理技術者とは、建築物の「環境衛生の維持管理」に関する国家資格のことです。
「ビル管」「ビル管理技術者」「ビル管理士」「環境衛生技術者」と呼ばれることもあります。
ビルの管理と害虫駆除になんの関係が?と思う方もいるかもしれませんが、本資格では一般的な衛生管理だけでなく、害虫・ねずみ防除といった害虫駆除についても深い知識と技術を持つことが求められます。
面積3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)の特定建築物において選任義務があり、とくに衛生管理が重要視される施設での害虫駆除業務において、大きな信頼を得ることができるでしょう。
この資格を取得するには、環境衛生学や微生物学などの科目を含む試験に合格しなければいけません(一部の科目では実務経験が試験の受験資格となっている)。
【試験の概要】
- 試験日程:年1回(10月頃)
- 試験方法:学科試験
- 受験資格:実務経験2年以上
- 受験料 :13,900円
- 受験場所:札幌市・仙台市・東京都・名古屋市・大阪市・福岡市
毒物劇物取扱責任者(国家資格)
毒物劇物取扱責任者とは、農薬や化学薬品などの毒物・劇物の扱いに関する国家資格であり、毒物を製造する際には本資格を取得しなければいけません。
害虫駆除をおこなうにあたって、害虫を処理するための特殊な薬剤を散布することがあります。
お客様やスタッフ・近隣の住民などに健康被害が出ないよう、扱いには十分な注意が必要です。
企業に勤めているとき(特別な薬剤を使うとき)はもちろん、独立開業した際にも特別な薬剤を使うケースがあるため、害虫・害獣駆除の仕事に携わる場合は取得しておくことをおすすめします。
本資格を取得するためには、筆記試験と実地試験を受ける必要があります。
【筆記試験】
- 毒物および劇物に関する法規
- 基礎化学
- 毒物および劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法
【実地試験】
- 毒物と劇物の識別や取扱方法(実際に毒物・劇物を扱うわけではなく、筆記試験と同様にマークシート形式でおこなわれる)
なお、試験には「一般」「農業用品目」「特定品目」の3種類があり、それぞれで責任者になれる業態が変わります。
「一般」であれば、毒物・劇物の全品目を扱えるようになるため、長く活用できる汎用性の高い資格を取りたい方は「一般」の合格を目指すと、より幅広い業務に対応できるようになるでしょう。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

害虫駆除を生業とする方は資格取得を目指そう!
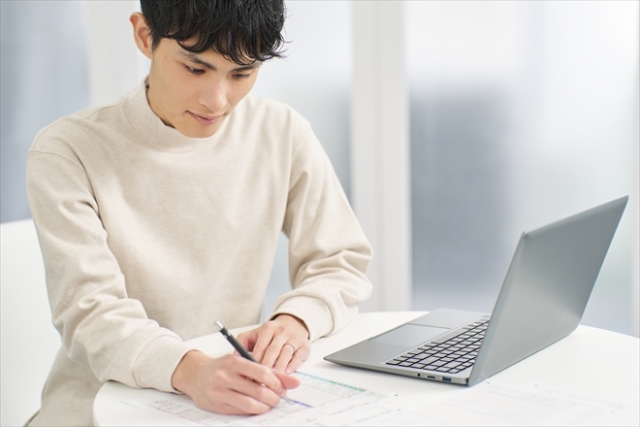
「害虫」と一言でいっても、その種類は多岐に渡り、被害内容や駆除方法はそれぞれで異なります。
ときには、現地調査や実際に駆除をおこなう際に予期せぬ事態が発生する恐れもあるでしょう。
害虫は資格がなくても駆除できるとはいうものの、素人が安易に手を出すべきではありません。
また、業者に依頼するお客様の側としても、資格保有者が多い・実績が多いといった熟練のプロがいる業者を選定し依頼することでしょう。
お客様の信頼を得ること・自身のスキルアップや将来的な部分も含め「仕事として害虫駆除を実施したい」と考える方は、ぜひ関連する資格を取得してみることをおすすめします。
害獣駆除に必須となる資格について

害虫を駆除する際に必須となる資格は今のところありませんが、害獣を捕獲・駆除する場合は資格を取得したうえで自治体に捕獲・駆除の申請をおこなわなくてはいけません。
業者のなかには害虫・害獣どちらの駆除にも対応しているところが多いため、本記事内にて害獣駆除に必要となる資格についても解説しておきましょう。
害獣駆除には「狩猟免許」が必要となる
害獣を捕獲・駆除する場合は「狩猟免許」を必要とし、免許を取得したうえで自治体に許可を得るための申請をしなければいけません。
狩猟免許は、以下4つの種類が存在します。
- 網猟免許
- わな猟免許
- 第一種銃猟免許
- 第二種銃猟免許
捕獲をする場合は「わな猟免許」があれば対応可能ですが、わな猟免許しか保有していない場合は、駆除はもちろん生きたまま運搬することができません。
駆除をおこなう場合は「銃猟免許」が必要であり、第一種・第二種でそれぞれ扱える猟銃が異なります。
ただし、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミといった環境衛生に重大な悪影響をおよぼす恐れのある鳥獣については、狩猟免許がなくても駆除することは可能です。
いずれにせよ、害獣を捕獲・駆除する場合は相応の知識とスキルを必要とするため、リスクを避けるためにも素人は不用意に対処すべきではないといえるでしょう。
狩猟免許の取得方法
狩猟免許の試験は、種類ごとに毎年複数回実施されており、取得までの流れは以下の通りです。
- 都道府県の担当部署に「狩猟免許申請書」を提出する
- 狩猟免許申請手数料を支払う(1免許あたり5,200円)
- 希望者のみ「狩猟免許予備講習会」を受講する
- 「狩猟免許試験」を受ける
申請先や必要となる書類は自治体によって異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。
試験は「知識試験」「適性試験」「技能試験」の3分野がおこなわれ、知識試験・技能試験は70%以上、適性試験は全項目の基準を満たすことで合格となります。
試験の合格率は80~90%ほどのため、きちんと勉強しておけば合格できる確率は高いといえるでしょう。
なお、狩猟免許の有効期限は約3年間であり、更新の際はお住まいの都道府県で実施される講習会を受講+適性検査に合格する必要があります。
更新時に、1免許あたり2,900円の手数料が発生することも把握しておきましょう。
害獣の駆除に資格が必要な理由
野生動物は「鳥獣保護管理法」という法律によって管理されており、資格や許可なく捕獲・駆除することが禁止されています。
仮にどれだけ被害に遭っていても無許可で駆除ができず、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が発生するため、注意しておきましょう。
これは、個人だけでなく企業であっても同様です。
害獣駆除時に役立つ他の資格について
狩猟免許は必須として、その他にも事業者として害獣駆除サービスをおこなう際に役立つ資格がいくつかあります。
一つは害虫の項目でもご紹介した「防除作業監督者」です。
防除作業の監督をおこなえる国家資格であり、防除業の登録の際に必要とします。
もう一つは、日本で深刻な問題となっている人と野生鳥獣の問題を地域で指導できるようになる「鳥獣管理士」という資格です。
1級・準1級・2級・3級という4つの区分があり、鳥獣管理士養成講座やJWMS認定プログラムを受講+筆記試験に合格することで取得できます。
(受験料は、新規:27,000円、昇級:12,000円)
また、銃を使って害獣を駆除する場合は、狩猟免許に加え「鉄砲所持許可」も取得しておかなくてはいけません。
鉄砲所持許可がないと銃を使った害獣駆除ができないため、銃猟免許を取得(銃を使用する)予定の方は確実に取得しておきましょう。
害虫・害獣の資格を取得しておくメリットとは?

害虫・害獣ともに、人々の生活圏に侵入し、さまざまな被害をもたらしています。
被害は増加傾向にある+素人では対処しきれないということもあって、専門業者に駆除を依頼する方も多いでしょう。
建物に潜む生き物は種類が非常に多く、ときには「調査の結果、害獣だけでなく害虫も巣を作り繁殖していた」というケースも少なくありません。
一方にしか対応できない場合、別の業者に依頼しなおす必要があるため、利用者側は害虫・害獣の両方に対応できる業者を選ぶ可能性が高いといえます。
そのため、害虫・害獣駆除を事業とする場合、双方に対応できるスタッフを育成するのが好ましいでしょう。
害虫・害獣駆除のニーズは拡大しているため、該当する資格を取得し、業務の幅を広げていくことをおすすめします。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
害虫を駆除するために、現時点では必須となる資格はありません。
しかし、害虫の特性上、素人がむやみに手を出すべきではありませんし、業者に依頼する場合も資格保有者や実績が豊富なところを選ぶ可能性は高いといえます。
資格を取得しておけば、お客様への信頼を得ることができ、さらに自身のスキルアップにも役立てることができるでしょう。
対応できる幅を広げるためにも、害虫だけでなく害獣に関連する資格も取得することをおすすめします。


コメント