害獣は、人々の生活になんらかの悪影響をおよぼす動物のことあり、放置するほどに被害が広がるため、早急な防除を必要とします。
しかし、害獣の多くは鳥獣保護法によって許可なく捕獲・殺傷ができないため、基本的には害獣駆除業者に駆除を依頼することとなるでしょう。
害獣駆除業者に依頼した場合、その費用はどれほどのものになるのでしょうか?
この記事では、害獣駆除にかかる費用(害獣ごとの相場)や、駆除費用を抑えつつもより良い業者を選ぶ方法についてご紹介します。
プロに駆除を依頼するのは決して安い買い物とはいえませんが、害獣の被害に悩まされずに安心して日々の生活を送るには、プロの助力は欠かせません。
ポイントを押さえ、より良い業者を選定できるよう調査を進めてみましょう。
目次
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

害獣駆除を業者に依頼する際の費用について

害獣の駆除は、資格や申請などを必要とすることから、一般の方であれば害獣駆除業者に依頼するケースが多いでしょう。
本章にて、業者に依頼した場合にかかる駆除費用をご紹介します。
害獣の種類と駆除費用の相場
害獣にもさまざまな種類が存在し、その種類によって駆除にかかる費用は変化します。
たとえば、家屋に棲みつきやすい害獣とその費用相場は以下の通りです。
【害獣駆除の費用相場一例】
- ネズミ :20万円~50万円
- イタチ :25万円~50万円
- タヌキ :25万円~50万円
- ハクビシン:25万円~50万円
- アライグマ:25万円~50万円
- コウモリ :30万円~50万円
あくまで相場であり、人によって被害状況などは変化するため、詳細は業者に見積もりを取ってもらわないと判明しないでしょう。
また、最低価格の相場が1万円~となっている害獣もいるものの、1・2万円ほどで駆除できることはそうはありません。
あくまで1万円程度でできるのは簡易的な応急処置のみです。
状況にもよりますが、基本的には20万円~50万円ほどかかるケースが多く、ある程度まとまった費用を用意しておく必要があると認識しておきましょう。
駆除費用にバラつきがある理由
駆除費用にバラつきがある理由は、人によって建物の広さや被害状況が大きく異なるからです。
- 坪面積
- 害獣の種類
- 被害状況
- 作業の難易度
- 侵入経度の封鎖の必要性 など
もし建物にまで大きな被害がおよんでいると、建物の修繕費用もかかってくるでしょう。
被害が軽微であるほど費用は安くなりますし、被害が甚大であるほど費用は高額になります。
「駆除費用を抑え、害獣の被害に悩まされることなく過ごしたい」という方は、できるだけ早めに業者に相談することをおすすめします。
料金を左右する要素とは?
害獣駆除を業者に依頼する際に、特に料金の変動幅が大きいものとして以下が挙げられます。
- 害獣の種類・数
- 作業する場所の広さ・築年数
- 被害状況
各ポイントを順に解説していきましょう。
害獣の種類・数
害獣は、その種類によって特徴が異なり、それぞれで適切な対処を実行しなければ効果的な駆除ができないため、害獣の種類によって費用は異なります。
また、ネズミを除くほとんどの害獣は鳥獣保護法によって無許可で捕獲・殺傷ができないため、自治体に許可申請を取ったうえで狩猟免許を保有したスタッフが対応をすることになります。
許可を得るための作業量が増えるだけでなく、有資格者が対応するとなれば費用も高くなる可能性があるでしょう。
加えて、対象の数が多いほど作業時間も長くなるため、その分料金も高くなりやすいといえます。
害獣は繁殖力が高いため、放置するほどその数は増加していきます。
なかには「複数の害獣・害虫が棲みついていた…」という可能性もあり、そうなるとより作業時間が長くなり、駆除費用も高額となってしまうでしょう。
作業する場所の広さ・築年数
作業する場所の面積=害獣の住処・行動範囲が広いほど、作業に必要な人数が増えるため料金が高くなりやすいといえます。
一般的な戸建てであればそこまで料金に差がないケースも多いようですが、60坪以上ともなれば費用が大きく跳ね上がる可能性もあるでしょう。
また、築年数が経っている建物ほど、経年劣化などにより侵入経路が多くなる可能性が高く、作業範囲と数が増加する=費用がかさむケースもあります。
建物の劣化は普段生活しているなかで気づきにくいため、適度に建物の劣化状況を確認し、必要に応じて修繕を(依頼)するのもよいでしょう。
被害状況
害獣被害の度合いが進んでいるほど、料金は高くなる傾向にあります。
特に多いのは、糞尿による被害です。
害獣の多くは溜め糞をする(同じ箇所に糞尿をする)傾向があり、棲みついている期間が長いほど糞尿はたまり続けます。
その糞尿に害虫や菌が寄り付く可能性があること、糞用により天井にシミができたり建物の建材部分が劣化することなどから、駆除をおこなった後は徹底的な清掃と消毒が必要となります。
清掃・消毒に時間がかかる(対応箇所が広い)ほど、その分だけ人員や薬剤の量を増やす必要があるため、費用が高くなりがちです。
また、建物の劣化が進んでいる場合は、修繕費用も別途必要となるでしょう。
害獣駆除の料金に含まれる作業内容について

業者依頼時の害獣駆除費用には、以下の作業が含まれているのが一般的です。
- 現地調査・見積もり
- 駆除作業
- 再発防止作業
- 清掃・消毒作業
各詳細を順に解説していきましょう。
現地調査・見積もり
業者に駆除をお願いする際は、本契約に入るまえに現地調査→見積もりという順に作業がおこなわれます。
この理由は、「害獣の種類や建物の被害状況を確認しないと正確な見積もりを出すことができないから」です。
現地調査・見積もりは無料で実施してくれる業者も多いため、無料で対応してくれる業者をいくつかピックアップして作業をお願いしましょう。
また、見積もりの段階で予算を伝えておけば、予算内でできる駆除方法を提案してくれることもあります。
なお、業者のなかには、現地調査をせず(渋り)にいきなり見積もりから入ろうというところもあるようですが、こういった業者は候補から外したほうがよいといえるでしょう。
現地調査・見積もりを丁寧におこなってくれる業者を候補に残すべきともいえます。
- 現地調査にて細やかな部分まで丁寧にチェックしてくれる
- 現場の写真や動画を見せながら、詳細を説明してくれる
- 見積もり内容を丁寧に解説してくれる
- こちらの質問に丁寧に答えてくれる
こういった業者のほうが、後のトラブルに発展するケースが少なく、安心して駆除をお願いできるでしょう。
駆除作業
見積もり内容を承諾し本契約に入ったあとは、現地調査の内容をもとに害獣の種類に合った駆除作業を実施します。
害獣駆除の作業には忌避剤や捕獲機などが利用されますが、こういった道具もそれぞれで料金が異なります。
見積もり時点で害獣の種類・被害状況を踏まえて作業内容が決定されるため、もし希望があれば見積もり時点で伝えておくとよいでしょう。
また、業者のなかには「見積もり時点では安い金額を提示しておき、後になって追加費用を請求してくる」というケースもあります。
そのため、安さだけを強調してくる業者・契約を急かしてくる業者は、基本的に候補から外すことをおすすめします。
ときには実際の作業に入ってから新たな作業箇所が見つかるケースもありますが、事前に「追加作業が発生した際の費用はどうなるのか?」を確認しておくことが重要です。
再発防止作業
家屋に潜む害獣を駆除できても、侵入経路が開いたままでは、いずれ被害が再発する恐れがあります。
そのため、再発防止作業も害獣駆除をおこなううえで重要な工程の一つといえます。
基本的には、害獣の侵入口となる穴や隙間を塞ぐ作業をおこなうこととなるでしょう。
害獣・害虫の侵入経路は豊富かつ小さな隙間からでも侵入してくるため、不慣れな方が対処するのは至難の業です。
侵入経路の封鎖は害獣・害虫に精通したプロに徹底対策してもらうのがよいでしょう。
清掃・消毒作業
害獣が棲みついていた場所・移動経路には、糞尿や害獣のエサとなる生き物の死骸などが残されています。
また、不衛生な害獣にはさまざまな病原菌や寄生虫が付着しているため、放置しておけば住人の健康被害や建物の劣化といった被害が発生するでしょう。
そのため、(再発防止の観点も含め)害獣がいた箇所は徹底的に清掃・消毒がおこなわれます。
清掃や消毒は、細かなところまで丁寧かつ徹底的におこなってくれる業者を選びましょう。
駆除費用を抑える方法と注意点について

害獣駆除は数万円~数十万円と高額な費用がかかるため、できるだけ費用を抑えたいと考える方は多いでしょう。
ただし、「ただ費用が安ければよい」というわけではないため、費用を抑えるには一工夫が必要です。
この章では、害獣駆除費用を抑える方法と注意点についてご紹介します。
駆除費用を抑える方法
駆除費用を抑える方法としては、主に以下が挙げられます。
- 相見積もりを取る
- できるだけ早めに業者へ相談する
- 自治体に相談する
各詳細を順に解説していきましょう。
相見積もりを取ること
業者選びにおいてもっとも重要なことは、「相見積もりを取る=複数の業者に見積もりを依頼する」ことです。
仮に一社からしか見積もりを取らなければ、費用が適正か?サービスの質はよいか?などが比較できず、後になってもっと条件のよい業者を知って後悔することになるかもしれません。
業者選びの流れは、主に以下のように進めていきます。
- インターネットや他者からの口コミなどでいくつかの業者をピックアップする
- 業者のホームページなどを確認し、そのなかから3~4社ほどに絞り込む
- 絞り込んだ業者に現地調査・見積もりを依頼し、比較する(良し悪しを判断する)
- もっとも信頼できると判断した業者に、駆除を依頼する
業者のなかには悪徳業者の類も存在するため、業者選びは特に注意しなければいけないポイントといえるでしょう。
できるだけ早めに業者へ相談する
害獣や害虫の被害は、瞬く間に広がります。
「害獣が家屋内にいる=害獣が棲みついている=すでに被害が進行している」と判断できるため、この時点で素人ができることはあまりないと考えておきましょう。
放置するほど被害は拡大し、かつ被害が大きくなるほど駆除費用が割高になっていくため、速やかに業者に相談することをおすすめします。
また、害獣は夜間など人を避けて行動することが多いため、自分でも気づかぬ間に害獣の被害が進行している可能性もあります。
被害を未然に防ぐためにも、適度に業者へ現地調査をお願いしてみるのもよいでしょう。
自治体に相談する
地域によっては、自治体が害獣駆除をサポートしてくれることもあるため、業者より先に自治体へ相談してみるのもよいでしょう。
ただし、以下の点には注意しておきましょう。
- 自治体によってサポート内容は異なる(対応していないケースもある)
- 自治体が直接害獣を駆除してくれるわけではない
- 家屋に潜む害獣に対して、補助金が出ることはほぼない など
基本的には、害獣駆除業者の斡旋が主となるでしょう。
また、害獣の捕獲ができる「わな猟免許」(狩猟免許の一種)を取得し、申請が承諾された場合は、捕獲機を貸し出してくれるケースもあります。
一部の自治体では害獣駆除に補助金が出る可能性もありますが、家屋に潜む害獣に対して補助金が適用されるケースはほぼありません。
念のため事前の確認をしておくに越したことはありませんが、あまりアテにはしないほうがよいでしょう。
いずれにせよ、一般の方が害獣駆除を依頼する機会は早々ないため、「どうやって駆除を依頼すればいいのか?どの業者を選べばいいのか?がわからない」という方は多いはずです。
自治体に相談すれば、この問題をある程度解消できる可能性があるため、お住いの地域の自治体が相談可能であれば積極的に活用してみましょう。
業者選考時の注意点
業者選考時の注意点としては、主に以下が挙げられます。
- 安さだけに捕らわれない
- ネットの情報を鵜呑みにしない
- 自分で無理に対処しない
こちらも、各詳細を順に解説していきましょう。
安さだけに捕らわれない
なかには、非常に低価格で害獣駆除をしていることをウリにする業者が存在します。
結論からいうと、安さだけをウリにする業者は悪徳業者であることが多いため、依頼しないほうがよいでしょう。
- 後から追加費用を請求される
- サービスの質が悪く、被害が収まらない(すぐに再発する)
- 保証がなく、被害再発時はまた高額な駆除費用を支払わなければいけない など
大切なのは、費用とサービス内容が釣り合っているか?です。
悪徳業者の場合、(他の業者と比較されると困るため)契約を急かしてくることが多いといえます。
もしも契約を急かされた場合も、絶対にその場で契約せず、他の業者にも相談することをおすすめします。
業者選考時は、費用だけでなく駆除内容や保証内容などもしっかりと確認し、総合的に納得できるところを選びましょう。
ネットの情報を鵜呑みにしない
特にインターネットの情報は鵜呑みにしないことをおすすめします。
その理由は、「業者の公式ホームページはメリットしか記載されていないことが多い」「ランキングサイトは1位の業者がインターネット広告会社などに依頼し作成してもらっているケースが多い」ためです。
口コミも同様で、特にネット上の口コミは「本当にその業者に依頼した人が書いた情報かどうか」も定かではありません。
ただし、インターネットの情報が業者を知るキッカケとなること、業者側も自社を知ってもらう宣伝のためにサイトを作成しているだけであることから、ネットの情報がまったくアテにならないというわけでもありません。
情報はあくまで参考程度にとどめておき、後は実際に現地調査・見積もりを依頼して業者の良し悪しを自身で確認してみるとよいでしょう。
自分で無理に対処しない
害獣の捕獲・殺傷は法律によって管理されているため、自己判断で勝手に駆除してはいけません。
また、棲みついている害獣を無理に追い出そうとすると怪我や感染症など病気のリスクも発生する恐れがありますし、侵入経路を封鎖するのも難しいため、素人が無理に対処しないほうがよいといえるでしょう。
下手をすれば、被害が悪化し、より駆除・修繕費用が高くなってしまう可能性もあります。
素人ができる基本的なことは、害獣に浸入されないよう対策することです(忌避剤や柵の設置など)。
害獣が侵入・棲みついている場合は、あらゆる手間やリスクを考えた場合、経験豊富なプロの業者に依頼するのがもっとも妥当な策と考えられます。
害獣駆除の費用は経費や雑損控除の対象となるのか?
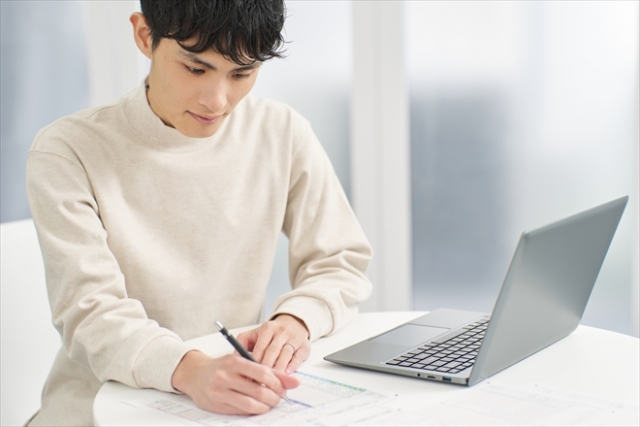
害獣駆除にかかる費用は高額なため、できるだけ費用を節約したいと考える方も多いでしょう。
害獣駆除を業者に依頼した際の費用は、確定申告時に経費や雑損控除として申請することで、所得税の控除を受けられる可能性があります。
本章にて、害獣駆除の費用を経費や雑損控除とする方法についてご紹介します。
事業者は「経費」として計上できる
たとえば、飲食店など店舗を経営されている方や農業を営んでいる方などは、害獣駆除にかかった費用を経費となる可能性があります。
勘定科目としては、主に以下が挙げられます。
- 資産維持費
- 修繕費
- 外注清掃費
- 衛生費 など
また、害獣の駆除は定期的におこなう必要もあるため、その場合は「害獣駆除費」のような形で個別に勘定科目を作るのもよいでしょう。
節税に役立てることができるため、購入・利用時に受け取った領収書は、大切に保管し適切に申請しましょう。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

住居としている建物の場合は「雑損控除」として申請できる
害獣もしくは害虫による修繕・駆除にかかった費用は、所得税法施行令第9条に規定する「害虫その他の生物による異常な災害」に該当するため、雑損控除の対象となります。
控除を受けるためには「被害を受けて駆除をおこなった事実」と「駆除にかかった費用」を明確にする必要があるため、業者に駆除を依頼した際の領収書などの書類は、大切に保管しておきましょう。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 「予防」のためにかかった費用は控除の対象とならない
- 事業用の資産や別荘といった、生活に必要な資産以外(住宅・家具・衣類など)の被害は控除の対象にならない
また、雑損控除の対象になるには、一定の条件を必要とします。
これらの詳細については「国税庁の雑損控除について」を参考にしてみてください。
まとめ
害獣駆除は、素人が自己判断でおこなうことができず、対策することも難しい分野です。
被害の拡大スピードが早く・かつ被害が大きくなるほど駆除にかかる費用も高額になるため、害獣の存在や痕跡を発見したら、できるだけ早めに害獣駆除業者に相談することをおすすめします。
業者によって費用やサービス内容・質が異なるため、複数の業者を比較して、より自身が納得できるところに依頼するとよいでしょう。


コメント