天井裏や屋根のすき間から「ドブのようなニオイがする」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか?実はその原因が、家屋に住み着いたコウモリのフンであるケースは少なくありません。
コウモリは夜行性で帰巣本能が強く、一度住み着くと追い払っても戻ってくる習性があります。しかもフンや尿は独特のアンモニア臭を放ち、健康被害や建物の劣化にも直結します。
本記事では、コウモリのニオイの原因について詳しく解説します。コウモリを追い払う対策、コウモリによるニオイ以外の被害、プロに任せるべきタイミングまで分かりやすく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

1. コウモリのフンによるニオイ被害

コウモリによる被害の中でも、もっとも身近で深刻なのがフンや尿によるニオイです。強烈なアンモニア臭や下水のような悪臭は生活空間にまで広がり、日常生活がかなり過ごしにくくなります。
ここでは、コウモリのフンがもたらす具体的なニオイ被害について詳しく解説します。
1-1. アンモニア臭・ドブのようなニオイがする
コウモリのフンや尿が溜まると、強烈なアンモニア臭を放ちます。人によっては下水のようなドブ臭や、カビ臭さを感じる場合もあります。天井裏や換気口から漏れたニオイが部屋全体に広がり、不快感だけでなく体調不良を引き起こすケースも珍しくありません。
特に梅雨や夏場は湿気でニオイが強まり、小さな体のコウモリでも、群れで生活すると大量の排泄物を残すため、わずかな期間で強烈なニオイ環境になってしまいます。
1-2. コウモリの排泄頻度は非常に多い
コウモリは体が小さい分、食事と排泄を頻繁に繰り返します。1匹でも毎日数十粒ものフンを排出するとされ、フンが積み重なることでニオイはさらに強烈になり、床材や断熱材に染み込んでしまいます。
そのため、フンの掃除を行ってもニオイの根本的な解決には至らない場合が多いです。尿やフンの成分が建材に浸透すると、表面を拭き取るだけではニオイが残り続けてしまいます。結果的に、換気や消臭剤では改善しきれず、専門的な対策が必要になります。
参考:国土交通省 国土技術政策総合研究所「コウモリ類調査を実施するための基礎知識」
2. コウモリが嫌がるニオイ

コウモリは特定のニオイを嫌うため、ニオイを利用した追い出しは効果的です。市販品や身近なもので対策できるため、個人で手軽に試すことができます。
ここでは、代表的な「コウモリが嫌がるニオイ」を紹介します。
2-1. ハッカ
コウモリは嗅覚が鋭く、特に刺激の強いニオイを嫌います。そのため、ハーブの一種であるハッカの香りを利用すると、住み着いたコウモリを遠ざけることが可能です。
ハッカ特有の清涼感のある香りは、メンソールという成分によって生じています。このメンソールはミントにも含まれているため、ミントの香りを活用することでもコウモリ対策が可能です。
使用する際は、スプレーにして散布したり、綿に染み込ませて天井裏に置くと、コウモリが嫌がって近寄りにくくなります。ただし、使用量や濃度を誤ると人間にとっても刺激が強すぎる場合があるため、容量を守って活用しましょう。
2-2. ナフタレン
ナフタレンとは、石炭を蒸留・精製する過程で得られる白色または無色の結晶状の物質です。用途は幅広く、染料や香料、医薬品の原料、防虫剤などに利用されています。
コウモリはナフタレン特有の強いニオイを嫌うため、忌避剤として使われることがあります。ただし、ナフタレンは人体に有害な可能性があるため、安全面に不安がある場合は、利用を控えましょう。
ハッカ、ナフタレン以外にもコウモリが嫌がるニオイ「木酢液」を活用した対策については、以下の記事で詳しく解説しています。
3. コウモリのフンがもたらすニオイ以外の被害

コウモリの被害は、ニオイだけにとどまりません。コウモリのフンや尿には、健康被害や建物の劣化を引き起こす要素が含まれており、放置すれば深刻な二次被害に繋がります。
ここでは、コウモリのフンがもたらすニオイ以外の被害について解説します。
3-1. 病原体による感染症のリスク
コウモリのフンには細菌や真菌が含まれており、感染症を引き起こす恐れがあります。代表的なのは「ヒストプラズマ症」で、肺に炎症を起こす危険性があり、免疫力の低い人や子どもは特に感染リスクが高いです。
また、コウモリは狂犬病ウイルスを保持している動物としても知られています。海外ではコウモリによる咬傷や唾液を介した感染が報告されており、世界的にみてもリスクがある動物です。
病原体による感染症のリスクを避けるためには、コウモリに直接触れたり、素手でフンを片づけたりすることは絶対に避けましょう。
参考:厚生労働省検疫所「感染症情報」
CDC「Human Rabies from Exposure to a Vampire Bat in Mexico」
3-2. ダニやノミの発生
コウモリの体には寄生虫がついていることがあり、住み着いた場所にはダニやノミが繁殖することがあります。これらが室内に入り込むと、かゆみやアレルギー反応を引き起こす可能性が高いです。
特にコウモリが天井裏に棲みついた場合、ダニやノミが換気口やすき間から室内に入り込みます。見えない場所で発生するため気づきにくく、被害が広がってから発覚するケースが多いため注意が必要です。
3-3. 家屋へのダメージ
コウモリのフンや尿は酸性度が高く、建材を腐食させる要因になるため、木材が黒ずんだり、断熱材が劣化したりといった家屋へのダメージに繋がります。
家屋への被害は見えない部分で進行するため、気付いた時には修繕が必要な状態になっていることも少なくありません。また、湿気や汚れが溜まるとカビが繁殖しやすくなり、家の寿命や室内環境にも悪影響を与えます。
コウモリによる被害については、以下の記事でも詳しく解説しています。
4. コウモリ駆除はプロに任せるのがオススメな理由
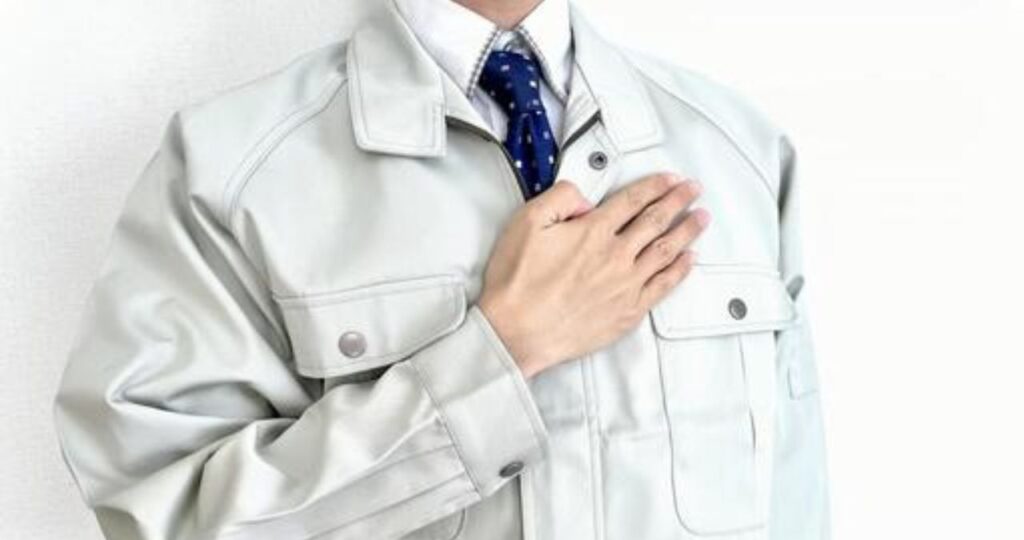
コウモリ被害を根本から解決するには、自己判断での対処では限界があるのが現状です。法律の規制や作業の危険性、再侵入を防ぐための専門的な施工など、個人では対応が難しい要素が多いためです。
ここからは、プロに任せるべき具体的な理由を解説します。
4-1. 鳥獣保護管理法を遵守する必要がある
コウモリは鳥獣保護管理法で守られている野生動物です。許可なく捕獲したり殺傷したりすることは法律で禁止されており、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
適切な手順を踏まずに駆除すると、思わぬトラブルに発展しかねません。そのため、個人で判断せずに、法律を理解したうえで安全に駆除できる専門業者に依頼するのがもっとも安心です。
鳥獣保護管理法については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
参考:e-GOV法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
4-2. 帰巣本能が強く追い出しても戻ってくる
コウモリは帰巣本能が非常に強い生き物で、一度追い出しても、侵入口を塞がなければ必ず戻ってきます。そのため、根本的な解決には侵入経路の封鎖が必須です。市販の忌避剤や音による撃退だけでは、一時的な効果しか得られません。
封鎖作業をしない場合、フンや尿による強烈なニオイが再び蓄積し、ニオイ被害を繰り返します。そのため、コウモリ駆除には、追い出しと同時に侵入口を完全に閉じる作業が必要となります。
4-3. 高所や閉所の施工が難しい
封鎖すべきコウモリの侵入口は、屋根裏・換気口・壁のすき間など高所や閉所に集中しています。素人が脚立や工具を使って施工を行うのは難易度が高く、転落やケガのリスクがあり危険です。さらに隙間は数センチ程度と非常に細かく、完全に封鎖するには専門的な技術が必要です。
その点、専門業者は専用の足場や器具を使用して安全に施工を行い、防護服やマスクを着用し、衛生管理もしっかり行います。そのため、封鎖作業を含めたコウモリ駆除はプロに依頼するのがもっとも安心です。
5. コウモリ被害でお悩みなら協会の無料相談をご活用ください

「コウモリに噛まれてしまい、感染症が心配で不安に感じている」など、コウモリ被害にお困りの方は、ぜひ「日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」の無料相談をご活用ください。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会は、コウモリをはじめとした鳥類・害獣による家屋被害に対し、安全で安心な生活環境を守るための防除・管理を専門とする団体です。
経験豊富な担当者が状況を聞き、効果的な対策のアドバイスや専門業者探しをお手伝いします。「こんな相談をしてもいいのだろうか?」と迷うような内容でも、もちろん大丈夫です。ぜひお気軽にご相談ください。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
コウモリのフンや尿は強烈なニオイを放ち、日常の快適さを奪ってしまいます。さらに感染症リスクやダニ・ノミの発生、建物の劣化といった二次被害にも繋がりかねません。
コウモリが嫌がるニオイを活用した対策で一時的に追い払える場合もありますが、帰巣本能の強さから根本的な解決には至らないのが現状です。また、法律の制約や作業の危険性を考えると、プロの業者に依頼するのがもっとも安全で確実です。
日本有害鳥獣駆除・防除管理協会では、無料相談を行っているため、コウモリの被害でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。


コメント