記事紹介
私たちにとって最も身近な害獣「ネズミ」
ネズミはその小さな体を武器に、他の害獣とは一線を画す適応力をみせ、人間社会のいたるところに蔓延っています。
生ゴミや残飯をエサとし、不衛生の象徴であるそんなネズミが、もし自宅に現れたとしたら貴方はどうしますか?
恐らく多くの方にとって、専門業者への依頼料は決して安くないものでしょう。
今回はそんな方に向けて、業者に頼らない自力でのネズミ駆除が可能なのか、また、その際の注意点や問題点はなんなのか徹底解説したいと思います!

ネズミの駆除を業者に依頼すると、どれくらいの金額になるのかしら?
ネットで調べてみたけどイマイチ分からないから、いっそのこと自力で駆除したいわ!
旦那も手伝ってくれるみたいだし大丈夫よね…?
目次
ネズミがもたらす実害

ネズミは人間の生活空間に溶け込み、人間と共生しつつも私たちに様々な実害をもたらす害獣です。
ネズミがもたらす害獣被害は、大きく分けて以下の4つに分類できます。
農作物や食料品の食害
ネズミは雑食性の動物であり、穀物や野菜、果物、種子などの農作物や、米やパン、チーズなど幅広い食料品を食べます。
人間の食べるものは殆ど全てネズミのエサにもなり、当然食害による農作物の収穫量の減少や品質の低下、食品の汚染などの経済的な損失を引き起こします。
こうした食害の影響は農業や畜産業、食品加工業、流通業、小売業など多種多様な業種にまで及び、例えば日本では、ネズミによる農作物の食害が年間約1000億円の損失に相当する害を生んでいると推定されています。
また、ネズミによる食品の汚染は、食品安全や消費者の信頼にも悪影響を及ぼします。
建物や家具、電気配線などへの噛み付き
ネズミには生涯に渡って歯が伸び続ける特性があり、その伸びすぎた歯を削るためにさまざまな物を噛む習性を持っています。
そうしたネズミの噛み付きは、建物や家具、電気配線、本や衣類などの物品の破損や機能不全を引き起こし、とりわけ電気配線の噛み損ないは、火災や感電などの重大な事故にまで発展することがあります。
噛み付き被害はネズミが棲みつき得る、住宅や公共施設、工場や倉庫といった建物全般に被害を与え、日本における噛み付きによる被害は、年間約2000億円の損失に相当する被害を生み出していると推定されています。
さらに、ネズミによる電気配線への噛み付きによって、最大で年間約1000件の火災が引き起こされているとも推定されているのです。
病原体の媒介や排泄物による衛生上の問題
不衛生な環境で生活するネズミは、多くの病原体を保有し、ダニなどによる媒介や咬傷、排泄物や尿への接触を通して人間に衛生被害を与える可能性があります。
ネズミが媒介する病気には、ペストやラットバイト熱、ハンタウイルス出血熱、サルモネラ食中毒、リプトスピラ症などがありますが、これらの病気はいずれも発熱や頭痛、吐き気、下痢、出血、敗血症などの重篤な症状を引き起こす深刻なものです。
また、ネズミの排泄物や尿は、アレルギーや喘息などの呼吸器系の疾患を悪化させることもあります。
ネズミの排泄物や尿は日本全体で年間約100万トン排出されているとされており、また、ネズミが原因となる病気の発生は、年間約1000件にものぼると推定されています。
心理的な不快感や恐怖感
多くの人々にとってネズミは不快感と伴う存在であり、ネズミの外見や挙動、臭いなどが心理的なストレスや恐怖感を人間に与えます。
ネズミに対するこうした心理的な不快感・恐怖感は人間の精神や感情に深刻な影響を与え、睡眠障害や不安障害などの精神疾患の原因になるケースもあるほどです。
その一方で、日本におけるネズミに対して不快感や恐怖感を持つ人の割合は約80%にものぼると推定されており、決して無視できない社会問題だと言えるでしょう。

私のウチでもスナック菓子とか食パンがネズミに食べられてたのよ!
それ以降、ネズミが口をつけたかも…って考えちゃて、家にある食材を食べたくなくなちゃったわ。
特にあの尻尾が気持ち悪くて、想像すると鳥肌が立つくらいゾッとするわ。
駆除に役立つグッズ
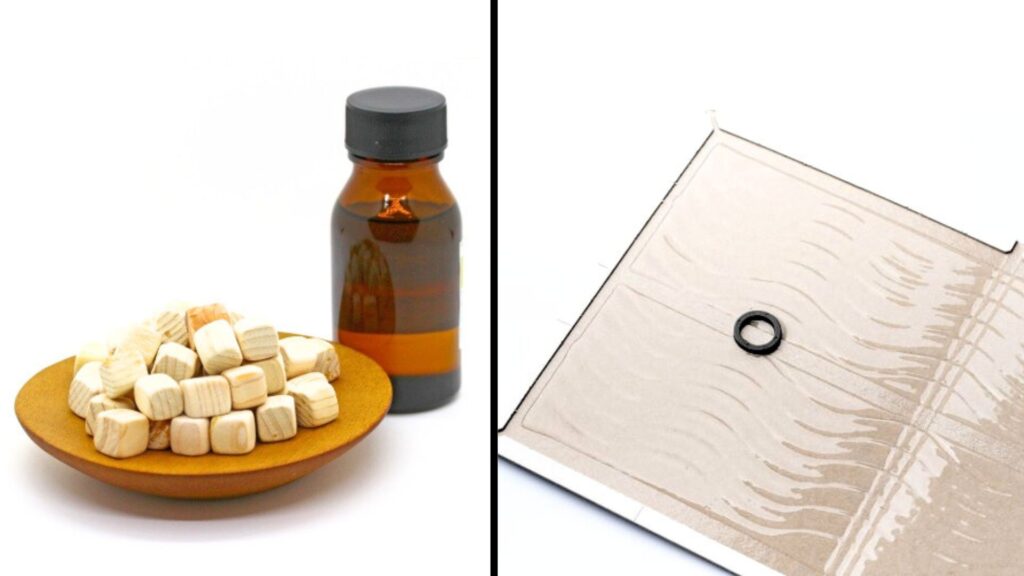
前項で解説したような被害を回避するためには、当然ネズミの侵入を防ぐための防鼠や、ネズミの駆除を行うための殺鼠などの対策が必要になります。
滅多に人前に姿を見せないネズミを効率的に防鼠・駆除するためには、適した対策グッズを駆使しなければなりません。
メジャーな害獣であるネズミに特化した対策グッズは様々な種類のもの市販されていますが、一般的に以下の5つのグッズを使用するのが良いでしょう。
- 粘着シート
- 捕獲器
- 毒餌
- 忌避剤
- 金網やパテ
これらの対策グッズはホームセンターやネット通販などで手に入れることができます。
それでは、次にグッズの詳しい特徴や使用方法を説明していきます。
粘着シート
粘着シートはその名の通りシートの上に粘着質の素材が塗布されており、シートの上を通ったネズミの胴体や四肢にくっついて動きを封じるという仕組みのグッズです。
粘着シートのメリットとしてはネズミの種類や大きさに関係なく使用でき、また、毒物を使わないのでペットや子供にも安全な点が挙げられます。
使用方法
粘着シートを使うときのポイントは、以下の通りになります。
- ネズミの通り道や出入り口となる場所を狙って粘着シートを設置すること。
警戒心の強いネズミは粘着シートを避ける場合もあるので、迂回経路が無い状態を作り出す事が重要です。 - 粘着シートの上に、ネズミが好むエサを置くこと。
ネズミは胃袋が小さいにもかかわらず、一日に体重の約10分の1から4分の1程度のエサを必要とする生き物のため、長くても4日〜5日で餓死してしまいます。
そのため、絶えずエサを探しているネズミを粘着シートに誘導するのであれば、シートの上にエサとなるチーズやナッツ、ドライフルーツ置いておくと捕獲確率を上げられるでしょう。 - 粘着シートを設置したら、定期的に確認すること。
ネズミが粘着シートに捕まった場合、エサにありつけず上で説明したように数日で餓死することになります。
その状態で放置されれば当然ネズミの死骸は腐敗してしまうため、目につきにくい場所に設置した粘着シートもこまめに確認し、死骸があれば早めに処理するようにしましょう。
捕獲器
捕獲器は粘着シートと同様にネズミを生きたまま捕まえることができる対策グッズです。
捕獲器にはカゴタイプや箱タイプなどがありますが、いずれも捕獲器の中にエサを仕掛けておき、ネズミが入ると扉が閉まり、捕獲できるという仕組みです。
粘着シートと比較して、何度も繰り返し使えて経済的である点が捕獲機のメリットになります。
使用方法
捕獲器を使うときのポイントは、以下のとおりです。
- 捕獲器の中には、ネズミが好むエサを置くこと。
粘着シートと同様に、エサにはチーズやナッツ、ドライフルーツなどを使用するのがオススメです。
なお、エサは捕獲器の奥に置いて、ネズミが奥まで入るように誘導できるようにしましょう。 - 捕獲器を設置する場所は、ネズミの通り道や出入り口に沿って壁に沿って置くこと。
ネズミは壁沿いを移動する習性があるので、壁に沿って置くことでネズミが捕獲器に入る確率が高まります。 - 捕獲器を設置したら、定期的に確認すること。
こちらも粘着シートと同様に、捕まったネズミを早めに処分する必要があります。
ネズミはストレスで死んでしまったり、脱走したりすることがあるので注意しましょう。
毒エサ
毒エサは、毒入りのエサを食べさせてネズミを駆除するための対策グッズです。
毒エサには粒状やブロック状のものがあり、ネズミの数を減らす効果が高いものの、取り扱いにはやはり注意が必要です。
使用方法
毒餌を使うときのポイントは、以下のとおりです。
- 毒エサは、ペットや子供に触れないようにすること。
毒エサは人間や他の動物にとっても有害なものなので、誤って子供やペットが食べてしまわないよう安全に十分配慮することが重要です。
また、毒餌を置く際には手袋やマスクなどを着用してください。 - ネズミが死んだ場所を特定できるようにすること。
毒エサを食べて壁の中や天井裏などの人の目の届かない場所で死んでしまったネズミの死骸が腐敗して、悪臭や虫の発生といった被害が起こる可能性があります。
毒エサの設置自体は簡単ですが、死骸の回収も含めて自己完結できるかどうか熟慮してください。 - ネズミの種類に合った製品を選ぶこと。
ネズミには、ドブネズミやクマネズミなどの大型の種類と、ハツカネズミやハツカダイコクネズミなどの小型の種類があります。
大型のネズミはエサを一度にたくさん食べることができるので、即効性の高い毒エサが効果的な一方、小型のネズミはエサを少しずつ食べることが多いので、持続性の高い毒エサが効果的です。
毒餌のパッケージには対象のネズミの種類や成分が記載されているので、そちらを確認してから購入しましょう。
忌避剤
忌避剤はネズミが嫌う匂いを発して、ネズミを追い出したり、侵入を防止したりするための対策グッズです。
忌避剤には固体状のものやゲル状のもの、スプレータイプのものなどが存在し、いずれも対象動物を殺さないので、死骸の処理や動物愛護といった点で優れています。
また、ハッカなどの匂いがするものの基本的に人間やペットにも無害なので安心できます。
使用方法
忌避剤を使うときのポイントは、以下のとおりです。
- 忌避剤は屋内と外を繋ぐ出入り口となる場所に、集中的に散布すること。
忌避剤の効果は時間とともに弱まるので、定期的に交換・散布しなければなりません。
また、忌避剤の種類によっては水や湿気に弱い製品も存在するので注意してください。 - 忌避剤はネズミの種類や個体差によっては、効果がない可能性があること。
ネズミが忌避剤に慣れてしまうと、期待した効果を発揮しない場合があります。
より効果的にネズミの防鼠・駆除するために、今回ご紹介した他の対策グッズも併用しましょう。
金網やパテ
金網やパテは、ネズミの侵入経路となる箇所を塞ぐことでネズミの侵入を防ぐためのグッズです。
配管や基礎の通気口、外壁に空いた穴などを塞いでしまえば、ネズミの侵入を高い確率で阻止できる一方、すでにネズミが家の中にいる場合は、逆にネズミを閉じ込めてしまうこともあるので注意が必要です。
金網やパテを使うときのポイントは、以下のとおりです。
- ネズミの出入り口を完全に塞ぐこと。
ネズミは思いもよらない小さな隙間からも侵入できるので、隙間無くしっかりと金網を固定、パテを塗布することが重要です。
また、侵入経路を塞ぐ前に忌避剤や捕獲シートを使って、家屋の中にいるネズミを一掃しておく必要があります。 - ネズミの出入り口を特定すること。
ネズミの侵入経路となる箇所は基礎の通気口、下水管、外壁や床の穴、エアコンのホースなど…多岐に渡ります。
侵入経路を特定するために、以下のようなポイントを確認しましょう。
- ネズミの毛や糞が付着している
- ネズミがかじった跡がある
- ネズミの匂いがする
- ネズミの足音や鳴き声が聞こえる
これらの条件が当てはまったら家屋の内外を繋ぐ出入り口となっている可能性が高いです。

ネズミを捕まえても、その後の処理に困るわね…。
でも殺しちゃうのも心が痛むし、家のどこかで死んでたらもっと嫌よ。
市販の対策グッズを使ったら気軽に駆除できると思ってたけど、そうもいかないみたいね。
ネズミ駆除のステップ

被害の内容と対策グッズについて理解できたところで、次にネズミ駆除の具体的な手順を見ていきましょう。
1.ネズミの種類や数を把握する
ネズミの種類や数によって、必要なグッズや効果的な駆除方法は異なるので、まずは、これらの情報を特定しなければなりません。
ネズミの種類や数を把握するために、以下のようなポイントを確認しましょう。
ネズミの毛や糞を観察する
ネズミの毛や糞はネズミの種類を特定する目安になります。
それぞれの毛や糞の特徴は、具体的に次のようになります。
- ドブネズミ:毛は黒や茶色で、長さは約2cm。糞は細長くて先が尖っており、長さは約1.5cm。
- クマネズミ:毛は灰色や黒で、長さは約1.5cm。糞は細長くて先が丸く、長さは約1cm。
- ハツカネズミ:毛は白や灰色で、長さは約1cm。糞は粒状で、直径は約2mm。
- ハツカダイコクネズミ:毛は黒や茶色で、長さは約1cm。糞は粒状で、直径は約3mm。
罠やカメラを設置する
ネズミの種類を確認する最も直接的な手段として、罠やカメラを使用する方法もあります。
粘着シートや捕獲機でネズミを捕まえたり、監視カメラを使用する事で、ネズミの種類と大まかな数を確認することができます。
罠やカメラはネズミの通り道や出入り口になる場所に設置しましょう。
2.ネズミの駆除に必要なグッズを準備する
把握できた種類や数に合わせて、駆除に必要なグッズを選びましょう。
その際には、前述したグッズの特徴や使い方を参考にしてください。
3.ネズミの駆除を行う
グッズを設置したら、いよいよネズミの駆除を実行します。
駆除というと、一度にネズミを一網打尽にするイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしらませんが、専門外の方が自力で行う場合、時間をかけて少しずつネズミの数を減らしていく他ありません。
駆除の際に気を付けるべき点は以下のようになります。
ネズミの巣や隠れ家を探して処分する
ネズミは巣や隠れ家を作ることで、安全に繁殖することができます。
なので、駆除をより確実に行うためにも巣や隠れ家を探して処分し、確実に個体数を減らしていきましょう。
巣や隠れ家があるメジャーな場所としては、壁の中や天井裏、家具の下や裏、押入れやクローゼットなどが挙げられます。
こうした場所に毛や糞、噛みつき跡などが見られば、ネズミが潜んでいる可能性大です。
巣や隠れ場所を見つけたら、手袋やマスクを着用して熱湯や消毒液で処理しましょう。
ネズミの対策グッズを定期的に確認・交換する
ネズミの対策グッズは多くの場合時間とともに効果が低下します。
また、ネズミが捕まったり、毒エサを食べて死んだ場合は早めに処理しなければ、ネズミの死骸や体液が感染症の原因になったり、ネズミが逃げ出したりする可能性があります。
ですので、対策グッズを仕掛けた場所やネズミな隠れ家となっている場所を定期的に確認しましょう。
4.ネズミ駆除の後始末
害獣の駆除には後始末の必要で、面倒ですが決して欠かすことができません。
駆除・捕獲したネズミを処分する
駆除・捕獲したネズミは当然何かしらの形で処分しなければなりません。
すでにネズミが死んでいる場合は、死骸を新聞紙などで包んだ上で燃えるゴミとして概ね処分できますが、実際の取り扱いについてはお住まいの自治体のルールに従うようにしましょう。
また、ネズミが生きている場合は、ネズミは鳥獣の保護を目的とした動物愛護法の対象外であるため、原則として殺すことが無難です。保健所も基本的に死んだ状態のネズミのみを引き取ります。
しかし、血の通った生命の殺生に躊躇いがある心優しい方であれば、自然豊かな公園などに生きたまま放つという選択肢もあります。
ただし、近くに住宅街がある場合、放ったネズミが別の家屋で害獣被害を引き起こすリスクも考えられるので、ネズミを逃す場所については熟慮して決定してください。
いずれにせよ、ネズミを処分する際には手袋やマスクを着用し、ビニール袋や容器に入れるなどして、衛生管理を徹底するよう意識しましょう。
ネズミの被害に遭った場所を清掃する
ネズミが生活していた場所には、多かれ少なかれネズミの毛や糞尿などが撒き散らかされています。
これを放置すれば建物の損傷に繋がるほか、感染症やアレルギーの原因にもなってしまうので、駆除後にはしっかりと清掃する必要があるのです。
清掃の際には手袋やマスクを着用した上で、消毒液や熱湯を使って洗浄しましょう。
また、ネズミにかじられた配線や水道管などは修理や交換すると良いでしょう。
5.ネズミの再発防止を行う
ネズミ駆除に一度成功したとしても、家屋置かれた状況が変わらなければ同じような被害が再発してしまいます。
再発を防ぐためには、下記のようなネズミが繁殖する条件を無くして行かなければなりません。
ネズミの侵入経路を塞ぐ
ネズミは、小さな隙間や穴から建物内部に侵入してきます。
建物内部でネズミが繁殖したということは、こうした侵入経路が少なからず存在する証拠なので、隙間や穴を見つけて塞がなければなりません。
隙間や穴を塞ぐには、コンクリートやモルタル、金属板やワイヤーメッシュなどの硬い素材を使うのが効果的です。
床下や天井裏、キッチンの下などを隈なくチェックしてみましょう。
ネズミのエサや水を取り除く
ネズミの行動範囲はさほど広くはないので、巣の周辺に必ずエサの供給源が存在するはずです。
そのため、食べ物や水は密閉容器に入れて保管し、食べ残しやゴミはすぐに処理するよう心がけてください。
特に、米やパンなどの穀物類や果物などの甘いものは、ネズミの好物なので注意が必要です。
環境を清潔に保つ
ネズミは汚れたり乱雑に散らかった環境に寄り付くため、環境を常に清潔に保つことが重要です。
生活雑貨や衣服は整理整頓し、草や木、ゴミなどのネズミの隠れ場所になるものは適切に処分しましょう。
特に、床下や屋根裏などのネズミが巣を作りやすい場所は定期的に点検するのが望ましいです。
以上が、自力でネズミ駆除を行う方法です。
ネズミ駆除には様々な対策グッズや手順がありますが、それぞれの特徴や使い方を理解して効果的に行うことが重要です。

1匹2匹駆除するだけなら簡単かもしれないけど、巣を丸ごと駆除するには手間がかかりそうね…。
ネズミがどこから侵入したかなんて見当もつかないし、侵入経路を塞ぐなんて私や旦那にもできないかも…。
業者に依頼するメリット
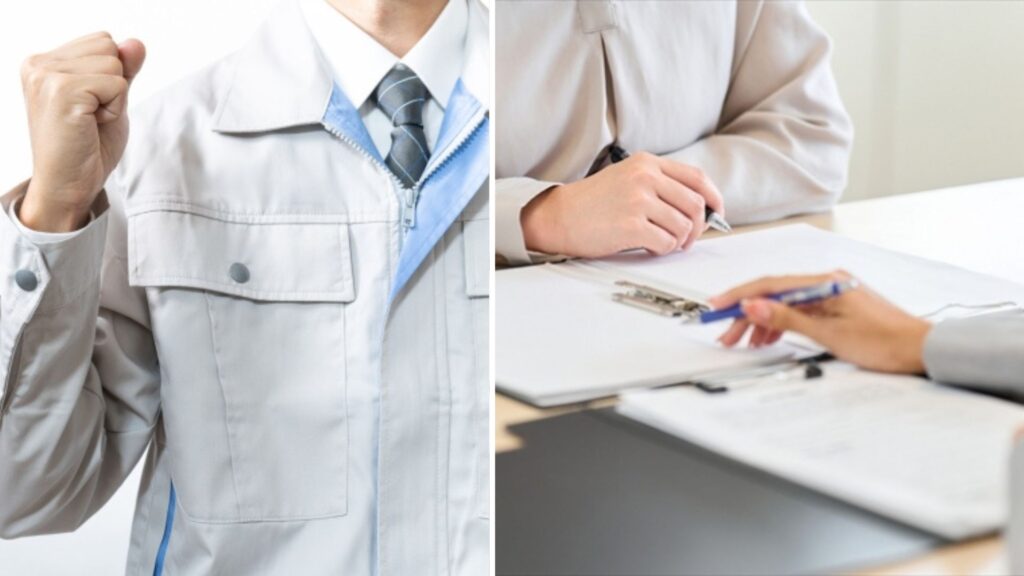
ここまでは、市販のグッズを使って自力でネズミを駆除するための方法や手順をご紹介しましたが、ネズミは繁殖力が強く、一度繁殖してしまえば一筋縄では駆除できない害獣です。
ネズミ駆除を専門業者に依頼するメリット
自力で駆除したいと考えている方に、改めて専門業者に依頼するメリットを知ってもらうため、この項ではネズミ駆除の専門業者の強みや費用相場について解説します。
専門知識や技術を持っている
ネズミ駆除業者は培われた経験によってネズミの生態や習性を熟知しており、侵入経路や巣の位置を特定することに長けています。
また、効果的な駆除方法や市販されていない薬剤を使用し、効率的に駆除を完遂することもできます。
専門家でない方が自力で駆除する場合、毒エサや罠の設置が不完全だったり、ネズミの死骸や糞の処理に難儀したりしますが、専門業者に任せればそういった心配がありません。
再発防止の対策をしてくれる
ネズミ駆除業者はネズミを駆除するだけでなく、同時に再発防止のための対策もしてくれます。
ネズミが侵入した穴や隙間を塞いだ上で、適切な忌避剤の使い方やネズミが寄り付きにくい環境を作るためのアドバイスを提供してくれるので、自分の知識に自信が無い方にオススメです。
また、アフターサービスとして定期的な点検や保証期間内の無料駆除などを保証している業者もあるので、依頼費用が水泡に帰す心配も少ないでしょう。
費用や時間を節約できる
ネズミ駆除を自分で行うと、駆除グッズの購入や設置・管理、ネズミの捕獲や処分、清掃や消毒など、多くの手間暇や費用がかかってしまいます。
ネットで駆除に関する情報を調べてそれを実行しても、完全な駆除ができずに結局やり直すことになるなんてケースもありがちです。
その点、ネズミ駆除業者に任せてしまえば料金に見合った駆除が保証されるので、長期的に見ればむしろ費用や時間の節約になると考えることもできます。
また、見積もりや相談を無料で行ってくれる業者も多いので、費用対効果を比較した上で依頼することもできます。
ネズミ駆除の費用相場は?
とは言っても、多くの方が駆除依頼費用の具体的な額について気になってらっしゃる思います。
ネズミ駆除の費用相場は状況や間取りによって異なりますが、結論から言うと約10,000~250,000円の範囲であることが多く、金額は以下のような要素によって変わります。
ネズミの種類や個体数
ネズミの種類や個体数によって駆除に必要な薬剤や罠の種類や量が変わります。
ネズミの種類にはドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミなどがありますが、それぞれに適した駆除方法があり、また、ネズミの個体数が多ければ、その分駆除や処理に時間と手間がかかります。
侵入経路や巣の場所
侵入経路や巣の位置は、死骸の回収、清掃・消毒、侵入防止策などにかかる費用に大きく影響します。
侵入経路や巣の場所が床下や天井裏などの、狭くて作業しづらい場所になれば、当然作業時が伸び、駆除の難易度が高まるため、それに比例して料金も高くなってしまいます。
このように、駆除にかかる時間は上記の要素によって変わりますが、一般的には1~3時間程度となることが多く、ネズミの個体数が多かったり再発防策を実施する場合には、所要時間が伸びて数回に分けて作業を行わなければならないケースもあります。
業者の料金体系
前項で依頼費用を左右する条件を解説しましたが、実際にはネズミの個体数や駆除の難易度を定量化することは容易では無いため、業者は以下のような料金体系で請求額を決定します。
坪単位の料金
これは駆除の対象となる建物の敷地・延床面積に応じて料金を決める方法で、坪単位の料金は約3,000~10,000円と言われています。
この料金体系では、敷地面積が大きい場合に費用が高くなり、小さい場合には費用が安くなります。
固定料金
これは駆除する建物の敷地面積に関係なく、一律で駆除費用を決定する方法です。
固定料金は 10,000~50,000円と言われています。
この方法であれば、敷地面積が小さい場合には費用対効果が高くなり、大きい場合には安くなります。
見積もり料金
駆除する建物の状況や作業内容に応じて、個別に料金を決める方法です。
見積もり料金は状況に応じて変化しますが、約10,000~250,000円と言われています。
この方法では適正な価格が請求されやすい反面、見積もりに時間がかかることがあります。
ネズミ駆除を専門業者に依頼する際の注意点
ここまで、専門業者に駆除を依頼するメリットや料金の相場を解説しましたが、当然ながら業者によって施工のクオリティや料金には大きな差異があります。
ネズミ駆除業者はインターネットや電話帳などで探すことができますが、目に入るすべての業者が信頼できるとは限りません。
そのため、悪徳業者への依頼を避けるためにも業者選びには慎重を期する必要があり、以下のような点に注意して業者を選ぶことが大切です。
資格や実績を確認する
ネズミは鳥獣保護管理法の対象動物とは異なり、駆除自体には特別な資格や免許を必要としません。
しかし、だからこそ専門性の無い低品質な悪徳業者が簡単に参入できてしまう状況にあるので、資格や実績の有無は業者の専門性や信頼性を確認するのに欠かせない情報となります。
例え必須ではなくても、狩猟免許や防除作業監督者資格を取得している業者はより信頼できるでしょう。
また、業者の実績をチェックするなら口コミを参考にしてください。
実際に駆除した事例やお客様の声などをウェブサイトやパンフレットなどで紹介している業者を選ぶと安心です。
見積もりや契約内容を確認する
ネズミ駆除業者に依頼する前には、必ず見積もりを取ることが欠かせません。
見積もりでは駆除するネズミの種類やおおよその個体数、作業内容や方法、費用や支払い方法、保証期間やアフターサービスなどについてを詳しく説明してもらえます。
また、見積もりは無料で行っている業者が多く、依頼して損をすることはないので見積もりをもとに契約内容を確認し、不明な点や不安な点があれば質問や交渉をしましょう。
トラブルに発展しないためにも契約書には業者の住所や電話番号、担当者の名前や連絡先などを記載してもらうことも忘れないでください。
追加料金やキャンセル料に注意する
ネズミ駆除業者に依頼する場合は、追加料金やキャンセル料の存在に注意してください。
追加料金は、見積もりでは想定されなかった作業や材料が必要になった場合に発生することがあります。
キャンセル料は、契約成立後に私的な都合でキャンセルする場合に発生することがあります。
追加料金やキャンセル料の発生条件や金額は、見積もりや契約書に明記されているはずですので、見積もりや契約書をよく読み、納得しかねる場合は業者と相談しましょう。
駆除後の対応
ネズミ駆除業者が作業を終えたら、適切に駆除の効果が出ているか確認してください。
ネズミの姿や糞が見られなくなったか、侵入経路や巣への出入り口が塞がれたか、破損箇所の修繕や清掃がなされているかなどをチェックし、もし効果が不十分だと感じたら業者に連絡を取りましょう。
保証期間内であれば無料で再駆除を行ってくれることがあるので気兼ねなく相談できます。

手間暇を考えたら業者に相談してみるのも良さそうね!
自力で駆除しようとしても、結局安物買いの銭失いになるかもしれないし、一度見積もりだけでもとってもらおうかしら?
総括
記事はこれで以上となります。
害獣被害を最小限に抑えるうえでは早期発見、早期対応がとても大切になります。
どんな些細な変化や違和感も見逃さず、被害を発見したら速やかに対処しましょう。
もしネズミの駆除をご自身でなされる場合は、必要な知識を得るためにも当サイトの豊富なネズミ関連記事を是非ご参照ください!


コメント