皆さんはハクビシンのフン被害についてご存じでしょうか。
ハクビシンは沖縄を除いた日本全域に生息する野生動物であり、私達の生活に悪影響を与える害獣としても広く知られています。そんなハクビシンの被害の中でも有名なフン被害は時にベランダにも及ぶ可能性があります。
今回はベランダのフン被害に着目し、その有害性と対策について解説していきます。
是非最後まで読んでみてください。
目次
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

ハクビシンってどんな生き物?
ハクビシンは体長50cm~1mほどの夜行性動物であり、沖縄を除いたほぼ日本全国に生息しています。
アライグマやタヌキとよく似た外見をしていますが、ハクビシンは額から鼻にかけて白い縦線模様が入っているのが特徴です。
ハクビシンは基本的に臆病な性格をしており、こちらが手を出さない限り襲いかかってくる事はありません。しかし危険と認識すると襲いかかってくる可能性もある為注意が必要となります。
またハクビシンは木登りを非常に得意としており、時に私達の生活圏に悪影響を及ぼす可能性もあります。
ハクビシンのフンの有害性とは?

さて、それではハクビシンのフンにはどのような有害性があるのでしょうか。
ここでは大きく分けて3つの有害性について解説していきます。
悪臭被害
ハクビシンがベランダにフンをする事によって発生する被害の1つ目は悪臭被害です。
ハクビシンのフンは比較的匂いが少ないと言われていますが、尿からのアンモニア臭によって悪臭被害に繋がる可能性があります。
健康被害
またハクビシンの糞尿は人間の体に悪影響を及ぼす可能性も十分にあります。
ハクビシンは自分の体にだけでなく、糞尿にも病原菌を多く保有しています。
ここではハクビシンのフンに含まれる病原菌とその他の健康被害について解説していきます。
サルモネラ菌
サルモネラ菌はハクビシンのフンを媒介して感染する病原菌の一種です。サルモネラ菌は食中毒を引き起こす事で知られており、感染すると急な発熱、下痢や嘔吐などを引き起こします。通常は一週間程度で快方に向かいますが、免疫の少ない高齢者や小さなお子様が感染した場合脱水などを引き起こすため、命を落とすリスクが考えられます。
エルニシア菌
エルニシア菌もハクビシンのフンを媒介して感染する病原菌の一種になります。
症状の中で最も多いのが腹痛とされており、特に右下腹部の痛みと嘔吐から虫垂炎症状と間違われる事も多い病気となります。
他にも頭痛や咳、咽頭痛など様々な症状が見られます。
また重症化した場合、致死率が高いとされる敗血症などにも発展する可能性が高いのも特徴です。症状は3日から1ヶ月近く続く場合があり、注意が必要となります。
カンピロバクター
カンピロバクターもハクビシンのフンが原因となり感染する可能性がある病原菌になります。
主な症状として高熱や下痢、嘔吐や腹痛などが挙げられますが症状は数日で収まる場合が殆どです。
ただし乳幼児や高齢者など抵抗力が弱い人が感染した場合重症化し、敗血症など命の危険を伴う病気に発展する場合があるので注意が必要です。
ダニやノミの被害
ハクビシンのフンが巻き起こす健康被害は病原菌だけに留まりません。ハクビシンのフンを放置する事でダニやノミが繁殖してしまう可能性があります。
特にダニの仲間であるマダニは様々な病原菌を保有しており、命の危険を伴うものも多いです。
ダニやノミは一度繁殖してまうと駆除が非常に難しい為、ハクビシンのフンを見つけた際は早急に処理する必要があります。
建物の汚損被害
ハクビシンのフンは放置してしまうと建物の汚損被害にも繋がる可能性があります。
ハクビシンのフンは放置してしまうと他のハクビシンを呼び寄せてしまう可能性があり放っておくと屋根裏などに住み着かれてしまう可能性もあるのです。
ハクビシンは溜めフンという習性を持っている為、屋根裏や天井裏に住み着かれてしまうとフンの重さで天井が抜けたり、腐り落ちてしまうなどの被害に発展してしまう場合があるのです。
ベランダでハクビシンのフンを見つけた場合は放置しないように気をつけましょう。
何故ハクビシンはベランダにフンをするのか
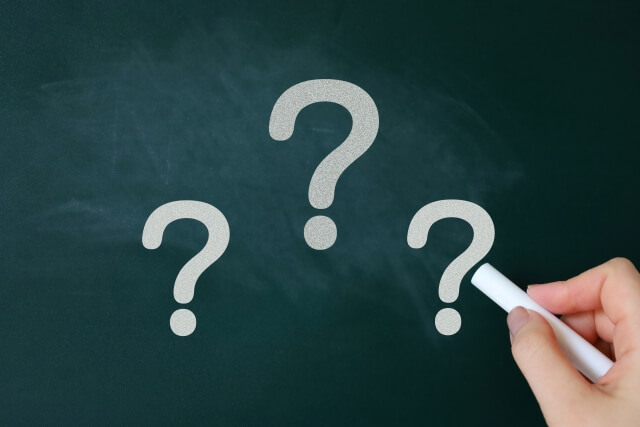
ハクビシンがベランダにフンをしている場合、大抵の場合はベランダにハクビシンの餌となるものが置かれていることが殆どです。
ベランダで家庭菜園などを行っている場合は特にハクビシンに狙われやすくフンをされやすくなってしまいます。
またベランダにゴミを放置してしまうのもハクビシンを呼び寄せる原因となります。
この為、ベランダなどで家庭菜園を行う場合は予めハクビシンが嫌がる成分を含んだ忌避剤などを撒き被害が出ないようにしましょう。
被害が少ないからと言って対策を怠ってしまうと屋根裏などの被害に発展する可能性があります。
ハクビシンは駆除してはいけないって本当?
ハクビシンが住み着いて困った方の中にはハクビシンを捕獲したり駆除したりする事を考えた方もいるのではないでしょうか。
実は個人がハクビシンを初めとする害獣を無断で駆除捕獲する事は法律によって禁止されています。
この法律を鳥獣保護法といい、違反した場合罰則を与えられる可能性があるのです。
個人がハクビシンを捕獲駆除を行う場合、行政に申請した上で複数の免許を取らなければならず、時間もかかってしまいます。
もしハクビシンに困っているという場合は専門業者に相談し、個人では再侵入防止の対策などに留めましょう。
また、業者に依頼する際も、その業者が狩猟免許を保有しているかどうかを確認する事も大切です。
ベランダのフンの処理と対策

それではいよいよハクビシンがベランダでフンをした際の処理の方法と対策について解説していきます。
ハクビシンは臆病な生き物ではありますが、一度危険と認識すると此方に襲いかかってくる可能性もあるので駆除を考えている場合は必ず専門の業者に依頼する様にしましょう。
ハクビシンのフンの処理の流れ
ハクビシンのフンを処理する際は十分な準備と対策が必要になります。
ここではハクビシンのフンの処理に必要な道具とフンの処理の流れについて解説していきます。
またここで準備するものは使い終わったら処分する為、使い捨てのものや足りないものは100均で揃えるなどして使い捨てのものを準備しましょう。
準備するもの
使い捨ての長袖の服と長ズボン
使い捨てのビニール手袋またはゴム手袋
不織布マスク
ゴーグル
髪をまとめる為のヘアゴム(必要があれば)
ホウキと塵取り
可燃ごみ袋
次亜塩素酸ナトリウム(ハイターなど)
雑巾
除菌スプレー
フンの処理の流れ
事前に準備したものを着用し、フンが素肌に付着しない様にする
ホウキと塵取りを使ってフンを集める
集めたフンを可燃ごみ袋に入れ、匂いが漏れないようにしっかり袋の口を閉じる
フンがあった場所に次亜塩素酸ナトリウムを使い消毒する
侵入経路の封鎖
ハクビシンは木登りを非常に得意としている為、近くにベランダに届くほどの木が立っていた場合、その木を登って侵入してくる場合があります。この場合可能であれば木を切るなどして対策を行いましょう。
またハクビシンは1箇所に住居を持たない為、他の家の屋根からベランダに入り込んでくる場合もあります。その際は忌避剤を使うなどして対策を行いましょう。
忌避剤の使用
ハクビシンの対策として忌避剤を使うのも有効な対策です。
ベランダでの対策を行う場合、殺虫剤のようにワンプッシュするだけで効果を発揮するスプレータイプや設置するだけで効果を発揮する固形タイプなどがオススメです。
また忌避剤は製品によって効果の期間が異なるため、購入の前に期間をよく確認しておきましょう。
専門業者に依頼する
ハクビシンを徹底的に追い出したい場合、素人では完全な対策は難しいと言われています。そんな時は害獣の専門業者に相談してみましょう。ここでは専門業者の選び方がわからないという方向けに有効な選び方を紹介していきます。
口コミで評価が高い会社を複数選ぶ
どの会社を選んだら良いか分からないという場合はまずクチコミの評価を基準にするといいでしょう。クチコミ評価の高い会社には対応がしっかりとしたスタッフが在籍しています。
この時、1社だけ選ぶのではなく、複数の会社を選んでおきましょう。
ホームページを確認し、成功実績が多い会社を選ぶ
ある程度の会社を選んだら、次はホームページなどでその会社の成功実績などを確認しておきましょう。
成功実績が多くある会社ほど、スタッフの知識や経験も豊富でありより正確な作業工程を組み立てる事ができます。
現地調査を行ってくれる会社を選び、作業工程を細かく確認する
また会社を選ぶ基準として現地調査を無料で行ってくれるかどうかの確認も必要です。
現地調査を行わなければ、現場の実情も分からず正確な作業工程も組めません。
現地調査を渋る会社であれば候補から外す事をおすすめします。
業者を選ぶ際は、現地調査を行う会社を選んだ上で詳しい作業工程や実情などをしっかり確認しておきましょう。
アフターケアや保証期間などを確認する
駆除後のアフターケアや保証期間も会社によって異なります。
アフターケア込みでの料金なのかどうかを確認し、保証期間の年数も事前に確認しておきましょう。
見積もりを複数の会社から貰い、予算に見合った会社を選ぶ
見積もりを貰う際は複数の会社から見積もりを貰う事も忘れてはいけません。
同じ作業工程や内容が近いものであっても会社によって料金は異なります。
複数の会社から見積書を貰い、自分の予算により近い会社を選ぶようにしましょう。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

まとめ
さて、ハクビシンがベランダにてフンをした場合の有害性と対策はいかがでしたでしょうか?
可愛い顔をしているハクビシンですが大変危険な害獣でもあります。
自身の環境や予算と相談して適切な対策を行ってください。
害獣駆除ガイドでは様々な害獣の対策について解説しています。是非一度他の記事も御覧ください。


コメント