アライグマを捕獲・駆除するには、お住いの自治体で許可を取る必要があります。
また、許可を取れたとしても、適切な場所に罠を仕掛けないとアライグマを捕獲することは難しいでしょう。
この記事では、アライグマを捕獲・駆除するための許可の取り方や、適切な罠の設置の仕方についてご紹介します。
多少運に左右されることもありますが、ポイントを押さえれば初心者でもアライグマを捕獲することはできるため、本記事を参考に適切な対応を実施してみましょう。
目次
アライグマを許可なく捕獲・駆除できない理由

アライグマは、自治体の許可を取らずに無許可で捕獲・駆除することができない動物です。
本章では、その理由について解説します。
理由①:「鳥獣保護法」によって管理されている
2014年5月に「鳥獣保護法」が「鳥獣保護管理法」が改正されました。
鳥獣保護法の歴史は、1896年に成立した「狩猟法」…つまり、狩猟に関する安全の確保・秩序の維持などを目的とした「狩猟の管理規則」を定めた法律に始まります。
現在、野生鳥獣は自然界だけでなく人々が住まう市街地にも姿を見せ、人との衝突を起こすケースも多発しています。
また「農林水産業に被害をもたらすもの」「気候変動の影響を受けて生息可能な環境が増加したもの」「地域の植生を食い荒らし生態系のバランスそのものを崩壊しかねないもの」など、野生鳥獣による被害・影響が拡大しており、その被害は放置するほど甚大なものとなるでしょう。
そのため、人間と鳥獣との関わり方も「保護」から「管理」へと変化していきます。
鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は「鳥類または哺乳類に属する野生動物」であり、アライグマもこの法律によって管理されています。
そのため、許可なく捕獲・駆除することができないのです。
理由②:「外来生物法」によって管理されている
アライグマはもともと北アメリカが原産であり、日本には生息していない動物です。
しかし、その見た目の可愛らしさからメディアなどで取り上げられ「動物園で飼育したい」「ペットとして飼いたい」といった方が急増、日本に大量輸入されることとなります。
しかし、アライグマは見た目に反して獰猛な性格をしているため、飼いきれずに飼育放置する人や逃げ出すアライグマが続出し、日本で野生化・繁殖することとなります(日本には天敵がほとんどいなかったこと、アライグマの繁殖率が高く・死亡率が低いことが、繁殖を拡大するきっかけとなった)。
野生化したアライグマによる被害は「農林水産業への被害」「生態系への被害」「人々の生活への影響」と広範囲に広がり、その影響を抑えるため「外来生物法」という法律が設立されました。
また、外来生物のうち「生態系」「人の生命・身体」「農林水産業」に悪影響を与える恐れがある動物を「特定外来生物」と認定し、アライグマは2005年に特定外来生物に指定されています。
外来生物法(特定外来生物)は、以下が規制されています。
- 飼育・栽培・保管・運搬・輸入
- 野外に放つ
- 特定外来生物を飼養する許可を得ている人が、許可を得ていない人に、譲渡・引き渡し・販売する
- 特定外来生物を特定飼養等施設以外で飼養すること
つまり、捕獲許可を得ることができたとしても、運搬することができないのです。
もし上記に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
アライグマを捕獲・駆除するための条件とは?

アライグマを捕獲・駆除するには、自治体の許可だけでなく一定の「免許」を所持していなくてはいけません。
本章では、その条件について詳しく解説していきます。
アライグマを捕獲・駆除するには「狩猟免許」が必要
アライグマを捕獲・駆除するには、狩猟免許を取得しなければいけません。
狩猟の狩法には「網猟」「わな猟」「第一種銃猟」「第二種銃猟」の4種類が存在し、箱罠などを使うには最低限「わな猟免許」を必要とします。
詳細は後述にてご紹介しますが、たとえば「わな猟免許」を取得するには、知識試験・適性試験・技能試験の3つの試験に合格しなければいけません。
自治体に許可をもらう方法
自力でアライグマを捕獲・駆除する場合、狩猟免許に加えて、役所や保健所などに許可を得る必要があります。
許可を得るには以下のような申請書類を必要とします。
- 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採卵等の許可申請書
- 有害鳥獣被害状況調査書
- 捕獲区域・場所を明らかにした地図や図面 など
ただし、必要な手続きは自治体によって異なるため、事前の確認が必須といえるでしょう。
狩猟資格を取らなければいけない理由について
アライグマを捕獲・駆除するには「指定の免許を取得したうえで、自治体の許可を得る必要がある」のですが、なぜ被害を被っている側がこういった面倒な手順を踏まなくてはいけないのでしょうか。
その理由の一つは、上述でもご紹介した「鳥獣保護管理法」によって保護されているからです。
もう一つの理由は「捕獲・駆除をするにはリスクが伴う」ことが挙げられます。
アライグマなどの野生動物は、効率的に捕獲する知識が必要となるだけでなく、感染症などの病気の感染にも注意しなければいけません。
病気の程度はそれぞれ異なるものの、なかには「致死率100%の狂犬病」のような症状が発病する恐れもあるため、知識・技術のない方が不要に野生動物に接触すべきではないといえます。
また、野生動物が棲みついていた場所にも菌や寄生虫が多数存在しているため、死骸はもちろん糞尿の清掃、居座っていた場所の消毒も徹底する必要があります。
素人が下手に対処することは大きなリスクを伴うため、その危険性を防ぐために一定の知識や技術が必要といえるでしょう。
狩猟免許を取得する方法について
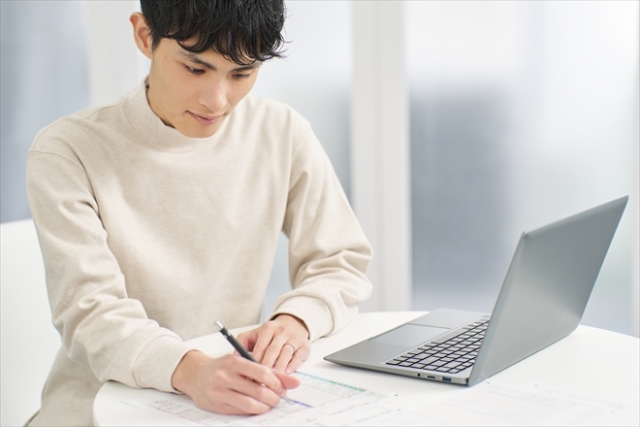
狩猟免許は猟法ごとに「網猟」「わな猟」「第一種銃猟」「第二種銃猟」の4種類に分かれており、いずれもお住まいの都道府県にて申請をおこないます。
提出書類は都道府県によって異なるケースがありますが、一般的には「狩猟免許申請書」と「医師の診断書」が必要です。
上記の書類とともに、受験票に貼るための写真(縦3cm×横2.4cm)と申請手数料の収入印紙(もしくは現金納付)を同封し、都道府県別の申請先に郵送することで申し込みが完了します。
また、免許を取得するには、知識試験・適性試験・技能試験という3つの試験をクリアしなければいけません。
知識試験は狩猟に必要な知識を確認するものであり、制度・猟具の使い方・動物の見分け方・自然保護や管理といった幅広い内容が出題されます。
試験時間は90分、問題数は30問です。正答率7割以上で合格です。
適性試験は視力や聴力・運動能力が問われ、わな猟の場合は両眼で0.5以上の視力がある+10mの距離で90dBの音が聞こえる+屈伸や挙手など体が自由に動かせるかどうかなどが確認されます。
技術試験は狩猟可能な鳥獣の判別に加え、使用可能な猟具・禁止猟具の判別+使用可能な猟具1種類の組み立てをおこないます。
これらすべてクリアすることで、罠猟の免許が交付されます。
なお、免許を取得したあとに実際の狩猟をする場合は、猟をおこなう都道府県で「狩猟者登録」をし「狩猟税」を納付しなければいけません。
狩猟者登録をするには3,000万円以上の損害賠償能力が必要であり、3,000万円以上の資産を証明できる書類もしくは猟友会に入会して共済保険に加入する必要があります。
- 許可を得るには免許+申請が必要
- 免許を取得するには申請+試験に合格する必要
- 実際の狩猟をおこなうには狩猟者登録をし狩猟税を納付する必要がある
このことから、家屋に潜むアライグマを捕獲・駆除するためにこれらの手間をかけるのは効率的とはいえないのが現状でしょう。
アライグマの駆除は専門業者に依頼するとよい

アライグマを捕獲・駆除するには相応の手順を踏む必要があり、それらの対応をしている間にその被害はどんどん拡大していくことでしょう。
そのため、害獣駆除に精通していない方(=素人)は、被害が拡大する前に専門業者に相談するのが手っ取り早いといえます。
自身で対処することに比べると駆除費用は高額になるかもしれませんが、免許の取得・申請・対処などのあらゆる手間を考慮すると、業者に依頼した方が総合的なコストパフォーマンスは優れているでしょう。
また、万が一被害が再発した際にも、業者に依頼していた方が安心です。
アライグマなど害獣の被害を防ぐことは素人には限界があるため、被害が拡大する前にプロに相談した方が効率がよいといえるでしょう。
アライグマを罠で捕まえる方法

自身でアライグマを捕獲する場合、適した場所に罠を設置する必要があります。
本章では、アライグマを罠で捕まえる方法についてご紹介しましょう。
「箱罠」を設置する
アライグマの捕獲によく利用される罠は「箱罠」というものです。
箱罠とは、箱のなかに餌を仕掛け、入ってきた動物が踏板を踏んだら扉が閉まる…というシンプルなもの。
アライグマは野生動物のなかでも大型な個体が多く(なかには140cmを超すものもいる)+力もかなり強いため、自力で箱罠を購入する場合は大きめで頑丈な作りのものを選ぶとよいでしょう。
価格は、6,000円~15,000円ほどが多いとされています。
また、自治体によっては罠を無料で貸し出してくれるケースもあるため、事前にお住いの自治体に確認をとっておくことも大切です。
罠の設置に適した場所は?
罠を仕掛ける場所として適しているのは、主に以下が挙げられます。
- 塀や家の壁沿い
- 軒下や庇の下
- 藪や茂みのなか
- 藪のなかの獣道
- 日陰になっている場所 など
その理由は「人や動物の目が届きにくく、安心してエサを食べられる場所」だからです。
また、罠の上部を板で覆うといった工夫も推奨されています。
捕獲に適した餌はなに?
捕獲に適した餌として挙げられるのは「キャラメル味のスナック菓子」です。
アライグマは果物や野菜などの甘いものを好物としますが、罠に仕掛けておくと腐ってしまう恐れがあります。
結果、アライグマをおびき寄せる効果が薄くなるだけでなく、害虫や悪臭が発生する原因にもなり得るでしょう。
また、ドッグフードやキャットフードの場合、野良の犬・猫を捕まえてしまう可能性が高くなるため、こちらもおすすめはできません。
腐る恐れがない+甘い食べ物という点で、キャラメル味のスナック菓子はアライグマをおびき寄せるに適した食べ物といえるでしょう。
捕獲したあとにやるべきこと
アライグマを捕獲したあとは、以下3つの手順を進めましょう。
- 自治体に連絡する
- 清掃・消毒をする
- 侵入経路を封鎖する
それぞれ、以下で補足を加えていきます。
自治体に連絡する
アライグマを捕獲しても「外来生物法によって生きたまま運搬できない」「免許の種類によっては駆除できない」ため、運搬・処分してもらうために、お住いの自治体へ連絡する必要があります。
仮に、自身で処分する場合であっても、できる限り動物に苦痛を与えない方法を取るように努めなければいけません。
免許・許可・知識・技術を有している方ならば自身でも対処できるでしょうが、不安がある方はすみやかにお住いの自治体の担当課へ連絡しましょう。
清掃・消毒をする
上述でも記載した通り、野生動物には数多のウィルスや寄生虫が付着しています。
また、住処としていた場所付近には糞尿が溜め込まれている可能性もあるでしょう。
これらは、悪臭や害虫などが湧く危険性があるため、徹底した清掃・消毒をしなければいけません。
清掃・消毒法の流れとしては、主に以下が挙げられます。
- マスク・ゴム手袋などを装備し、肌の露出を極力避ける
- 箒や新聞紙などで、野菜くずや糞尿を片付ける
- 糞尿があった場所にアルコールやエタノールなどを吹き付ける
- しっかりと拭き取る
- 使用した道具や着ていた服はそのまま処分する
消毒に使用する薬品は、消毒用アルコール・エタノール・殺菌力の高い次亜塩素酸ナトリウム洗剤などを使うとよいでしょう。
侵入経路を封鎖する
建物に棲みつくアライグマを駆除できても、侵入経路がそのままでは被害が再発する恐れがあります。
二度と被害にあわないためにも、侵入経路となる隙間は徹底的にふさいでおくべきでしょう。
侵入経路となりえる隙間は、金網などで封鎖してください(アライグマは10cmほどの隙間からでも侵入できるため、5~8cm以下の目合いが細かいものを使うとよい)。
また、以下の点にも注意しておきましょう。
- 破れやすい素材を使わない
- 建物の近く木の枝が伸びているような箇所があれば、剪定する
- 有刺鉄板・忌避剤・超音波発生装置などを併用する
- 隠れ蓑となりえる雑草は適度に処理する など
ここまでにご紹介した内容を徹底的におこなえば、アライグマの侵入を大幅に防ぐことができるはずです。
害獣を駆除する際の注意点について

本章では、害獣を駆除する際の注意点についてご紹介します。
猟で利用する猟具は使い方を間違えると人を傷つける恐れがあるため、狩猟をおこなう際にはさまざまなルールが定められています。
この点をしっかりと理解したうえで、狩猟をおこなうようにしましょう。
近づいても不用意に接触しないこと
野生のアライグマにはさまざまな菌や寄生虫が付着しており、さらに狂暴な性格をしていることから、不用意に接触すると攻撃を受け・病気を発病する恐れがあります。
仮に罠で捕獲できても「罠に入っているから大丈夫」と安易に近づけば、隙間から伸びてきた手に引っ掻かれたり、罠から逃げ出したアライグマに噛まれるといった危険を伴うかもしれません。
リスクを避けるためにも、罠で捕獲したアライグマは、市町村の職員や業者が来るまで不要に近づかないことをおすすめします。
とくに小さなお子さんやペットと一緒に住んでいる方は、自身だけでなく家族も接触しないよう十分な注意が必要です。
なお、アライグマは外来生物法によって管理されており、捕獲していても「運搬」することが禁じられています。
この点にも十分注意しておきましょう。
場所・期間が決められている
猟は好きな場所でいつでもできるわけではなく、狩猟可能な地域である「猟区」が定められ、かつ猟ができる期間(猟期)も原則11月15日から翌年2月15日までと決められています(北海道は10月1日~翌年1月31日)。
猟区・猟期が定められている理由は、事故を防ぐためです。
冬は葉や草が枯れ見通しがよくなること、さらに農林業に従事する人が減るため山林での事故が起きる危険性も少なくなることが挙げられます。
猟期・猟区以外での狩猟は違反行為のため、猟区や猟期をしっかりと確認しておくことが重要といえるでしょう。
狩猟可能鳥獣や捕獲数にも制限がある
日本に生息する野生動物は約700種類といわれており、そのなかでも狩猟が許されているのは48種(鳥類28種・獣類20種)とされています。
こういった制限がかけられている理由は、狩猟対象としての価値・農作物に対する有害性・生態への影響などを考慮した結果です(詳細は環境省が定めている)。
また、狩猟可能な鳥獣であっても、捕獲方法・捕獲頭数などが制限されているケースもあります。
この制限は都道府県によって異なる+年によっても変わるため、狩猟地域の制限や狩猟可能鳥獣の確認は怠らないようにしましょう。
自治体の許可・免許がなくてもできる対策法

無許可or免許がなくてもできるアライグマ対策としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 餌となるものを極力見せない
- 忌避剤などの対策グッズを活用する
- 侵入経路を封鎖する
アライグマは雑食のため、たとえ生ごみであっても口にします。
野菜・果物などの食べ物は表に出しっぱなしにしない、袋に入っている食材は容器に移し替える、生ごみはふたをし鍵をかけるなどの対策をし、衛生面を徹底的に管理するとよいでしょう。
ホームセンターやネット通販などで簡単に購入できる対策グッズを活用したり、金網や電気柵などで侵入経路を徹底的に封鎖するのもおすすめです。
ただし、素人にはできることに限界があるため、対処しきれないor被害が心配と感じる方は、早めに自治体や専門業者に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
アライグマを捕獲・駆除するには、免許を取得したうえで自治体の許可を得る必要があります。
しかし、被害が発生している段階で免許の取得を目指しても、取得できたころには被害が大幅に拡大していることでしょう。
- 手間と時間がかかりすぎる
- 怪我・感染症の恐れがある
- 駆除しきれない可能性が高い
- 再侵入を防ぐのが困難
上記のような問題も起こり得るため、被害を危惧される方は自力でどうこうしようとせずに、早めに自治体や害獣駆除の専門業者に相談することをおすすめします。


コメント