あいさつ
皆さんは、ダニ被害に遭われた事はありますか?
とても小さな生き物なので、日々の生活の中でその存在を意識する機会は多くないと思いますが、実はあなたの身の回りにもいる身近な生き物なのです。
そんな普段意識しない存在だからこそ、いざダニの被害に遭ってしまうと、多くの人にはどのように対処すればよいか検討もつきません。
そこで今回は、 ダニの被害に遭われてしまった方に向けてオススメの対策法をご紹介したいと思います!

聞いた話によると布団の中には1㎡あたり10万匹もいるらしいわね…。
今まで意識したこと無かったけど、最近ダニの存在が気になり始めたわ。
自分の寝ているところに虫がウジャウジャいるなんて耐えられない!

なかなか実感しづらいですが、ダニは我々の身近に沢山生息しています。
ある調査では、家庭のハウスダスト1gに最低でも数百匹のダニが含まれているとのこと。
アレルギーの原因にもなるダニは、できるだけ避けたいものです。
目次
ダニの基本情報

生態・習性
感染症の原因生物として有名なマダニは幼虫の段階でも目で見えるくらいの大きさですが、実のところ他の種類のダニはほとんどが体長1mm以下で、目視で確認する事はほとんど不可能なのです。
ダニは節足動物の中でも鋏角亜門と呼ばれるクモに近いグループに属する生物で、意外なことに分類学上は昆虫には当たりません。
ダニ目に属する種は世界中で40000種類以上存在するとされており、熱帯から寒冷地、乾燥地まで幅広く生息しています。
土の中、水の中、植物や動物に付くだけでなく、家の中、保存食の中、さらには人間の顔や皮膚など、さまざまな環境に合わせてそれぞれ違う種が適応して暮らしています。
種類
4万種以上存在するダニですが、今回はその中でも”家”に住んでいるダニをピックアップしてご紹介します。
室内に生息するダニとしては、主に以下のコナダニ、チリダニ、ツメダニなどが挙げられます。
コナダニ
成虫の体長は0.3~0.5mm。
コナダニがエサにしているのは、小麦粉、パン粉、ホットケーキミックスなどの粉類をはじめ、ポテトチップス、チョコレートなどのお菓子、七味やコショウといった薬味など非常に多岐にわたります。
発生場所は台所まわりが多いですが、湿度が高いと畳やカーペットなどの敷物でも発生します。
コナダニは湿度の高まる梅雨の時期や秋から春にかけての温度低下に伴う結露によって発生し、適した環境が整えば1日から2日で大繁殖する場合もあり、小麦粉などの中に紛れれば肉眼で確認することは大変難しく、気がついたら小麦粉がコナダニに置き換わっていた!なんて恐ろしい事態も起こり得るのです。
チリダニ(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ)
体長は0.3〜0.4mmで、肉眼ではほとんど見えませんが、日本の家庭にいるダニのほとんどはチリダニと言われるくらい身近なダニです。
チリダニは、エサとなるのは人間のアカやフケ、食品のくず(食べこぼし)、カビ、昆虫の死骸やホコリなどを食べて生活します。
温度20〜30℃、湿度60〜80%の環境を好み、畳、カーペット、ベッド、布団などの敷物や寝具が発生場所となりますが、貯蔵された食品の中で増える場合もあります。
チリダニは人間や動物を直接刺すことはありませんが、ダニの死骸やフンがアレルギー疾患(アレルギー性鼻炎、喘息など)の原因になることがあります。
ツメダニ
成虫の体長は0.7~0.8mm。
ツメダニは、ヒョウヒダニやコナダニなどの小さなダニや虫を餌にする習性を持っているため、チリダニが増殖するに伴って、必然的にツメダニも増えてきます。
ツメダニは人間の血を吸血しないものの、他のダニの体液を吸って栄養を得る習性を持っており、たまたま接触した際に人間の皮膚に刺さった際には、人間の体液も吸うことがあります。
刺された直後は異変を感じないものの、数時間後には発疹や痒みが生じ、この症状は最大で一週間ほど続きます。
コナダニなどを餌とするため、発生場所もこれらのダニと共通しています。
害虫被害
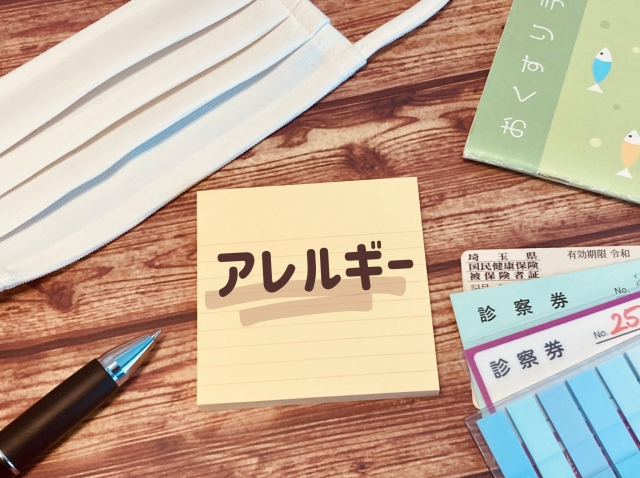
アレルギー
人が生活している以上、コナダニやチリダニは必ず発生してしまいますが、通常の範囲内でしたら大した問題にはなりません。
無視できないほど被害が顕著になるのは、生息数が多くなってアレルギーを引き起こしたり、ツメダニが増えて人間が刺されるようになったりする場合でしょう。
家の中にあるチリやホコリの中でも1mmより小さいものを特に”ハウスダスト”と言いますが、これは具体的にはダニの死骸や糞、カビ、細菌、花粉、衣服の繊維、アカや皮脂、ペットの毛などによって構成されており、ハウスダストでアレルギーになる人のほとんどは、ダニやその死体、糞が原因で、気管支ぜんそくやアトピー性皮膚炎になるのです。
したがって、アレルギー被害を軽減するためにも家の中でダニが増えないようにすることが大切です。
ダニによるアレルギー反応は花粉症の症状と似ているため混同されがちですが、花粉の季節が終わってもアレルギーの症状が続く際には、ハウスダスト(ダニ)アレルギーかもしれません。
特に、1年中鼻が詰まってる、という方はこうした可能性を疑うべきでしょう。
また、開封した穀物の粉を含む食材(お好み焼き粉・ホットケーキミックスなど)を常温で保管していると、保管中に粉の中でダニがたくさん増えて、それに気付かないまま作った料理でアナフィラキシーショック(全身に出るアレルギーの症状で命の危険があるひどい反応)になることがあります。
これは、「パンケーキシンドローム」という名前で、日本や外国で事例が報告されています。
吸血被害
ダニによる吸血被害とは、ダニが人間や動物の血を吸って感染症などの症状を引き起こす被害です。
ダニには、マダニ、イエダニ、トリサシダニ、シラミダニ、ヒゼンダニなど、人の血を吸う種類がいくつか存在し、これらのダニは人や動物に付着すると皮膚に穴を開けて血を吸います。
ダニに血を吸われると、かゆみや痛み、発疹などの炎症が起こりますが、それだけではなく、ダニが持っている病原体に感染する可能性もあります。
ダニによって媒介される感染症には、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)、日本紅斑熱、ライム病、ダニ媒介脳炎などがあり、これらの感染症によって発熱や消化器症状、神経症状、出血症状などを引き起こし、最悪の場合重症化して死に至る可能性もあります。
ダニは顔や手足はほとんど刺さず、わき腹や下腹部、太ももの内側など皮膚がやわらかいところを刺す習性を持っており、刺された箇所は赤い斑点ができて、中心部がプツプツと少し膨らみます。
もし、ダニに刺されたり感染症の症状が出たりした場合は、医療機関を受診して適切な治療を受けるよう注意してください。

ダニって布団とかカーペットにいるイメージだったけど、食材の中でも繁殖するのね…。
知らず知らず食べてしまってるかと思うと、気持ちがゲンナリするわ。
私は年がら年中鼻が詰まってるんだけど、もしかしてダニアレルギーなのかしら…?
対策法

目に見えず、数も非常に多いダニをどのように駆除するのか、なかなか想像がつきにくいかもしれません。
しかし、対策法の鉄則はとてもシンプルで、ダニも好む「高温」「多湿」「豊富なエサ」の3つがそろう環境を減らすという点で一貫しています。
以下に、その具体的な方法をご紹介しましょう。
天日干し
ダニ対策と聞いて真っ先に思い浮かぶのは天日干しです。
布団などを天日干しする光景は今でも至るところで目にできますが、実は天日干しによるダニ駆除効果は極めて限定的です。
ダニを駆除するのに必要な温度は60℃以上といわれており、暑い夏の日に布団の表面のダニを駆除できたとしても、布団の中の温度が60℃まで上がらないので、完全な死滅はできないのです。
また、ダニは思いのほか機敏に移動することができ、天日干しをしても布団の裏側に避難して、被害を回避する習性を持っています。
天日干しで片面20分~40分づつ、裏表で合計1時間半ほど太陽光に晒しても、布団のダニのおよそ80%が生存すると言われており、布団叩きで叩くことでダニの死骸を払い落とすことは出来ても、内部に潜り込んだ生きたダニを除去することは困難です。
とはいえ、天日干しが布団の湿気や匂いを取り除くのに有効な方法であることには変わりないので、定期的に日に当てることをおすすめします。
吸引機
数年前から知名度が高まり、一躍ヒット商品となった”布団専用の掃除機“。
振動機能や紫外線照射などを謳うこうした掃除機を実際に使用しているという方も多くいらっしゃると思いますが、その効果には懐疑的な見方があることをご存知でしょうか。
もちろん掃除機ですのでダニのフンや死骸を吸い取ることは出来ますが、生きたダニは脚を布団の繊維に絡ませて体を固定するので、掃除機であっても吸引は困難です。
ただ、死滅したダニの死骸はハウスダスト、ひいてはアレルギーなどの原因になりますので、掃除機をかけて死骸を除去することは無駄ではないでしょう。
また、周波数のより短いUV-Cと呼ばれる紫外線は、ある程度長時間照射することでダニを死滅させる効果があります。一度の照射でダニを死滅させるのは難しくても、布団専用掃除機を繰り返し使用することで一定の効果を期待できます。
布団や畳、カーペットなどダニが潜みやすい場所には「1㎡あたり20秒」を目安に、ゆっくり時間をかけて掃除機をかける事を意識すると良いかもしれません。
洗濯
次に思いつくのは、洗濯によってダニを除去する方法です。
最近では水洗いできる布団、布団カバー、枕、マットレスなどが普及しているので、洗濯機にダニ掃除を任せて手軽に綺麗な状態にしたいところです。
しかし、残念ながら洗った程度ではダニは死滅しません。
ダニの死骸とダニの餌である人間の皮脂や髪の毛などもキレイに落とせるので、表面がキレイになる水洗いには、ダニ対策として一定の効果はあるものの、生きているダニも、ダニの卵も死滅はしません。
ただし、家庭用のドラム式洗濯機も乾燥時には最大で60℃から70℃と、ダニを死滅させるのに十分な高温状態になります。
ご家庭にこうした洗濯機があるという方は、ぜひご活用ください。
コインランドリー
コインランドリーの種類や温度・乾燥時間によって異なりますが、ダニ対策でコインランドリーを使用するのも有効な選択肢です。
コインランドリーの乾燥機は一般的に家庭用洗濯機よりも高い温度で乾燥することが可能なので、ご自宅の洗濯機では心許ないという方にオススメです。
ただし、この方法だけで完全にダニを死滅させるのは難しいので、他の方法と併用するとより安心できるでしょう。
また、綿や羊毛などの素材をコインランドリーで洗濯・乾燥すると、生地を痛める危険性があるので注意が必要です。
乾燥機
最も手軽な方法として挙げられるのが布団乾燥器を使ったダニ駆除です。
ダニは50℃では2~6時間で、60℃でなら15分以内で死滅しますが、一般的な布団乾燥機の温度は最大60℃ほどとなるので、ダニの駆除には十分な性能を持っています。
この方法の一番のメリットは、ノズルをセットするだけで良い、という手軽さで、天日干しや洗濯のように重い布団を移動させる必要はないので、高い頻度でこまめに乾燥できます。
ただし、ダニの死骸を別途掃除しなければならず、熱が一部に集中してしまうケースもあるので気を付けてください。
湿度の高い時期は最低でも2週間に1度程度、できれば数日に1度程度の頻度で使用しましょう。
ドライヤー・スチームアイロン
ここまでは布団のダニを想定して対策法をご紹介してきましたが、実はソファもダニが繁殖しやすい場所になります。
布団などに比べて厚みがあって湿気が溜まりやすいですが、厚みがあることにより乾燥機にかけることもできません。
そこで活用できるのがドライヤーやスチームアイロンを使ってソファのダニを駆除し、湿気を取り除く方法です。
ダニをドライヤーやスチームアイロンの高熱に晒して死滅させた後は、掃除機でしっかりダニを吸い込むようにしましょう。
ソファの種類によってはダニの繁殖を抑えることができる革やアクリル素材のものもあるので、布地のソファを使われている方はダニ対策も兼ねて買い替えを検討してみては如何でしょうか。
ただ、ダニが繁殖しにくい素材であっても、完全に予防ができるわけではないためこまめな掃除が必要不可欠となります。
予防法
前述したダニ駆除の方法は、もちろんダニの発生予防としても有用です。
ダニが繁殖しやすい6月頃から湿度を上げない、餌となる食料を適切に管理、皮脂・アカを掃除するといった予防策を講じることで、夏を迎える数ヶ月後の繁殖数を劇的に抑える事ができます。
起床後に布団が寝汗で湿っていた場合は、天日干しや乾燥がけで湿気を十分に取り除き、木製のタンスやクローゼットの換気も心掛けるようしてください。
タンスやクローゼットを常に閉めていると、空気が入れ替わらず湿気が溜まりやすく、ダニのみならずカビの原因にもなります。定期的に扉をあけることで風通しが良くしましょう。
こまめに換気をすることが難しい場合は、湿気を吸い取ってくれる市販の乾燥材を使用するのがおすすめです。
とりわけ梅雨から夏にかけての時期に繁殖を抑制し、秋頃からは繁殖したダニの死骸やフン、脱皮殻などのアレルギー物質を除去するよう心掛けましょう。

生きてるダニを除去するのって難しいのね…。
洗濯できる布団ならまだしも、ソファのダニ対策はなおさら大変よ。
台所も含めて丸ごとダニ対策をするなら、やっぱり業者に頼むのが一番良さそうね!
専門業者へ依頼

ダニ対策をしたいけど、時間も自信もないという方には専門業者への依頼がおすすめです。
専門的な知識を持ったプロに任せれば、面倒な作業を自分で行う事なく、確実で効率的な対策が可能です。
一方で、決して安くない金額を要するので、業者選びは慎重に行わなければなりません。
ダニ駆除業者の選び方
無駄な出費を避けるためにも、失敗しないダニ駆除業者の選びはとても大切です。
目を引く安さや誇大広告に釣られて安直に決めてしまうと、駆除を頼んでも満足できる結果が得られないかもしれません。
広告の言葉に惑わされないで、以下ののポイントをきちんと確認し信頼できるダニ駆除業者を探しましょう。
- 駆除の方法について詳しく教えてくれるか
駆除業者によって駆除方法や使う薬剤に差があります。
料金に見合った適切な施工をがなされるか、あらかじめ確認しておくと安心でしょう。 - その薬剤は人体に影響がないのか
特に赤ちゃんやペットがいるご家庭は、健康に配慮した薬剤が使用されるか業者に問い合わせてみましょう。
最近は人体に無害な薬剤をまくダニ駆除業者が多いですが、それでも心配な人向けに高熱処理を用いたダニ駆逐に対応している業者もあります。
問い合わせの際には最初に希望や家の状況を伝え、それに応じた駆除方法を提案してくれる業者を選ぶよう心がけてください。
見積もり料金がはっきりしているか
専門業者への駆除依頼は最低でも数万円〜が相場ですが、業者によってある程度価格体系に差があるので、見積もりを明朗に示してくれるところを選びましょう。
業者によっては見積もりが杜撰で、見積もりと異なる額を請求したり駆除後に追加料金を要求するなどして、予想だにしないトラブルに発展するケースも散見されます。
特に、顧客が依頼するか迷っている状況で、繁盛期になると依頼を受けられなくなる、などといった論調で依頼を急かすような業者は危険です。
曖昧な説明や不安を煽るようなセールストークには注意して、事前にしっかり見積もりを示し、メリット・デメリットを公平に説明する優良業者を見極めましょう。
優良業者であれば、追加費用が発生する可能性や、その内訳をきちんと説明してくれるので安心できます。
実績を調べる
業者の信頼性を確認するのに最も有効な方法は、実績を調べることです。
ホームページを持っている業者も多いので、依頼を決める前に一度その業者の実績を確認することをオススメします。
ただし、ホームページには業者にとって都合の良い情報だけが掲載されている可能性もあるので、インターネット上で第三者の口コミを調べてみると良いでしょう。
その業者の信頼性は対応件数や事業年数に現れることが多く、業界団体による認証を受けていない業者には注意が必要です。
どうぞ料金やプランに釣られずに、実績や評判から信頼できそうな業者かどうか確認してください。
駆除後のアフターフォローがあるか
ダニ被害の中には、稀に対策後も短期間で再発してしまうケースがありますが、再発の度に追加で対策費用がかかってしまう事だけは避けたいものです。
一部の業者では、駆除後一定期間内にダニが再発生した場合に無料での駆除を保証する制度をとっているところも存在するので、こうしたアフターフォローの有無をぜひとも確認してください。
保証制度がある業者であれば、再発の不安に怯える必要もありませんし、再発を抑える方法をアドバイスしてくれる場合もあります。


オススメの業者を紹介してくれて助かるわ!
ホームページを確認してみたけど、どの業者も実績豊富で見積もりや現地調査を無料でしてくれるみたいね。
最長10年の保証もあるし、この中から依頼先を選ぼうかしら…?
後書き…
これで以上になります。
今回はダニ被害に遭われた方へ向けて、おすすめの対策法をご紹介させて頂きました!
目に見えない小さな生き物だからこそ、ダニに対する危機意識は低くなりがちです。
当サイトではダニにまつわる豊富な情報をはじめ、他にも多種多様な害獣被害に関する情報も発信しておりますので、ぜひブックマーク登録していただいて、害虫・害獣にお悩みの際はお気軽にご参照くださいませ!


コメント