「家の近くでアナグマらしき生き物をよく見かける」「アナグマにビニールハウスの果物を食い荒らされた」とお困りではないですか?
アナグマを見つけたときに自分でできる対処法として、
・板やワイヤーメッシュ、電気柵で侵入を防止する
・嫌いなにおいや音、光で追い払う
などがあります。
しかし、完全に駆除したい場合は、これだけでは不十分です。
アナグマは穴掘りが得意なため、柵の下に穴を掘って敷地内に侵入する場合があります。
そうなると捕獲が必要になりますが、アナグマなどの野生鳥獣は、鳥獣保護法という法律によって守られており、勝手に捕獲や駆除をすることが禁止されています。
アナグマの捕獲には、狩猟免許と狩猟者登録、市町村による有害鳥獣捕獲の許可が必要です。
狩猟免許なしで許可が下りる場合もあるものの、効果的な場所に罠を仕掛ける必要があるほか、捕獲したアナグマを自分で殺処分しなければならない可能性があります(回収してくれる自治体もあります)。
ハードルが高いと感じる場合や、どうしたらいいかわからない場合は、害獣駆除業者に相談することも視野に入れてみてください。
この記事で、アナグマがどんな害獣なのか、どんな対処法があるのかを知っていただき、被害を最小限に抑えるきっかけになれば幸いです。
本当にアナグマ?似た動物との見分け方【画像あり】
アナグマを見つけたらまず最初にやることは、本当にアナグマなのか確認することです。
害獣の種類を特定するのは、簡単なようで意外と難しいです。
遠くからしか見られない場合や、一瞬しか姿を見せない場合もあるので、似ている動物と混同しやすいためです。
アナグマは、タヌキ、ハクビシン、アライグマとよく見間違えられます。
害獣駆除を効率よく進めるために、アナグマと、アナグマに似た動物の特徴を知っておきましょう。
アナグマの見た目の特徴

アナグマは、目の上下に縦に伸びる黒い模様が印象的です。
体はズングリムックリで、褐色のものが多いです。
鼻は黒く大きいです。
耳は丸みを帯びて小さく、細長く鋭い爪があります。
タヌキの見た目の特徴

タヌキは、目から頬にかけて横に広く黒い模様が広がっています。
体は灰褐色をしており、足先が黒いです。
額から鼻の手前までは白いです。
耳は黒く縁取られており、三角形です。
ハクビシンの見た目の特徴

ハクビシンは、頭の上から鼻まで伸びる白い模様が一番の見分けポイントです。
体は灰褐色で、顔と足の下部分は黒いです。
両目の上と下にも白い模様があります。
鼻はピンク色(黒色の個体もあり)で、尻尾が長いです。
アライグマの見た目の特徴

アライグマは、目の周りにハの字の黒い模様があります。
体は、灰色から明るめの茶褐色です。
額から鼻にかけて黒い縦線が入っています。
長い尻尾のリング模様も特徴的です。
アナグマの生態

アナグマという名前の由来は、「穴を掘ること、クマに似ていること」からきています。
「クマ」と付いていてもクマの仲間ではなく、イタチの仲間です。
アナグマの大きさは、頭と胴の長さが55~75cm、尾の長さが10~15cmほどです。
体重は、4~15kgほどで、地域によってバラつきがあります。
オスのほうがメスよりも一回り大きいです。
参考:農林水産省 農村振興局
野生鳥獣被害防止マニュアル -アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ-(中型獣類編)
アナグマの食性|雑食で甘いものが大好物
アナグマは、肉食寄りの雑食です。
長く鋭い爪で土を掘り起こし、地面に鼻先をねじ込んでミミズや昆虫の幼虫、うさぎ、モグラ、ネズミ、カエル、トカゲ、ヘビなども食べます。
猫を食べるという噂もありますが、猫は基本的に食べません。
スイカやイチゴ、柿、落花生、きのこ、うり類、とうもろこし、稲など、果物に野菜、穀物も好みます。
木登りは不得意で、果実は木から落ちたものを食べます。
食べ物に対する執着心が強く、何度もしつこく食べ物を求めてやってきます。
アナグマの行動|建物の下に穴を掘られると崩壊のリスクが高まる
アナグマは土に穴を掘って穴の中で生活します。
長い穴は15mほどのものもあります。
建物の下に穴を掘られると、地盤が緩み倒壊するリスクが高まります。
日本は地震が多いこともあり、切実な問題となっています。
海外では、イギリスの小学校の地下にアナグマが大きな穴を掘り、倒壊のリスクに怯えながら授業を受けているというニュースもありました。
アナグマは夜行性で、日中は穴の中で休息をとることが多いですが、日中に活動することもあります。
アナグマが掘った穴を利用して、タヌキなど別の動物も侵入してきます。
人を襲うことは基本的にありませんが、人馴れしており、近づいても逃げようとしないことが多いです。
アナグマの危険性|病原菌や寄生虫を媒介し、溜め糞で床材を腐らせる
アナグマなどの野生鳥獣は不衛生な環境で暮らしているため、病原菌やノミ、ダニ、寄生虫などを持っており、人にも媒介します。
体にマダニがついている場合もあります。
危険なので、むやみに近づかないようにしましょう。
また、アナグマには同じ場所に何度も糞をする溜め糞という習性があります。
雑食で何でも食べることもあり、糞はひどい悪臭です。
溜め糞と同じ場所に排尿もするので、床下や納屋などに棲みつくと、床材を腐らせてダメにしてしまいます。
溜め糞は、害虫が寄ってきたり雑菌が繁殖したりと、不衛生極まりない状態となります。
アナグマの繁殖力|繁殖力は低めだが成長が早い
アナグマは春に1~4頭出産します。
4月が出産のピークで、生まれたばかりの子は体長7~8cmで毛がない状態です。
繁殖力は低めと言えるでしょう。
生後1ヶ月で黒っぽい体毛が生えて、目はまだ開きません。
2ヶ月頃に目の上下に黒い模様が出現します。
4ヶ月で大人とほぼ変わらない大きさになり、長く鋭い爪も生え揃います。
成長が早いです。
寿命は10年ほどですが、野生のアナグマは5~6年などさらに短い場合もあります。
アナグマを見つけたらどうする?自分でできる対処法

「害獣駆除業者に依頼すると費用がかかりそうだし、自分で対処したい」と思う人も多いことでしょう。
予備知識のないまま個人で動くと、思わぬアクシデントに見舞われる可能性が高いです。
まずは市町村のホームページを確認してみましょう。
忌避剤で追い払ったり、板や電気柵で侵入を防止したりするだけであれば、狩猟免許は必要ありません。
市町村のホームページを確認して問い合わせる

市町村のホームページでは、その地域に多く出没する害獣の注意喚起をしていることが多いです。
猟具の貸し出しや、害獣駆除業者の紹介を行っている場合もあります。
市町村のホームページ内で「アナグマ」「害獣」「鳥獣」などの単語で検索するとヒットするはずです。
ホームページでアナグマ駆除についての記載内容を確認したら、市町村に電話もしくは直接出向き、詳しく話を聞いてみましょう。
市町村では、相談はできても害獣駆除自体は引き受けてもらえないことが多いです。
自分でできる対処法でどんなものがあるか相談し、できそうにない場合は害獣駆除業者の利用を検討しましょう。
忌避剤(嫌がるにおい)で追い払う

忌避剤とは、害獣が嫌いなにおいなどを使って追い払うための薬剤のことです。
アナグマは、木酢液やハッカ、ミント、レモンのにおいが嫌いです。
また、天敵である狼の尿のにおいも効果的です。
雨で忌避剤が流れてしまうと、効果が弱まります。
小さい子供やペットがいるなどの理由で、忌避剤や狼の尿を使いたくないときには、ミントなど天然由来成分のものを使いましょう。
ホームセンターや通販サイトなどで、さまざまな忌避剤が販売されています。
害獣撃退器(音や光)で追い払う
アナグマは、害獣撃退器で強い光や大きな音を出すとこわがって逃げていきます。
ただし、警戒心が低いこともあり、毎回同じ音や光だと、慣れてしまいこわがらなくなる可能性があります。
効果が薄れてきたと感じたら、別の策を考えましょう。
音と光に加えて動きもある害獣撃退器であれば、「生きている」と錯覚させることができ、さらに効果があります。
害獣撃退器も、ホームセンターや通販サイトなどで購入できます。
板やワイヤーメッシュ、電気柵で侵入を防止する

板や目の細かいワイヤーメッシュを土の中に埋め込んで侵入を防ぐ方法や、トタン板で敷地内の野菜などを囲み餌となるものを見せないようにする方法なども有効です。
電気柵もよく使われますが、雑草が伸びてワイヤーの通電部分に触れると、漏電して大幅に電圧が下がるため、草刈りを怠らないようにする必要があります。
最近では、樹脂と電気を組み合わせた複合柵なども市販されており、「管理作業への支障を少なくし、低コストで設置に時間を取らない、移動が簡単である」ことから人気が高いです。
また、アナグマはアライグマやタヌキなどによく見られる探査行動が少ない傾向にあります。
探査行動とは、目の前にあるものが安全かどうかを確認するため、警戒しながら鼻先で触る行動のことです。
電気柵は、この探査行動の習性を利用して、鼻先に痛みを与え害獣を撃退する方法です。
アナグマは、好きな食べ物があるとわかると、電気柵に触れることなく手前に穴を掘り、土の中から敷地内に侵入することができるため、電気柵が通用しない場合があります。
罠を仕掛けて捕獲する【狩猟免許が必要】

罠を仕掛けて害獣を捕獲するには、狩猟免許と狩猟者登録、市町村の許可が必要です。
ただ、被害が大きい自治体などでは、狩猟免許を持たない人にも許可を出し、捕獲を行わせているケースもあります。
害獣の捕獲には危険がつきものです。
噛まれたり引っかかれたり、病原菌や寄生虫、ノミ、ダニをもらってしまうリスクもあります。
自信がない場合は無理に行わず、害獣駆除業者に相談してください。
害獣駆除業者に依頼する場合の流れ
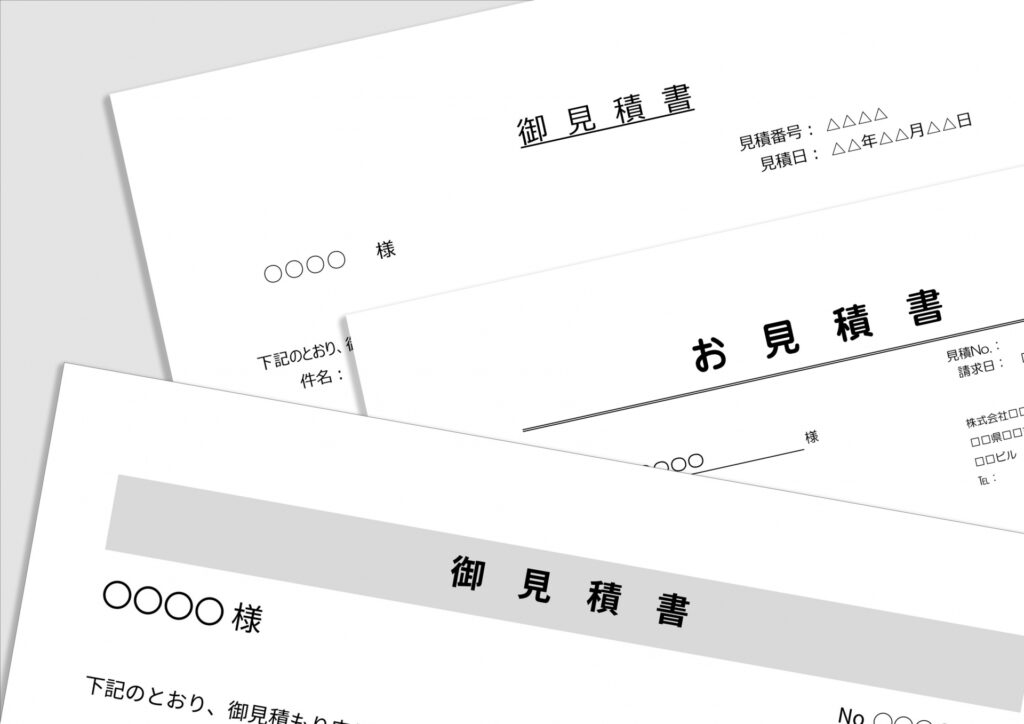
害獣駆除の基本的な流れは、
①害獣の追い出しまたは捕獲 ②侵入経路の遮断 ③被害箇所の清掃・消毒 ④再発防止 ⑤被害箇所の修復
です。
これらをまとめて引き受けているのが、害獣駆除業者です。
害獣駆除は、間違ったやり方で時間だけ経過すると、あっという間に被害が拡大してしまいます。
どうしたらいいかわからない場合や、すでに被害を受けている場合は、害獣駆除業者に相談することをお勧めします。
悪徳業者も存在するため、優良な害獣駆除業者を見つけるために、三社程度から相見積もりを取りましょう。
害獣駆除業者に駆除を依頼する場合の流れは以下の通りです。
アナグマの駆除ができる業者を見つける
害獣の種類によって、駆除の方法も猟具も違うため、アナグマの駆除ができる害獣駆除業者を見つけなければいけません。
まずは、「市町村名 アナグマ 駆除」などの単語でネット検索をして、お住まいの地域でどういった害獣駆除業者が活動しているかをざっくりと見てみます。
ホームページを数件開き、「対象害獣」の項目にアナグマが載っている業者を三社程度ピックアップします。
その際、害獣駆除業者の口コミも確認しておきましょう。
業者のホームページ内に掲載されている口コミは、いいことしか掲載されていない場合があります。
悪い口コミも公平に掲載されているサイトを信用するようにしてください。
市町村から紹介された害獣駆除業者だからと言って、必ずしも優良業者とは限らないので注意が必要です。
【あわせて読みたい】
信頼できる害獣駆除業者の選び方チェックリストとおすすめの害獣駆除業者3選
三社程度から相見積もりを取る
三社程度をピックアップできたら、メールか電話で相見積もりを依頼します。
おすすめはメールでの見積もり依頼です。
なぜかというと、害獣駆除の悪徳業者が存在するので、あとで「言った、言わない」になるのを防ぐためです。
三社にバラバラの条件を伝えてしまうと、見積もり内容の比較が難しくなるため、必ず同じ条件を伝えるようにしましょう。
現場確認に来てもらう【立ち会い推奨】
見積もり依頼をした三社程度にそれぞれ現場確認に来てもらい、被害の現状やどういう処置が必要かを検討してもらいます。
現場確認の様子を見ておくと、信頼できる業者かどうかを判断する材料になります。
「現場確認を依頼したらあとはおまかせ」ではなく、業者の現場確認に立ち会い、積極的に話を聞くようにしましょう。
面倒かもしれませんが、悪徳業者に騙されてお金を無駄にするリスクを考えると、慎重に選ぶべきです。
見積もり比較!「侵入保証10年」など信頼できる業者に依頼する
見積もりが提出されたら、比較をして業者を選びましょう。
再発した場合の保証については、「侵入保証」と「部分保証」があります。
たとえ保証期間が10年であっても、「部分保証」の場合は、前回害獣駆除の処置をした場所から侵入した場合のみ保証の対象となります。
一方「侵入保証」は、処置の有無に関係なく、敷地内に再度害獣が侵入したら保証しますという内容です。
保証が無償か有償かも確認して、見積もりに記載がない場合は記載してもらいましょう。
アナグマを見つけたときやってはいけないNG行動

アナグマを見つけたときに、やってはいけないNG行動があります。
近隣住民や自治体に迷惑を掛けないよう、責任ある行動を心がけましょう。
【NG】近づく、餌を与える
アナグマはかわいい姿形をしているため、近づいてさわったり餌を与えたりしたくなるかもしれませんが、絶対にやめましょう。
餌付けをすると、アナグマが味をしめてその場所に何度も来るようになり、近隣住民はもちろん、自治体にも迷惑をかけることになります。
たとえ、アナグマが怪我を負っていたとしても、保護して家に連れ帰ることはやめましょう。
害獣を再度放すほうが、無責任な行動なのです。
特に子供の行動には注意が必要です。
【NG】許可なく罠を仕掛けて捕獲、駆除する
アナグマは害獣ですが、鳥獣保護法で守られており、許可なく捕獲すると罪に問われます。
中には、狩猟免許がなくても捕獲を許可している市町村もありますが、許可は必ず必要です。
市町村の許可を受けて捕獲することになった場合、殺処分は害獣が苦しまない方法を取ることが大切です。
自治体によって定められたルールがある場合もありますので、守りましょう。
【NG】動物園に持ち込む、問い合わせる
害獣をいきなり動物園に持ち込んだり、引き取りをお願いするケースがあり、市町村のホームページに注意喚起が掲載されています。
一般の人が動物園に掛け合って、引き取ってもらえることはまずありません。
動物園の迷惑になるので、動物がかわいそうだと思ってもやめましょう。
市町村のホームページに問い合わせ先が記載されていますので、そちらに問い合わせてください。
【NG】何の対策もせず放置する
アナグマが近くに何度も出没していて、何の対策もせず放置すると、被害が大きくなる可能性があります。
床下に穴を掘られると、最悪の場合、家まで倒壊させてしまう危険な害獣です。
甘く見ていると、大きな損失に繋がることがありますので、なるべく早い段階でアナグマに適した対策を講じましょう。
まとめ
アナグマの見分け方や生態、アナグマを見つけたときの対処法、NG行動などについて解説しました。自分でできる対処法で被害が防げればそれが一番ですが、一時的に被害が軽減されても再発する可能性があります。限界を感じたら、害獣駆除業者に相談だけでもしてみることをお勧めします。アナグマはかわいくても危険な害獣だということを認識し、被害が拡大する前に適切な対策をしましょう。


コメント