「屋根裏から動物の鳴き声がしていて眠れない」
「畑の近くで動物の鳴き声が聞こえた。大事な作物が食べられないか心配」
「アライグマのような動物の鳴き声を聞いた。本当にアライグマなのか知りたい」
聞いたことのない動物の鳴き声が聞こえると少し気になりますよね。特に、毎日のように聞こえると被害に遭っていないか心配になってもおかしくありません。
この記事では、動物の被害に関する悩みを持つ方に向けて、アライグマの鳴き声や生態、駆除について紹介します。
- ・アライグマの鳴き声の特徴・意味
- ・他の動物の鳴き声との違い
- ・鳴き声以外の特徴
- ・アライグマの生態
- ・アライグマの騒音被害を解決する方法
アライグマはかわいいイメージがありますが、実は2005年に特定外来生物に指定されています。アライグマによる被害は、騒音被害や農作物被害、住宅被害、生態系への影響など多岐にわたります。
もしアライグマが家や畑の近くに出没していたら、被害が起きているかもしれません。アライグマの被害を放置しておくと、被害状況は悪化してしまいます。アライグマを追い出すか駆除を行って、早期解決を目指しましょう。
野生動物の被害に遭ったことのない方にもわかりやすく解説しているので、ぜひ読んでみてください。
目次
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

アライグマの鳴き声の特徴・意味
アライグマはあまり感情を出しません。そのため、嬉しいときや楽しいときに鳴くことはあまりありません。
アライグマが鳴くのは、主に威嚇や喧嘩など身に危険を感じているときです。また、子が親に空腹を知らせるときや困っているときも鳴きます。
ここでは、3種類のアライグマの鳴き声を紹介していきます。
威嚇:「シャーッ」「ウー」「ワン」
アライグマは威嚇するときに「シャーッ」と鳴きます。
犬のように「ウー」と唸ったり、「ワン」と吠えたりすることもあります。下の動画でその鳴き声を聞くことができます。
下の動画に登場するアライグマは狂犬病を発症している疑いがあります。このような鳴き方が、狂犬病に罹患している証拠にはなりません。健康なアライグマも犬のように吠えることがあるからです。
ただ、本来好戦的ではないアライグマが異常に威嚇してきたり、よだれを垂らして毛艶が悪く、フラフラと歩いているのであれば、狂犬病を発症している可能性があります。狂犬病は動物由来感染症で致死率がほぼ100%です。人から人に感染する可能性があるため、近づかないようにしましょう。
赤ちゃんの鳴き声:「クルクルクル」
アライグマの赤ちゃんは、上の動画のように「クルクルクル」という特徴的な鳴き声を出します。赤ちゃんは特に鳴くことが多いため、うるさく感じるかもしれません。
この鳴き方は、大人のアライグマも時折します。
もし上の動画のような鳴き声が聞こえたら、近くにアライグマがいる可能性が高いです。
その他の鳴き声:「キューキュー」
「キューキュー」と困ったように鳴くことがあります。上の動画の4分あたりから聞くことができます。
他の動物の鳴き声との違い
アライグマとよく間違われる動物として、以下の動物がいます。
- ・ハクビシン
- ・タヌキ
- ・アナグマ
いずれもアライグマと同じ中型哺乳類なので、知識がないと鳴き声を聞き分けるのは難しいです。
それぞれの鳴き声と見た目の特徴を順に紹介していきます。
ハクビシン

ハクビシンはアライグマよりも一回り小さいです。特徴的なのは、名前の由来である顔の白い縦線です。長いしっぽと胴長で足が短い点も、ハクビシンを見分けるポイントになります。
下の動画ではハクビシンが「キュッキュッ」と鳴く様子が見られます。ハクビシンの特徴である顔の白い縦線もしっかり確認できます。
下の動画では、ハクビシンが威嚇しているときの鳴き声を聞くことができます。「ガウッ」という太い声が特徴的です。
タヌキ

タヌキはアライグマと非常に似ています。見分けるポイントは、ひげとしっぽです。タヌキのひげは黒くて短いので、あまり目立ちません。しかしアライグマのひげは白く長いので一目でわかります。また、タヌキのしっぽには模様がありませんが、アライグマのしっぽにはしま模様があります。
下の動画では、タヌキの鳴き声を聞くことができます。タヌキは「キューン」と、子犬のような高い声で鳴きます。
アナグマ

アナグマは、50㎝前後の大きさをしています。ハクビシンに似た体系をしていますが、アナグマの方がやや丸いです。また、目の周りが黒く、耳が小さいです。ハクビシンよりもしっぽが短く、アライグマのような模様はありません。
アナグマは、「ククク」と短く鳴いたり、「グァグァグァ」とカエルのように鳴きます。下の動画でアナグマの鳴き声を聞くことができます。
もしアライグマ以外の動物でしたら、自治体への連絡の義務や駆除方法などがアライグマとは異なります。適切な駆除を行うには、駆除対象の動物の生態や被害の特徴などを調べることをおすすめします。
鳴き声以外の特徴

鳴き声以外でも、アライグマを見分けることができます。アライグマの痕跡を複数知っておくと、アライグマをより見分けやすくなるので、覚えておくとよいです。
- ・足跡
- ・食べた跡
- ・フン
順に解説していきます。
足跡

アライグマの足跡は、鋭い爪と人間の手のような形が特徴的です。
詳しくは以下の記事で解説しているので、読んでみてください。
食べた跡
アライグマは手先が器用なので、スイカやメロンなどは5~6㎝程度の穴を開けて食べます。このような食べ方は、アライグマ以外はしません。
また、力も強いのでビニールハウスや食害対策の袋を破ってしまいます。ブドウやイチゴなどがよく狙われます。
木登りも得意なので、柿などは枝の上から食べることがあります。ヘタの方に食べられた跡があれば、アライグマの仕業かもしれません。
トウモロコシは穂先に飛びついて引き寄せて食べます。そのため、根元から倒された状態になってしまいます。また、皮が綺麗に剥かれていたら、アライグマの可能性があります。
フン
アライグマのフンは直径2~3㎝、長さは5~15㎝程度です。咀嚼せずに飲み込むため、動物の骨や虫の羽、植物の種などがそのままフンに混ざっていることがあります。また、アライグマには一か所にまとめてフンをする「ため糞」と言われる習性があります。
アライグマのフンには、「アライグマ回虫」という人体に有害な寄生虫が紛れ込んでいる可能性があるため、フンやその周辺を触らないようにしましょう。
アライグマの生態

アライグマの特徴や生態を知っておくと、騒音被害の原因やその他の被害の理由がわかります。アライグマかどうか見分けるときの助けにもなるので、生態や特徴について知って損はないでしょう。
アライグマは北アメリカから輸入されてきました。1970年代のテレビアニメをきっかけに、ペットブームから需要が高まりましたが、ペット向きではなかったため、飼育放棄が各地で起きました。現在、日本国内ではほとんどの地域でアライグマの目撃情報が報告されています。
なお、アライグマに混ざって中南米原産のカニクイアライグマという動物も輸入されてきました。今のところ日本国内に定着したとの報告はありませんが、アライグマと同様に特定外来生物に指定されています。
カニクイアライグマはアライグマよりも毛色が赤く、短いです。もしカニクイアライグマを見つけたら市役所などの自治体に連絡して相談することをおすすめします。
アライグマの外見的特徴

アライグマは次のような見た目をしています。
- ・とがった耳
- ・黒いアイマスクのような模様
- ・白く長いひげ
- ・くすんだ茶色の毛
- ・足の先は白い
- ・しっぽにしま模様がある
大人のアライグマは、40~60㎝ほどの大きさで、中型哺乳類に分類されます。しっぽの長さは20~40㎝で、特徴的なしま模様があります。しま模様のあるしっぽを持つ中型哺乳類は、日本ではアライグマだけと言われています。体重は4~20㎏ほどあり、メスよりもオスの方がやや大きいです。
アライグマの生態
アライグマの基本的な生態は次のとおりです。
- ・雑食
- ・夜行性
- ・単独行動
- ・身体能力が高い
- ・繁殖能力が強い
- ・適応能力が優れている
- ・学習能力が高い
- ・寿命は約5年
順に解説していきます。
雑食
アライグマはさまざまなものを食べます。
小哺乳類・魚類・鳥類・両生類・爬虫類・昆虫類・野菜・果実・穀類など、食べられるものは多岐にわたります。動物の死骸や生ごみを食べることもあります。
春から夏まではタンパク質の豊富な動物質や旬の農作物を好んで食べます。秋になると、冬に向けてエネルギー源や脂肪分の多い植物質を多く摂取する傾向があります。冬は活動量が低下するため、身近なところで得られるものを食べるようです。森林に生息する昆虫類や、納屋などにある米や麦、米ぬかなどを食べたという調査報告が存在します。
アライグマは、特に糖度が高く嗜好性のあるものを好みます。トウモロコシやブドウ、柿、キャラメル味のスナック菓子などを好みます。そのため、アライグマを捕獲する際のおとりのエサとして、スナック菓子を使うことがあります。
夜行性
アライグマは夜行性です。夜中に活発に動くため、屋根裏などに住みつくと物音や鳴き声がしてうるさいです。冬は活動量が低下して、気温が氷点下以下になると休眠します。そのため、冬は比較的騒音被害が少ないです。しかし春になると子どもが生まれるため、騒音被害は深刻化します。
単独行動
アライグマは基本的に単独行動を取りますが、繁殖シーズンではペアを形成します。出産後、子どもは秋の終わりまで母親を行動を共にすることが多いです。
行動範囲はエサの量によって決まると言われています。エサが豊富な場所であれば行動範囲は狭くなりますが、あまりエサがとれない地域では、アライグマの行動範囲は広くなります。また、行動範囲はメスよりもオスの方が広いですが、それはオスが複数のメスと繁殖行動をとるからです。
アライグマは複数のねぐらを持ち、河川や用水路、側溝などを通って移動します。
身体能力が高い
アライグマは身体能力に優れています。
壁登りやジャンプが得意なので、簡単に屋根の上に登ることができます。木登りも得意です。
泳ぐことはできますが、穴掘りは苦手です。
バランス感覚に優れているため、細い針金の上を伝って渡ったり、登ったりすることもできます。
繁殖能力が強い
アライグマは繁殖力が強く、100頭が6年で10倍、10年後には5000頭、12年後には10000頭になると言われています。
アライグマの繁殖力の強さは、高い妊娠率が関係しています。1歳の妊娠率は約60%ですが、2歳になるとほぼ100%の確率で妊娠し、死ぬまで妊娠率が下がることなく、妊娠・出産が可能です。
1回の妊娠で3~6匹を授かりますが、妊娠の失敗や流産、捕獲などにより授乳せずに子どもを失うと、再度発情期が訪れます。
アライグマの繁殖シーズンは1~3月です。妊娠期間は54~70日と言われ、母親は秋の終りまで子どもと一緒にいます。
また、一夫多妻制なのもアライグマの数が増えやすい原因の1つです。
適応能力が優れている
アライグマは、他の動物が適応できなかった都市にも順応しました。人間の出す生ごみや食べ残し、嗜好性の強い甘いお菓子などを食料とし、ごみ荒らしや農作物被害などが起きています。
また、住宅街に住みついたアライグマは民家を住みかにすることがあります。住宅や文化財の木造建築物などは、一年を通して比較的気温が安定していて雨風をしのぐことができるため、アライグマにとっては快適な場所です。特に断熱材のある建物が好まれます。屋根裏や壁の中は子育てに向いているため、春先に物音が聞こえたら要注意です。
学習能力が高い
アライグマの学習能力が高いことで知られています。
アライグマの原産地であるカナダはトロントでも、アライグマによるごみ荒らしが問題になっていました。そこで、30億円かけて「グリーン・ビン」というアライグマ対策に特化した新しいゴミ箱を開発し、トロントのあらゆる場所に設置しました。新しいゴミ箱は功を奏し、アライグマの行方を心配する声が続出するほど、アライグマの目撃情報も少なくました。
しかし、その2年後にはアライグマがゴミ箱のロックを解除する方法を理解し、下の動画のように器用にフタのハンドルを回すことができるようになったのです。
アライグマは一度覚えたうま味は忘れません。人間の生ごみの味がアライグマにとって魅力的だったため、2年もごみ箱のロックの外し方を模索していたのでしょう。痛みや不快感によってアライグマを一時的に追い出すことはできても、再発すると言われているのはこのためです。
アライグマ対策は一筋縄ではいかないのが現実です。
寿命は約5年
諸説ありますが、野生のアライグマの寿命は約5年と言われています。中には16年生きたアライグマもいれば、2年で亡くなるアライグマもいるため、個体差があります。
1歳前の死亡率は35~48%です。日本にはアライグマの天敵となるコヨーテやオオカミなどがあまり生息していません。そのことも、アライグマの数の増加に繋がっています。
アライグマによる被害

アライグマによる被害は、騒音問題だけではありません。アライグマによる被害は大きく分けて4種類あります。
- ・住宅被害
- ・農作物被害
- ・健康被害
- ・生態系への影響
順に解説していきます。
住宅被害
民家や文化財などの木造建築物は、アライグマにとって快適なねぐらになります。雨風をしのげる上、一年を通して比較的気温が安定しているからです。特に断熱材のある家屋はアライグマに好かれます。
アライグマが住みつくと、さまざまな問題が発生します。
- ・夜行性のアライグマによる騒音被害
- ・子育てシーズンによる子どもの鳴き声
- ・ふん尿の悪臭
- ・ふん尿や湿気などが原因の建築物の損害
- ・雨漏り
- ・ダニやノミなどの健康被害
どれも平穏な生活に支障をきたす大きな問題です。
この他にも、市街地ではゴミ荒らしやふん尿による健康被害が懸念されます。
農作物被害
アライグマによる農作物被害は、年々増加傾向にあり、被害総額も増えています。特定外来生物に指定された2005年は1億5500万円でしたが、2016年には3億3600万円まで膨らみました。近年アライグマの数が増えていることから、今後も農作物被害は増えてしまうのではないかと考えられます。
よく狙われるのは、トウモロコシやスイカ、ブドウなど、糖度の高い作物です。
春から秋にかけてアライグマは活発に動くため、注意が必要です。
健康被害
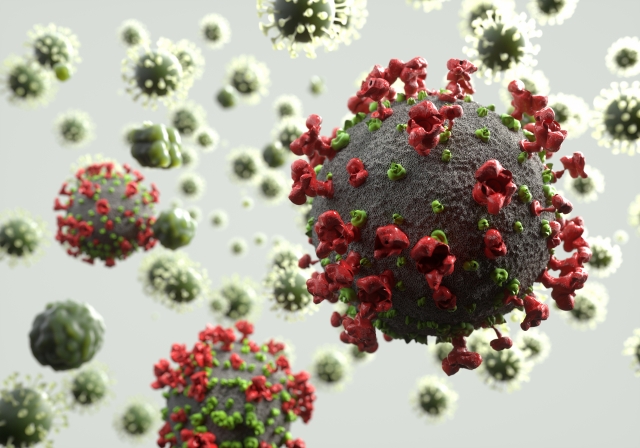
アライグマに限らず、野生動物にはさまざまな病原体が付着している可能性があり、非常に不衛生です。
以下の病原体は、アライグマが保有している可能性があります。
- ・アライグマ回虫
- ・レプトスピラ菌
- ・狂犬病ウイルス
- ・ダニやノミ
あまり耳慣れない名前だと思うので、順に解説していきます。
アライグマ回虫
アライグマ回虫とは、主にアライグマの小腸に寄生している寄生虫です。フンによって外界へ排出されます。アライグマ回虫が人体に寄生すると、致死的な中枢神経障害を起こします。
国立感染症研究所によれば、日本においては、野生のアライグマからアライグマ回虫が発見されたという報告はまだないですが、動物園や観光施設で飼育されているアライグマからは見つかっています。アメリカにおいては死者も出ています。
アライグマ回虫を持った野生のアライグマがいてもおかしくはありません。
アライグマ回虫から身を守るには、アライグマのフンやフンで汚染された場所に近づかないようにしましょう。やむをえずフンを片付ける際には、決して素手で触らないでください。フンを掴んだ道具は、煮沸消毒など熱による処理のみが有効です。
レプトスピラ菌
レプトスピラ菌は、世界中の野生動物からの発見が確認されている細菌です。尿によって外界へ排出されます。
レプトスピラ菌は、急性熱性疾患を引き起こします。症状は軽度なものから死に至るケースまで、さまざまです。日本においても発症例があります。
尿や尿で汚染された土壌に触れないようにしましょう。
狂犬病ウイルス
アライグマは狂犬病ウイルスの主要媒介者です。狂犬病を発症するとほぼ100%の確率で死んでしまいます。有効な治療法は確立されていません。
狂犬病ウイルスは、引っ掻かれたり咬まれたりしてできた傷口から侵入してきます。
狂犬病を発症しているアライグマは、見た目から少しわかります。
- ・異常に威嚇してくる
- ・よだれを垂らしている
- ・毛艶が悪い
- ・目が赤い
- ・フラフラと歩いている
上の項目にあてはまるアライグマは、狂犬病を発症している疑いがあります。襲われる危険性があるため、決して近づかず、速やかにその場を離れ、市役所などに連絡しましょう。
狂犬病に罹患していなくても、野生動物に咬まれたら健康被害の可能性があります。
万が一アライグマに襲われたら、患部を大量の水と石鹸で洗い流した後、速やかに皮膚科か形成外科を受診しましょう。リンパ腫の腫れや発熱の症状が見られる場合には、内科を受診してください。
ダニやノミ
アライグマには大量のダニやノミが付着しています。ダニやノミ自体がアレルギーを引き起こす原因になりますが、ダニやノミが病原体の媒介となって健康が脅かされる可能性があります。
例えば、ヒゼンダニによる疥癬は肌の内部に寄生して激しい痒みの原因になります。ヒゼンダニに寄生されたアライグマは毛が抜け落ちているため、弱っていてかわいそうと思っても決して近づいてはいけません。
そのほかの動物由来感染症については、以下のハンドブックが参考になります。不安な方は読んでおくとよいでしょう。
生態系への影響
特定外来生物に指定されているアライグマは、雑食のため生態系にも影響を及ぼしています。
北海道では、ニホンザリガニやエゾサンショウウオといった固有種の捕食が確認されています。また、タヌキやキツネなどと、食料を巡った競合が起きています。アオサギの巣をのっとってしまう事例は、アオサギの繁殖に大きな影響を与えています。
アライグマは勝手な都合で日本にやってきましたが、飼育放棄により野生化しました。アライグマを駆除するのはかわいそうという意見も一理あります。しかし、繁殖力の強さと天敵のいない環境下でアライグマは数を増やし、農家の方や希少な動物に被害を及ぼしています。民家に住みつけば、困るのは自分たちです。自然や生態系、人間社会を守るには、適切な個体数管理と計画的な駆除が必要なのです。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

アライグマの騒音被害を解決する方法
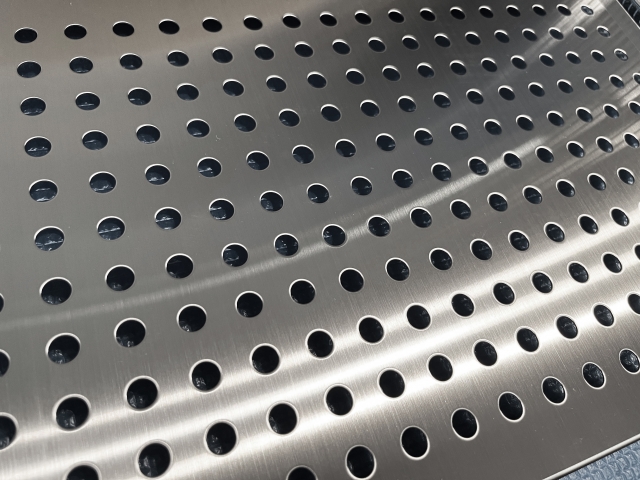
アライグマの鳴き声や足音などといった騒音被害に悩んでいる場合には、早めに被害解決策を講じましょう。
特に住宅などにアライグマが住みつくと、ふん尿の悪臭やダニなどの健康被害、ふん尿や湿気などによる家屋の損害、雨漏りなどさまざまな問題が起きます。アライグマの問題を放置しておくと、大規模な駆除やリフォームが必要になることもあるので、早めの行動が大切です。
以下では、アライグマの騒音被害に悩んでいる方向けにアライグマの追い出し方や駆除について解説します。
アライグマの追い出し方
アライグマを追い出す方法は、アライグマの心理を狙ったもので、狩猟免許がない方でも行うことができます。
手順は以下のとおりです。
- ⑴アライグマの巣を特定して駆除グッズを準備する
- ⑵追い出す準備をし、駆除グッズを使用する
- ⑶侵入経路をふさぐ
- ⑷巣の清掃・消毒を行う
詳しい追い出し方は以下の記事で解説しているので読んでみてください。
「追い出し」の注意点

駆除グッズを使用した方法も駆除方法の1つですが、厳密に言うと「追い出し」と呼ばれる手法です。
追い出しは狩猟免許なしで手軽に行えますが、一時的な効果しかないと言われています。アライグマを物理的に阻止するのではなく、あくまで心理的な効果を狙ったものだからです。また、アライグマにも個性があり、全てのアライグマに効果があるわけではありません。不快感に慣れたアライグマにも効果は期待できないでしょう。
駆除グッズはリーズナブルに試せる手軽なアライグマ対策ですが、駆除作業に慣れていない方の場合、侵入経路の塞ぎ漏れやふさぎ方が適切でないことが多く、被害が再発する可能性が高いです。再発の可能性だけでなく、巣の清掃が不十分でないことがあるため、健康被害などの二次被害が起きる可能性があります。
最初はお手軽でも、アライグマとの攻防が長く続き、ずっと騒音問題に悩まされるのは辛いことです。
そうならないためには、信頼できる害獣駆除業者に依頼するとよいです。
- 対処方法
- 業者選び
- 害獣の特定

害獣駆除業者の適切な選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ

この記事では、アライグマの鳴き声から生態、駆除の方法まで解説しました。
アライグマはあまり感情を表に出しませんが、危機に直面しているときなどに鳴きます。「クルクルクル」という鳴き声で空腹を知らせたり、「シャーッ」と威嚇したりします。興奮状態にあると、犬のように唸ったり吠えたりすることがあります。
そのほかにアライグマを見分けるポイントとして、足跡や食べた跡、フンがあります。
アライグマの足は人間の手のような形をしています。5本の指と鋭い爪の5~6㎝程度の足跡なら、アライグマのもしれません。
アライグマは手先が器用なため、スイカやメロンは開けた穴から身をほじくって食べます。力が強いため、袋を割いて中身を食べてしまうこともあります。
雑食のため、フンには動物の骨や虫の羽などがそのまま混ざっていることがあります。「ためフン」という一か所にフンを出す習性があります。
アライグマは夜行性なので、寝ているときに物音や足音、鳴き声がしてうるさいと感じることがあるのではないでしょうか。アライグマの被害を放置しておくと、家屋の損害や雨漏りなど被害が深刻化してしまいます。特に春先はアライグマの繁殖シーズンなので、被害が深刻化しやすいです。
アライグマは騒音被害だけではなく、住宅被害や農作物被害、健康被害、生態系への影響が懸念されています。
アライグマの被害解決はできるだけ早く行う必要がありますが、個人で行うにはリスクがあります。アライグマの生態に熟知していないと、侵入経路の封鎖漏れや被害の再発の可能性があります。また、アライグマに遭遇したときに襲われてしまうかもしれません。感染症などの健康リスクもあります。
そのため、アライグマの駆除はプロに依頼することをおすすめします。
アライグマの駆除経験が豊富なので、被害状況に合わせた適切な駆除を行える他、業者によっては再発防止保証制度や無料見積もりを実施しています。
アライグマの駆除は緊急対応です。緊急時は自分で解決しようとせず、安全を優先することをおすすめします。
ここまで読んでいただきありがとうございました。


コメント