住宅や菜園などを荒らす困り者のアライグマ。
鳥獣保護法によって保護されているアライグマは、害獣でも許可なく駆除することはできません。
追い出すことは個人でも可能ですが、今すぐに退治したくても自分でできる範囲は限られているし、効果が出ないこともあります。
アライグマの駆除はプロに任せるのが一番楽な方法ですが、どれも似たようなサービス内容で選ぶのが難しいですよね。
初めてアライグマの駆除を考えている方なら、業者の選び方についてよく知らないと、悪質な業者に依頼してしまうかもしれません。それに、よくわからない害獣駆除業者に対する不信感があると、中々依頼しづらいと感じる人もいると思います。
そこで、この記事では
- 業者を選ぶときのポイント8選
- おすすめの業者とその理由
について解説します。
この記事を読めば、トラブル解決をしてくれる信頼できる業者が見つかって安心できるはずです。
一刻も早く厄介なアライグマの被害を解決して、平穏な毎日を取り戻しましょう!
駆除業者を選ぶときのポイント8選
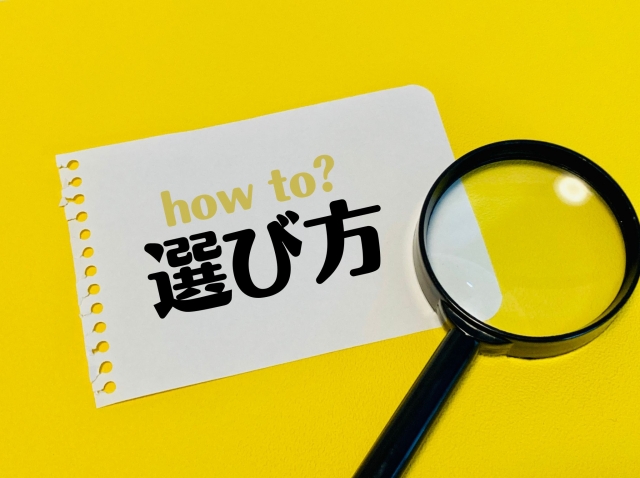
害獣駆除の業者はどれも似たようなサービスなので、害獣の被害に遭っている方に寄り添って駆除できるかどうかが、業者の見極める際のポイントになります。
特に以下のポイントを確認することが重要です。
- ・アライグマの駆除経験はあるか?
- ・サービスの内容が明確か?
- ・アフターサービスが充実しているか?
- ・利用者の口コミや評判はどうか?
- ・地域に根付いた業者か?
- ・迅速かつ丁寧な対応をしているか?
- ・駆除にかかる費用は明確か?(追加請求する可能性はないか?)
- ・複数の業者を比較検討する
順に解説していきます。
アライグマの駆除経験があること

アライグマの駆除ができる業者の中から選びましょう。
特にアライグマの駆除実績が豊富な業者がおすすめです。
駆除の実績が豊富だと、被害状況に応じた柔軟な駆除を適切に行ってくれるでしょう。
害獣駆除業者と一口に言っても、対応できる害獣の範囲はさまざまです。
どれだけ魅力的な業者だとしても、自分が被害に遭っている動物の駆除ができなければ依頼はできません。
ホームページなどを確認してアライグマの駆除に対応しているかどうか確認しましょう。
中にはホームページなどで記載がなくても、相談内容によってはアライグマの駆除を行ってくれる業者も存在します。もしどうしてもその業者でないと駆除を依頼できないという場合には、一度相談してみるのもよいかもしれません。
ただ、そのような業者は少数なので、基本的にはホームページを参考にして業者を選ぶとスムーズです。
アライグマによる被害かどうか確信が持てないという場合には、できるだけ多くの種類の害獣駆除ができる業者を選ぶと適切に対応してくれるでしょう。
その他にも、アライグマ以外の害獣も侵入していたという事例があります。
下の動画は、アライグマの駆除が完了した後にネズミが侵入を試みているものです。
できるだけ幅広い害獣・害虫に対応している業者を選んだ方が、適切な駆除をスムーズに行うことができるでしょう。
サービスの内容が分かりやすいこと
害獣駆除の費用は、作業工数や範囲によって大きく変動します。
費用だけに目が行くと、肝心の作業内容が必要最低限で、作業項目を追加しないと自分で行うのと大差がない、なんてことにもなりかねません。作業項目を追加したら、トータルで見ると予算より高額な費用がかかってしまったということもあります。
駆除サービスの内容について理解しておくと、業者選びに失敗しにくくなります。
害獣駆除の主な作業内容は、以下のとおりです。
- ・害獣の追い出し
- ・捕獲用のカゴの設置
- ・侵入口の封鎖
- ・駆除後の殺菌・消毒や清掃
害獣駆除業者のサービスは似ていますが、業者によって少しずつその内容は異なっています。
複数の業者を比較検討しているうちに、業者ごとの違いが不鮮明になって混乱してしまう人もいます。
先にどんな駆除をしてほしいか決めておくと、業者の選定作業が楽になるでしょう。
アフターサービスが充実していること
アフターサービスとは、害獣による被害の再発防止に対する保証です。
ほとんどが、保証期間内に害獣による被害が再発場合には、無償で再度駆除してくれます。
アフターサービスがある業者の方が駆除の質が高く、中には最長10年の保証をしている業者もあり、万が一再発しても安心して駆除を依頼することができます。
一方でアフターサービスがない業者は、質が低いため再発しやすく、再発する度に駆除費用がかさんでいきます。
再発防止の保証については、以下のポイントが大切です。
- ・保証期間はどのくらいか?
- ・保証内容は手厚いか?
保証期間
アライグマの被害が再発する場合は、おおよそ1年以内に起こることが多いです。
そのため1~5年程度の保証期間があれば充分な保証期間と判断できます。
保証内容
保証内容は、大きく分けて2パターンあります。
ここでは、わかりやすく「部分保証」と「侵入保証」という名前で区別します。
- 「部分保証」・・・駆除を行った場所で被害が再発したときのみ保証が適用される
- 「侵入保証」・・・建物内であれば駆除処理した場所かどうかに関係なく、また同一の害獣でない場合の再発に対しても保証が適用される
侵入保証の方が、部分保証よりも手厚い内容ですね。
いつ再発してもいいように保証期間に目を向けがちですが、期間よりも内容の方が再発した時の対応に大きく影響します。
害獣による被害が再発したときに困ったことにならないように、保証内容について事前に駆除業者に確認しましょう。
利用者の口コミや評判が高いこと
基本的にホームページや公式SNSからは、業者の良い面しか見えません。
サービス内容や料金がよくても、実際に「信頼できるかどうか」は別の問題ですよね。
ですから、気になる業者の口コミは確認するようにしましょう。
Googleの口コミや『みん評』、SNSで実際に依頼した人の率直な感想を見ることができます。
口コミの件数が極端に少ない業者の場合、情報量が少ないため、依頼してよいか判断が難しいです。また、依頼者が少なく実績が薄いということが考えられるため、依頼した後にトラブルが起きるかもしれません。
できるかぎり、口コミの件数が多い業者の中から評価が高いところを選ぶのが無難です。
地域に根付いた業者であること
地域に根付いた駆除業者の方が土地勘があり、その地域特有のアライグマの被害に対する知見が豊富です。
また、地域密着タイプだと、継続して仕事を受注できるよう丁寧で誠実な駆除サービスを心掛けているところが多いです。
害獣駆除をしていると伝わらないようにするなど、周辺住民への配慮が細やかだったり、作業の時間帯の融通が利きやすかったりします。また、距離が近いため数十分で駆け付けてくれることもあります。
できるだけ居住地エリアで駆除を行っている業者を選ぶと、気持ちよく駆除の依頼ができるでしょう。
迅速かつ丁寧な対応をしていること
害獣駆除業者の対応は、業者選びで最も大切な部分と言っても過言ではありません。
対応が雑な業者は、駆除処理も雑に行う可能性が高く、アライグマの被害で困っている依頼者に寄り添えているとは言いがたいです。
害獣駆除業者の対応については特に以下のポイントを見るとよいです。
- ・説明が的確でわかりやすいか?
- ・周辺住民への配慮が行き届いているか?
- ・清潔感を大切にしているか?
- ・安全性の高い薬品を使用しているか?
説明が的確でわかりやすい
依頼者に対して誠実に向き合っているかどうかは、説明の内容から伝わってきます。
詳細な見積もり書などを提出して明確に説明し、依頼者からの質問にも的確かつ丁寧に答えられる業者は優良と言えるでしょう。
周辺住民への配慮が行き届いている
害獣駆除をしていると周辺住民に知られると、依頼者のイメージが低下したり自分の家も被害に遭うのではないかと不安に思う人が出てきます。
周辺住民に害獣駆除を知られないように配慮できている業者は、依頼者の心情に寄り添っていると言えるでしょう。
- ・近隣住民にバレにくい時間帯に訪問し、作業を行う
- ・業者名のロゴがない社用車や作業服で施工する
特に上の点は優良な業者かどうか見極めるポイントになるので、よく確認するようにしましょう。
清潔感を大切にしている
野生動物を取り扱っているため、駆除作業中はどうしても不衛生になりがちです。
アライグマの場合、「アライグマ回虫」という人体に深刻なダメージを及ぼす寄生虫がフンに紛れていたり、ノミやダニを付着させていたりします。また、雑食のアライグマのフンは強烈な悪臭がするため、そのような臭いをまき散らされたら不快ですよね。
見積もり調査の際も、屋根裏や床下などホコリっぽいところに入るため汚れます。
そのため、以下の点を見過ごさないようにするとよいです。
- ・作業前に養生作業をしている
- ・敷物を敷いてから脚立を置く
- ・訪問時の服装のまま調査しない
周囲を汚さないよう徹底し、駆除処理した場所を清潔な状態に戻すよう最善を尽くせる業者は好ましいですね。
安全性の高い薬品を使用している
使用する薬剤の安全性や危険性について、根拠を持って説明できる業者は優良です。
害獣駆除は住宅地など人間の身近なところで行われます。害獣も人間も生き物ですから、害獣に害があるのは人間にも少なからず悪影響が出る可能性があります。
特に小さなお子さんやペットのいる家庭は、安全が保たれているのか心配になる方が多いのではないでしょうか。
資産である家屋が痛まない成分かどうかも、気になる点ですよね。
こうした依頼者の心情を理解して、安全性の確認された薬剤で駆除を実施する業者には、信頼を置くことができますね。
駆除の費用が明確であること
多くの害獣駆除業者は無料で見積もり調査を行っています。
見積もり調査を行ったら、見積書の内訳を確認しましょう。
一般的に、駆除の費用は以下の項目によって算定されます。
- ・施工内容
- ・数量
施工内容
駆除の具体的な作業内容が書かれています。
よくある項目としては、以下のものが挙げられます。
- ・追い出し
- ・捕獲用カゴ設置
- ・再侵入防止工事
- ・清掃・消毒作業
- ・損壊箇所修繕工事
各項目ごとに単価が設定されています。
複数の業者を比較するときは、単価が1つの目安になるのでよく確認しましょう。
数量
数量は、主に作業の面積や駆除する頭数、設置する捕獲用のカゴなどを表します。
業者によって作業の面積が異なることがあるので、必要な範囲を見積もりに入れているか確認するとよいです。
複数の業者を比較検討するときは、数量を統一して費用を見るようにしましょう。
あいまいな見積もり書を提示された場合、追加で費用を請求されるかもしれません。
また、見積もり額を安く見せたいために必要な施工項目を省いている業者は、適切かつ誠実な駆除を行わない可能性が高いです。
こうした業者は避けるようにしましょう。
複数の業者を比較検討する
悪質な駆除業者に依頼しないようにするには、複数の業者を比較検討するとよいです。
複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格や標準的な作業内容が判断できます。
相見積もりは、以下の点に留意して取るようにしましょう。
- ・最低でも3社に相見積もりを依頼する
- ・保証内容を比較する
また、良い業者は、必要な作業を無駄なく迅速にこなすことができます。
- ・電話での応対は親切だったか?
- ・訪問調査は丁寧に行っていたか?
- ・見積書の内容は他の業者より具体的かつ妥当か?
以上の項目を比較することで、優良な業者とそうでない業者が見分けられます。
複数人が暮らすところで被害が起きたら?
複数の同居人が暮らす家の場合、できるだけ同じ人が立ち会ったほうがスムーズに業者選びができます。
家のトラブルなので全員で対処したい気持ちもわかりますが、訪問調査や電話対応などの評価は主観的に判断されます。
複数人が個別に業者に対応すると、比較検討がむずかしくなり、業者選びに時間がかかってしまいます。
もし複数人で検討したい場合には、できるだけ全員が揃っている日程に訪問調査を依頼するとよいでしょう。
ぜひ上の項目を参考にしながら、適切な害獣駆除業者にアライグマの駆除を依頼してみてください。
悪質な業者の特徴6選
あまり考えたくないことですが、事実として悪質な害獣駆除業者は存在します。
アライグマではないですが、悪徳業者の事例として国民生活センターに寄せられたケースを紹介します。
【事例内容】
コウモリを駆除するために、「見積もり無料」「5年保証」を謡う業者に電話をした。被害状況を伝えたところ、事業者からは「実際に見ないことにはわからない。見積もり後に断ることも可能だ」と言われた。契約するかどうかは見積もりを見てから判断するつもりで、見積もりを依頼した。翌日に作業担当者が訪問し、コウモリの発生を確認した。見積もりは約10万円だったが、確認作業の際に大量のコウモリのフンを床に落とされたため、作業が断れなくなってしまった。
そのため、契約を結んでしまった。作業終了後、事業者が帰ってから作業箇所を確認してみると、コウモリの再侵入ができそうな雑な処理しかされていなかった。汚れた箇所の清掃もなく、苦慮の電話を業者にかけたが対応してもらえない。契約から8日以内にクーリング・オフを申し出ても応じてくれなかった。
このような悪徳業者に引っ掛からないために、悪徳業者の特徴6選を紹介します。
- ・誇大な表現を使用したり釣り広告を出す
- ・作業内容や費用の説明が不明確
- ・調査がすぐに終わる
- ・契約を断れないような状況を作る
- ・不必要なリフォーム工事をすすめる
- ・対応が横柄で粗野
合わせて対処法も解説するので、順に見ていきましょう。
誇大な表現を使用したり釣り広告を出す
「業界安値」や極端に低い金額の広告を張り出していたら悪徳業者の可能性を疑いましょう。
実際のサービス内容や金額とは著しく異なる内容で広告を出すことは、景品表示法に違反します。
景品表示法とは、事業者の売上増大のためにしかならないような不当な表示や過大な景品類を付けないよう規制するものです。公正な競争の中で、消費者が適正に商品やサービスを選択できることを目的に制定されました。
適正な害獣駆除は、追い出しなどの駆除作業の他に、再発防止や清掃、リフォームなどさまざまな工程を含みます。
異様に価格が安い業者は、必要な工程を削ったり、簡素な対策しか施してくれなかったりします。
業者のホームページや広告で怪しい表現を見つけたら、その業者は避けたほうが無難です。
作業内容や費用の説明が不明確
悪質な業者は、具体的な作業内容や費用を明らかにしません。
作業内容や費用をあいまいにするのは、正確な調査を行っていないか、後で高額な料金を請求しやすいようにするためと考えられます。
見積もり書の内容や質問に対する返答が適切かどうかよく確認するようにしましょう。
調査がすぐに終わる
悪徳業者は、被害状況の正確な把握をする前に作業を始める傾向があります。
事前の調査を行わないため、作業ミスや施工箇所の漏れが発生しやすくなります。
良心的な業者は、きちんと綿密な調査を行って依頼者に説明してから作業にとりかかります。
訪問調査が15分以内に終わったり、見積もり書の提示が早い場合には、悪徳業者の可能性があるので断るようにしましょう。
契約を断れないような状況を作る
上で紹介したコウモリの事例でも、契約を断れない状況に依頼者を追い込んでいましたね。
他のケースでは、
- ・調査の名目で長時間滞在する
- ・危機感をあおって駆除するよう急かしてくる
- ・契約書へのサインをすぐに求める
などが見られます。
被害の拡大を防ぐという意味で早めの駆除をすすめる業者はいますが、上記のように契約を強要する業者は自分勝手な利益を優先していると言えます。
威圧的な業者を断るには勇気が要るかもしれませんが、後のことを考えるときっぱりと断ることが賢明です。
断っても強引な勧誘が続くといったトラブルに遭ったら、迷わず消費者ホットライン「118」などに電話して相談しましょう。
消費者ホットライン「118」について
「118」に電話すれば、トラブル解決の支援を受けることができます。
状況に応じて消費生活センターで詳しく話を聞いてもらえ、業者との交渉をサポートしてもらえます。また、弁護士や福祉関連などの相談が適しているときには窓口を紹介してもらうこともできます。
不必要なリフォーム工事をすすめる
害獣駆除のときに必要なリフォームの内容はどういうものか、害獣の被害に不慣れな人には判断が難しいと思います。
複数の業者から相見積もりを取れば、適正なリフォームの場所や範囲、作業内容がわかります。
手練れな悪徳業者は、あの手この手でお金を搾取しようとしてきます。
費用が高いなどの疑問を感じたら、別の駆除業者に見積もりの依頼をするとよいです。
対応が横柄で粗野
対応が粗野な業者には、以下の特徴があります。
- ・適切な敬語が使えない
- ・威圧的な態度を取る
- ・依頼者の話を最後まで聞かない
- ・業者側の意見を押し通そうとする
電話応対のときに違和感を感じたら、その場で話を切り上げて他の業者に見積もりの依頼をするようにしましょう。
見積もり調査のときに高圧的な態度で迫られて断りづらい状況になったら、消費者ホットライン「118」などに相談するのも手です。

慣れない害獣のトラブル発生で冷静になるのは難しいですよね。
しかし焦って判断を誤ると、高額な駆除費用を請求されるかもしれません。駆除の措置も雑でアライグマの被害が収まらなかったら、どんどん状況は悪化していきます。
費用を抑えたり被害を拡大させないために早めに依頼することも大切です。
しかし、アライグマと悪徳業者という二重の被害トラブルに発展しないよう、業者選びは慎重に行ったほうが賢明です。
万が一依頼した業者とトラブルが発生したら?
業者との間でトラブルが起きたときには、以下の窓口が相談に乗ってくれます。
- ・消費者ホットライン(188)
- ・国民生活センター
- ・都道府県の消費者相談窓口
消費者ホットラインの受付時間は、平日の10時~12時、13時~16時です。
土日祝日など消費者ホットラインが開所していない日は、国民生活センターが消費者ホットライン(188)にて相談対応を行っています。
ただ、建物点検日などで休所しているときもあるため、ホームページで確認するとよいでしょう。
消費者ホットラインや国民生活センターの他に、各都道府県の消費生活センターに相談することも可能です。
各センターごとに受付時間などが異なるため、詳細は下記のリンクを参照してください。
手練れな悪質業者に個人で立ち向かうには、体力と時間が膨大にかかります。
我慢したり相手の言いなりになって泣き寝入りせずに、気になることがあったら迷わず相談窓口に連絡しましょう。
まとめ

最後に、アライグマの駆除業者を選ぶときのポイントをまとめます。
- ・アライグマの駆除経験の有無
- ・サービスの内容があいまいでないこと
- ・アフターサービスが充実していること
- ・利用者の口コミや評判がよいこと
- ・地域に根付いた業者であること
- ・迅速かつ丁寧な対応をしていること
- ・駆除にかかる費用は明確であること
- ・複数の業者を比較してから選ぶこと
特に業者の対応はよく見るようにしましょう。
害獣の排除が基本的な業務ですが、その中心にいるのは依頼者であるべきです。
害獣駆除は1つのサービス業であり、依頼主とトラブルなく駆除作業を終えようとするのが普通です。
少しでも違和感を感じたら、冷静に断って他の業者を選ぶようにしましょう。
相見積もりを取る際の注意点は以下のとおりです。
- ・最低でも3社から見積もりを取る
- ・見積書の内容を比較する
- ・誠実な対応だったか確認する
現地調査や見積もりを無料で行っている業者は今回紹介した業者以外にもたくさんいます。できるかぎり多くの業者から相見積もりを取るほうが賢明です。
インターネットの他にも、信頼できる周囲の人に相談して業者を探すのもよいです。
ただ、害獣駆除業者が多すぎて比較検討の候補すら挙げるのがままならないという方には、日本有害害獣駆除協会・防除管理協会に加盟している業者がおすすめです。
日本有害害獣駆除協会・防除管理協会は、高い駆除と施工技術を持ち、使用する薬剤の安全性に配慮している業者しか加盟することができません。
加盟する段階でふるいにかけられているわけですから、安心して相談することができますね。
おまけ:害獣駆除Q&A
害獣のトラブルでよくある意見や質問をまとめました。
- ・アライグマを見つけたらどうすればいい?
- ・アライグマを駆除するなんてかわいそう
- ・業者以外に相談して解決することはできる?
順に回答していきます。
アライグマを見つけたらどうすればいい?
アライグマを見つけたら、静かにその場から離れましょう。
アライグマに限らず野生動物にはさまざまな病原菌が潜んでいる可能性があります。アライグマの場合、「アライグマ回虫」という寄生虫がフンに紛れ込んでいることがあります。この寄生虫は、人体に寄生すると幼虫移行症を引き起こし、中枢神経に深刻なダメージを及ぼします。
その他にノミやダニも付着しているため、非常に不衛生です。
また、繁殖シーズンの1~6月になるとアライグマは気性が荒くなる傾向があります。
狂犬病に罹患している個体も凶暴化しているため、非常に危険です。
アライグマは好戦的な性格はしていませんが、凶暴化したアライグマに近づくと襲われる可能性があります。特に小さなお子さんが近づこうとしたときはすぐに引き留めてその場から離れるようにしましょう。
間違ってもえさをあげてはいけません。
必ず、静かにその場を去り、被害状況を確認しましょう。
アライグマの駆除の作業中に遭遇したときも、静かにその場から離れてください。数時間後に様子を見て、アライグマがいる気配がなければ作業を続けても大丈夫ですが、周囲への警戒は怠らないようにしてください。
もしアライグマと頻繁に出くわすようなら、危険なので害獣駆除業者などのプロに相談してください。
アライグマを駆除することはかわいそう?
アライグマは確かに罪はありません。
しかし、「かわいそうだから」、「面倒だから」という理由でアライグマの被害を放置してしまうと、どんどん状況は悪化していきます。
被害範囲が広がって駆除の費用がかかるだけではなく、そこをねぐらにしたアライグマが周辺に頻繁に出没することで、家庭菜園を荒らしたり、生態系に深刻な影響を及ぼしたりします。
アライグマの被害を放置しておくメリットはありません。
被害を発見したら、速やかに駆除の相談をすることが大切です。
殺処分したくないなどの駆除方法に関する要望があれば、業者に相談してみるとよいです。
業者以外に相談して解決することはできる?
根本的な解決を目指すなら、業者以外に相談しても実現は難しいでしょう。
市役所など各自治体に、害獣の被害相談窓口が設置されていることもありますが、市役所は害獣駆除の事業を行っていません。
市役所ができることは、以下のことだけです。
- ・害獣の被害に関する相談とアドバイス
- ・捕獲機の貸し出しや助成金の交付
- ・捕獲の申請の受理
- ・害獣駆除業者の紹介
地域によっては、捕獲道具の貸し出しや業者の紹介を行っていないこともあります。
ただ、捕獲機の貸し出しがあるからと言って、誰でもすぐに捕獲作業に取り掛かれるわけではありません。
アライグマは鳥獣保護法と外来生物法の対象になっています。
アライグマを捕獲するには、狩猟免許が必要となります。また、捕獲の際には申請書の提出が義務付けられており、簡単ではありません。
自分で追い出すことは可能?
アライグマを捕獲するには免許と許可が必要ですが、駆除グッズなどを活用して自分で追い出すことは可能です。
ただ、駆除グッズには一時的な効果しかなく、アライグマの被害が再発しやすいです。
侵入口を完璧にふさげれば、被害の再発防止には繋がるかもしれませんが、アライグマはわずかなスキマからでも侵入することができます。
害獣駆除の経験がない人は、こうしたわずかなスキマの侵入経路を見つけてふさぐことは簡単ではありません。
また、被害場所の清掃やリフォームなどを自分で行うのはかなりの手間です。
ですから、業者に依頼して早期解決を図ることが一番確実と言われています。

この記事がみなさんのお役に立てたなら幸いです。
みなさんの業者選びが成功して、アライグマによる被害の解決ができるよう応援してます!


コメント